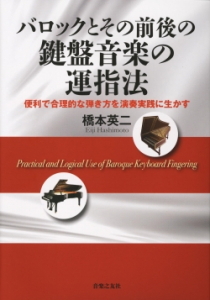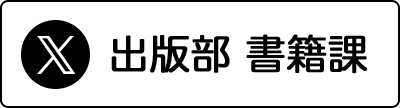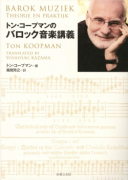内容紹介
ピリオド楽器、モダン楽器の別を問わず、バロック音楽を演奏する鍵盤楽器奏者のために、運指法の概要から個々の事例まで網羅した必携の一冊。第1部では、ドイツ、スペイン、イギリス、イタリア、フランス各国の教本・理論書の記述を、時代別に紹介。J.S.バッハ、F.クープラン、ラモー、D.スカルラッティ、C.P.E.バッハ、マールプルク、テュルクなどが実践した指使いを検証する。第2部では、各指の使用法や手の位置、アーティキュレーションと指使い、並進行、装飾音など演奏実践に即した項目別に解説。膨大な資料から要点をまとめ、実際の楽曲を含む譜例を多数掲載して、現代の奏者が演奏に生かせるよう目配りが行き届いている。R.カークパトリックの直弟子であり、シンシナティ大学名誉教授の橋本英二による、既刊『バロックから初期古典派までの音楽の奏法』に続く書き下ろし。著者の専門領域である運指法についての待望の解説書。
♪【関連情報】「専門書にチャレンジ!」掲載記事はこちら
♪【関連情報】「専門書にチャレンジ!」掲載記事はこちら
目次
ギボンズ、F.クープラン。J.S.バッハ。C.P.E.バッハ、パスクアリが書き入れた指使いの例
序説
方針
第Ⅰ部 文献の検討
第1章 バロックの運指法を学ぶ際役に立つ知識
第1節 バロック時代の運指法の意義と特徴
第2節 指使いによる表現の相違
第3節 指をさす数字
第4節 バロック時代の鍵盤楽器の説明
第5節 初期にはなぜ黒鍵の多い調を使用しなかったか
第2章 16世紀から17世紀前半にかけて
第1節 ドイツ
第2節 スペイン
第3節 イタリア
第4節 イギリス
第5節 本章で述べた運指法の比較
第3章 17世紀後半から18世紀前半にかけて
第1節 フランス
第2節 ドイツ
第3節 イタリア
第4節 イギリス
第4章 18世紀の後半
第1節 ドイツ
第2節 イタリア/イギリス
第3節 フランス
第Ⅱ部 バロック運指法の考察と応用
第5章 パッセージ奏法
第6章 各指の適切な使用法
第7章 手の位置
第8章 アーティキュレーションと指使い
第9章 片手で並進行を弾く指使い
第10章 装飾音の指使い
第11章 手の交差
第12章 指の置き換えと打ち返し
第13章 反復進行での指使い
第14章 バロック音楽の暗譜演奏の練習について
第15章 運指法の実例
あとがき
主要参考文献
索引
序説
方針
第Ⅰ部 文献の検討
第1章 バロックの運指法を学ぶ際役に立つ知識
第1節 バロック時代の運指法の意義と特徴
第2節 指使いによる表現の相違
第3節 指をさす数字
第4節 バロック時代の鍵盤楽器の説明
第5節 初期にはなぜ黒鍵の多い調を使用しなかったか
第2章 16世紀から17世紀前半にかけて
第1節 ドイツ
第2節 スペイン
第3節 イタリア
第4節 イギリス
第5節 本章で述べた運指法の比較
第3章 17世紀後半から18世紀前半にかけて
第1節 フランス
第2節 ドイツ
第3節 イタリア
第4節 イギリス
第4章 18世紀の後半
第1節 ドイツ
第2節 イタリア/イギリス
第3節 フランス
第Ⅱ部 バロック運指法の考察と応用
第5章 パッセージ奏法
第6章 各指の適切な使用法
第7章 手の位置
第8章 アーティキュレーションと指使い
第9章 片手で並進行を弾く指使い
第10章 装飾音の指使い
第11章 手の交差
第12章 指の置き換えと打ち返し
第13章 反復進行での指使い
第14章 バロック音楽の暗譜演奏の練習について
第15章 運指法の実例
あとがき
主要参考文献
索引