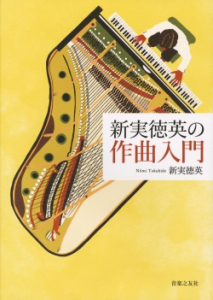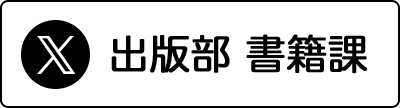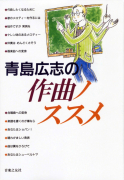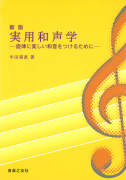内容紹介
作曲のなかでもメロディ作法を中心とした作曲入門書。最初は真似することからという方針で、第1章「古典に学ぶ」ではバッハからラヴェルまでの美しい旋律の成り立ちを調べる。第2章「僕の作曲法」では主に《白いうた 青いうた》より著者自身の旋律法、リズム形式による作曲法(ワルツ、タンゴ、ハバネラなど)を紹介。第3章「添削講座」では5つの作例のよい点と、改善点を具体的に解説。第4章「音楽の背景にあるもの」では著者の管弦楽作品が生まれるところの宇宙観、世界観について記す。全編にわたって佳い音楽をたくさん聴き、歌い、弾くことの大切さが強調される。読者対象は、作曲科以外の音大生、アマチュア楽器・声楽学習者、小中高の音楽の先生、《白いうた 青いうた》のファンをはじめとした合唱団員、指導者など、楽典の基礎知識があり、楽譜にある程度親しんでいて作曲をしてみたいと考えている人。
♪【関連情報】「専門書にチャレンジ!」掲載記事はこちら
♪【関連情報】「専門書にチャレンジ!」掲載記事はこちら
目次
序文
はじめに
Ⅰ 古典に学ぶ
バッハ
モーツァルト
ベートーヴェン
シューベルト
メンデルスゾーン
ショパン
シューマン
リスト
ブラームス
フォーレ
ドビュッシー
ラヴェル
Ⅱ 僕の作曲法
歌および器楽曲
〈ねむの木震ふ〉
〈二十歳(はたち)〉
〈なぎさ道〉⇒〈なぎさのワルツ〉
〈春〉⇒〈春のエレジー〉
〈鳥舟(とりふね)〉⇒〈鳥のシシリアーノ〉
「常套句(じょうとうく)」から旋律を作る
リズム様式
ワルツ①
ワルツ②
ハバネラ
シチリアーノ
タンゴ
Ⅲ 添削講座
和音の使い方を工夫する
「対(つい)の構造」をつくる
旋律の「行き先」を見つける
バスの動きはとても大切
D-T進行の実践例
Ⅳ 音楽の背景にあるもの――宇宙観・世界観
音像の定着/記譜法・書法
《ヘテロリズミクス――管弦楽のために》('92)
《生命連鎖》('93)
《風水――弦楽器、打楽器、チェレスタのために》
《宇宙樹(じゅ)――20絃とオーケストラのために》('96)
《焔(ほのお)の螺旋(らせん)》
《風神・雷神》
《アニマ・ソニート》('02)
《ヴァイオリン協奏曲Ⅰ――カントゥス・ヴィターリス》('03)
《協奏的交響曲――エラン・ヴィタール》('06)
おわりに――より佳(よ)い作曲のために
参考:和音記号とコードネーム
あとがき
はじめに
Ⅰ 古典に学ぶ
バッハ
モーツァルト
ベートーヴェン
シューベルト
メンデルスゾーン
ショパン
シューマン
リスト
ブラームス
フォーレ
ドビュッシー
ラヴェル
Ⅱ 僕の作曲法
歌および器楽曲
〈ねむの木震ふ〉
〈二十歳(はたち)〉
〈なぎさ道〉⇒〈なぎさのワルツ〉
〈春〉⇒〈春のエレジー〉
〈鳥舟(とりふね)〉⇒〈鳥のシシリアーノ〉
「常套句(じょうとうく)」から旋律を作る
リズム様式
ワルツ①
ワルツ②
ハバネラ
シチリアーノ
タンゴ
Ⅲ 添削講座
和音の使い方を工夫する
「対(つい)の構造」をつくる
旋律の「行き先」を見つける
バスの動きはとても大切
D-T進行の実践例
Ⅳ 音楽の背景にあるもの――宇宙観・世界観
音像の定着/記譜法・書法
《ヘテロリズミクス――管弦楽のために》('92)
《生命連鎖》('93)
《風水――弦楽器、打楽器、チェレスタのために》
《宇宙樹(じゅ)――20絃とオーケストラのために》('96)
《焔(ほのお)の螺旋(らせん)》
《風神・雷神》
《アニマ・ソニート》('02)
《ヴァイオリン協奏曲Ⅰ――カントゥス・ヴィターリス》('03)
《協奏的交響曲――エラン・ヴィタール》('06)
おわりに――より佳(よ)い作曲のために
参考:和音記号とコードネーム
あとがき