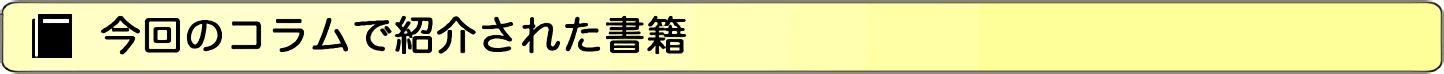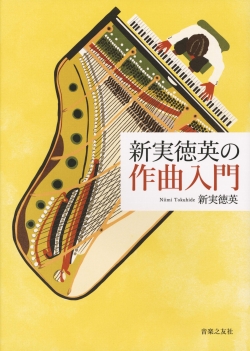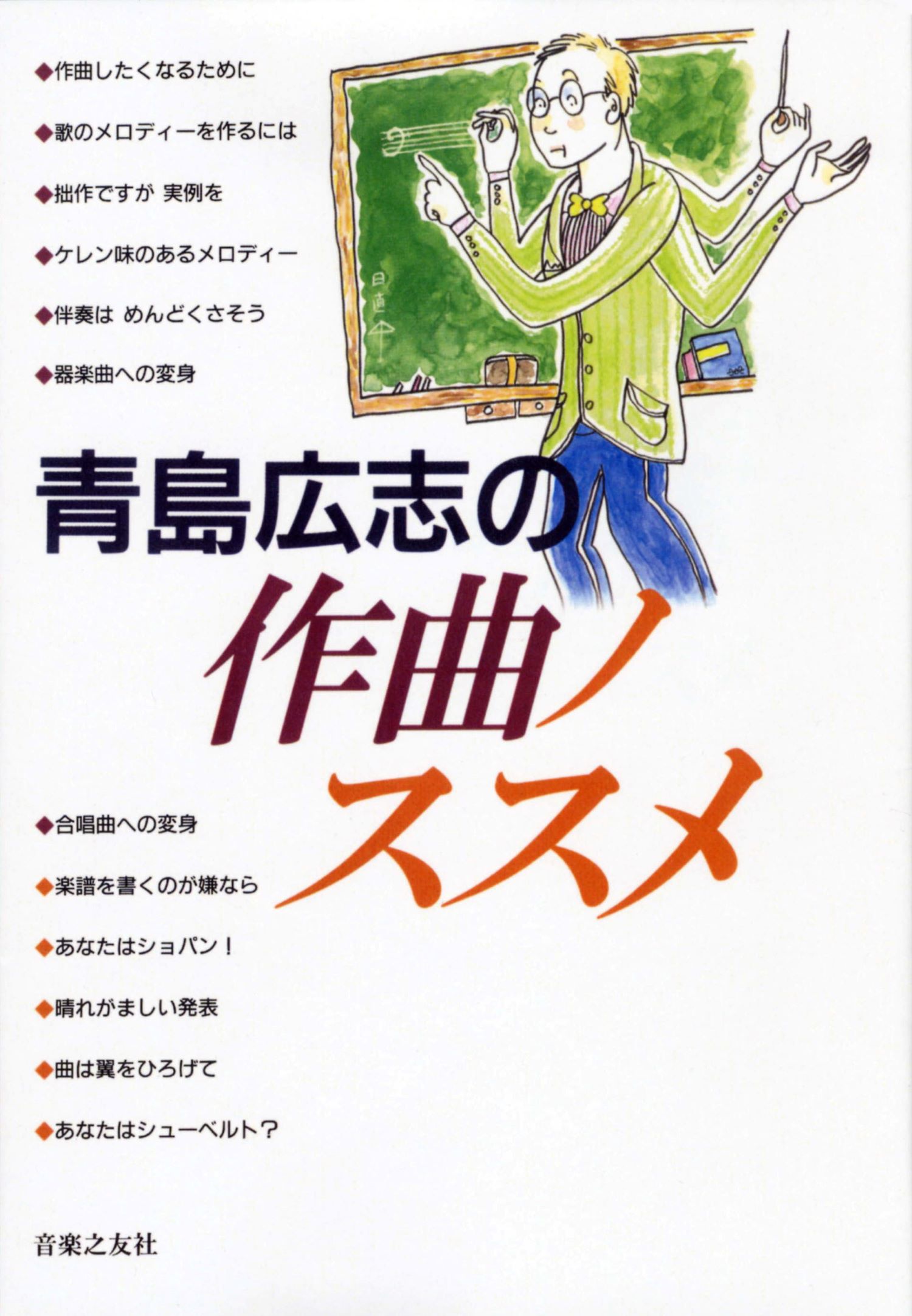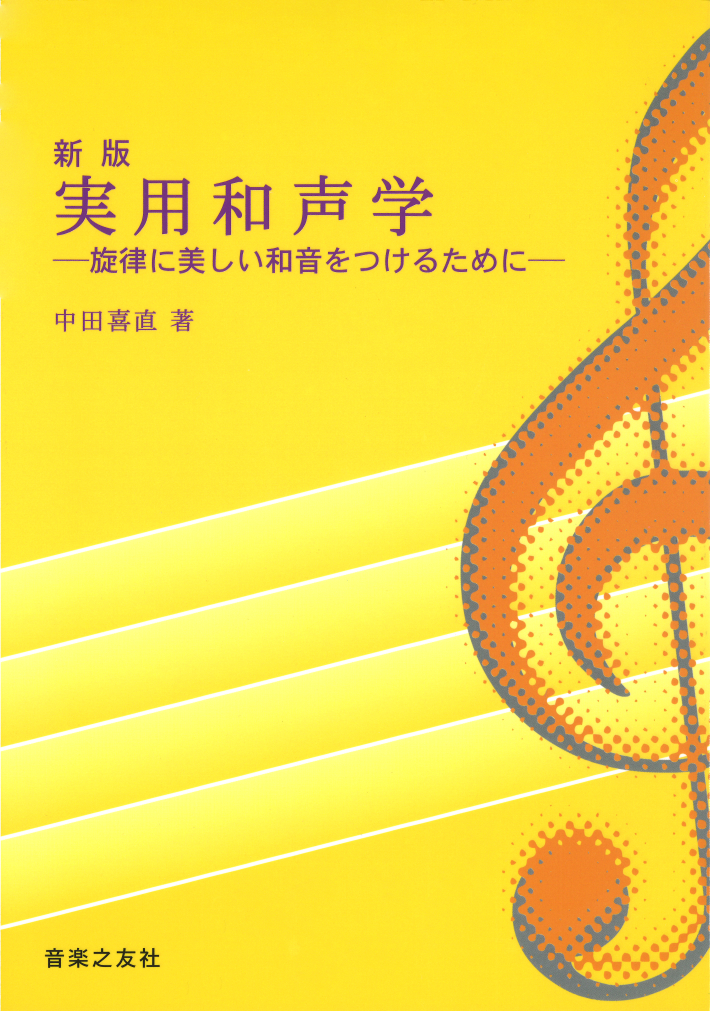第10回 作曲家の創作の秘密
音楽家、とりわけ作曲家には、エッセイの名手が多い。もう、わざわざ筆者ごときがそんなことを断らなくてもわかってるよ、と叱正が飛びそうなほど、当たり前となった命題だろう。どの作曲家のエッセイをひもといてもよい。その語り口は、プロの作家も裸足で逃げ出すほどの完成度であり、そして独特の風韻を帯びている。その文章が長かろうと短かろうと、大抵の場合はきっちりと命題があって、それに対する考察があって、結論がある。当たり前のことを書いているような気もするが、専業の作家センセイが書くエッセイの中には、ただひたすら筆の流れるまま、つれづれなるままに雑記を書き綴っているものも決して少なくない。作曲家のエッセイには、そうした漫然たるエッセイがあまり見当たらないように思う。どんなに身辺雑記的なものであっても、きちんと起承転結があり、序破急がある。思うに、この種のエッセイで、優れた知見と巧まざるユーモアを両立させていた戦後世代の作曲家の一人に、矢代秋雄が挙げられるだろう。團伊玖磨という巨大な存在のために知名度こそ低いが、そして今なお手に入れることのできる『オルフェオの死』という本の題名こそおどろおどろしいが、その説くところは深い知識と洞察に満ち、謙虚さとユーモアがその洞察を嫌みに感じさせない。そのあまりに早い死がなければ、我々は彼の手になる音楽作品、そしてその良質な文章をもっといろいろと楽しめたはずだろう。
もちろん、普段音楽の形式を考え抜いている作曲家の頭脳が、自らの文章にも無意識のうちにそうした「形式」を求めてしまうのだ、と、理由づけするのは簡単なことではある。それを職業的習性と呼んでも、まあ失礼には当たるまい。でも、きっとそれだけが全てではない。音符の代わりに文字を書き記す作曲家。その文字の並びを筆者のような一般人が目にした時に感じるのは、彼らが単語レヴェル、いや、ことによったら、ひとつひとつの文字レヴェルにまで気を配り、文意をコントロールし、言葉のありようを、あたかも和声の課題を仕上げるときのように、精緻に組み立てているのではないか、という感慨である。文章に「独特の風韻」が生まれるのは、常人では及びもつかないような、文字レヴェルに至る微調整の賜だろう。現在では活字として読めるエッセイが少なくなっているものの、ブログやツイッターを探せば、興味深く当意即妙な投稿で読み手を唸らせているのは、やはり圧倒的に作曲家なのである。
そんなサーヴィス精神に溢れた作曲家の皆さんが、あまり、いやほとんど語ってくれないジャンルがひとつだけある。それは、自分の作品における作曲技法について。そりゃそうだ、そんなの、いわば企業秘密、トップシークレットである。自分の工房の秘密をえたりかしこしと語ってくれる人など、そういるわけがない。よしんば語るにせよ、下手をしたら単なる専門用語の羅列になって、それを理解できるのは同業者だけ、ということにもなりかねない。音楽を生み出すという行為を、万人向けの言葉で語ることがいかに難しいことか。作曲は個人の感性の発露である以上など、軽々しく他人に教えられるようなモノではない、という共通認識が広く行き渡っているからでもある。
それでも作曲がどのような「技法」を駆使して行われるのかを他人に伝える、というあまりにも大きすぎる命題に対し、ドン・キホーテ的蛮勇をふるって(と言ってもあながちはずれてはいないはず)果敢に突撃する作曲家がいてくれることは、我々にとって大きな福音である。作曲家・新実徳英(にいみ・とくひで)が著した『新実徳英の作曲入門』。自然、感情、人生の経験、様々な外部の刺激にインスパイアされることで生まれた、原石のような音の連なりを自立した一つの旋律にするために、どのように磨き、形を整えるか。氏はすこし楽譜を読める人向けではあるものの、音楽に興味のある人ならば誰にでもわかるような言葉を用いて、そんな旋律の「育(はぐく)み方」を教えている。
氏がはじめに説き起こすのは、西洋の大作曲家の印象的な旋律が、どのような力学のもとにバランスを保っているのか、音域の使い方や、リズムの適切な使用が、同じ素材からできているはずの旋律を、どれだけ素晴らしいものへと変貌させることができるかについて。音楽のすばらしさというものを言葉で説明しようとする際、評論家ならずとも、普通は印象批評、文芸的な修辞に走るのが常である。かの有名な「モオツァルト」の「疾走する哀しみ」を氏も例に挙げており、そのこと自体を否定はしない。でも、名曲の秘密を旋律そのものの力学に添い、音符を使ってきちんと論理的に説明してくれる氏の手際は、きっと多くの人にとって、新鮮に感じられることだろう。そう、それは前回取り上げたアナリーゼそのものでもある。たった一つの音を上げ下げするだけで、その旋律は良くも悪くもなる。たった一つのリズムを変えるだけで、旋律の印象は180度異なってしまう。これは実際に書かれた楽譜をピアノで鳴らしてみれば、すぐに実感できるはず。
いや、筆者は新実氏の「手際の良さ」ばかりを強調しすぎたかもしれない。氏の文章の魅力は、飄々とした「飾らなさ」にもある。いや、「飾らなさ」にこそある、というべきか。自己を徹底して客体化できる能力。20歳の時に作曲を志したものの、それまでにヴァイオリンの演奏を投げ出し、ピアノもろくに弾いたことがない、といった類の暴露話は、自身にいささかでも虚栄心が残っている人間には、決して書くことができない。その飾らなさこそが、氏の文章に大きな説得力を与えている本当の源泉だろう。自然界の音から、人間の所為としての音楽が生まれ、それが芸術として昇華していく。そんな氏の思想を言葉で描いたエッセイをまとめた『風を聴く 音を聴く』をひもとけば、氏の人となりがそのままその音楽に直結していることがよく感じ取れるはずである。もっとも、ご本人に面と向かってこんなことを申し上げたら、「いやいや、ぼくはただの酒飲みですから」とご謙遜なさるような気がしないではないけれど。
新実氏が旋律の力学を説明する際に、とりあえず言葉との関係を脇に置き、それだけで自立した存在としてとらえているのに対し、『青島広志の作曲ノススメ』では、まず言葉・詞のイメージから旋律を想起せよ、と唱えているのは興味深い。作曲の初心者がメロディを生み出すに当たり、何の手がかりもない器楽曲より、歌詞のイメージ、あるいはアクセントなどの助けを得ることができる点に着目し、歌曲の作曲から始めよ、というのは、確かに一方の真理を突いている。初歩的な楽典、和声をコラム形式で補うことで、より実用的な視点から、作曲というものの実際を読者に伝えようとする青島氏の徹底したサーヴィス精神も、読んでいて心地よい。自分を客観視する視点を有しているのは新実氏と同じなのだけれど、その客観性がどこか自虐的・皮肉っぽい方向へと流れていくのが、青島氏独特の個性だろう。
この二人から時代はかなり遡るが、中田喜直が1957年に著し、その後も改訂が繰り返された『新版 実用和声学』が目指すところは、その副題「旋律に美しい和音をつけるために」が全てを語っている。こうした本が執筆された背景には、当時の日本に於いて、至る所で和声的に「間違った」「センスのない」伴奏による音楽が溢れていたことを容易に想像させる。また、当時の和声学が作曲家・研究者以外の人たちにとって、独習するにはあまりにも難しかったという事情もあっただろう。もちろん簡素にまとめられたこの本が、現在でも簡単な作曲を志そうとする人の役に立つのは言うまでもない。
作曲家という人種が、その持てる能力の全てを注ぎ込み、我々にその「工房」の秘密を教えてくれる。世の中に個性的な音楽が、より美しい形で響くことにこれらの書物が役立つのだと知れれば、もっといろいろな作曲家が、こうした試みに取り組んでくれるようになるだろう。作曲家と我々との、こうした形での対話は、まだ始まったばかりなのである。そして我々も、心の隅に浮かんだ旋律を温め、膨らませることで、この世の中をほんのちょっとだけ豊かにすることならば、いますぐにでもはじめられるはずである。