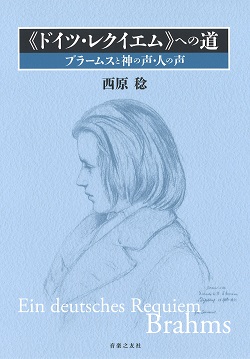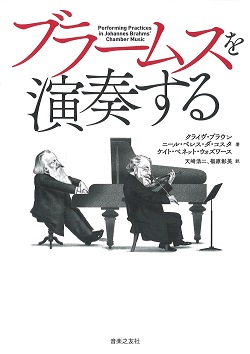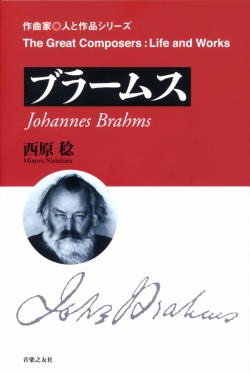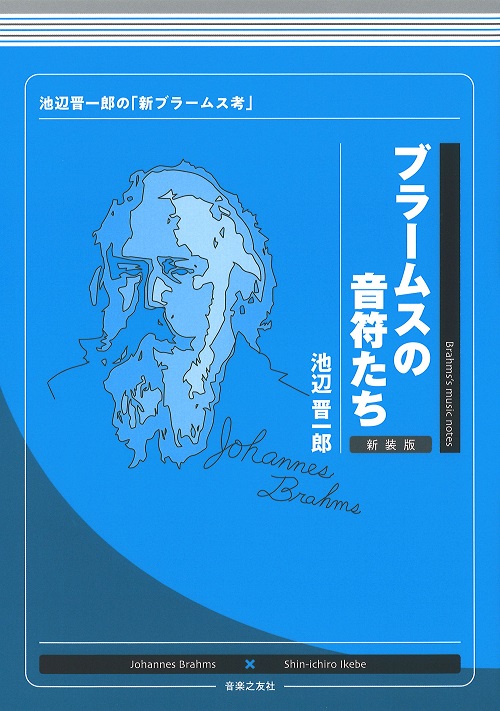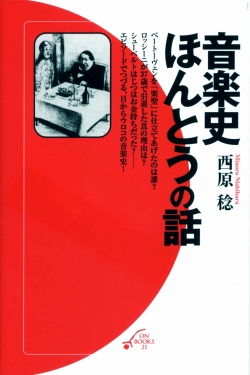第44回 ブラームスの創作世界を知る鍵は、民謡だった
まず、本稿では、本書の著者・西原稔氏を、敬意を込めて「西原先生」と呼ぶことをお許し頂きたい。桐朋学園大学に長年奉職されていた西原先生は、筆者が勤める大学にも講師として長らくお越し頂き、多大なる労力と情熱をもって学生をご指導頂いた。年に一・二度はお目にかかってお話しする機会もあり、その折は溢れんばかりの博識を披露していただいた。酒席ということもあり、舌は普段よりもなめらかに、興味深い話はとどまるところを知らず、いつも時間の経過に驚きを隠せなかったことを想い出す。
西原先生の授業は午前中だったので、授業終了後の昼休みには、当方のゼミ学生が西原先生の授業で用いられたレジュメを持って私の研究室へと足を運び、弁当を食べるのもそこそこに、いかに西原先生の授業が素晴らしかったかについて熱弁を振るうのが常だった。半期、あるいは通年でひとりの作曲家の足跡を追いかけ、その作曲家が生み出した作品をすべて網羅しようかという勢いの分厚いレジュメが、毎回配られるのである。毎週、その情報量を目の当たりにすると、西原先生が毎回、いかに充実した授業を繰り広げておられるか(そして自分がいかに怠惰に日々をやり過ごしているか)を痛感させられたものである。
西原先生が次々と上梓される近年の著作をひもとくと、こうした日々の授業での積み重ねが、そのまま驚くべき生産性の源となっていることが実感される。たとえば、作曲家の意外なエピソードから綴られる『音楽史ほんとうの話』を読むと、まさしく西原先生の日々の授業がこのような雰囲気で進められているのだろう、と容易に想像できる。だが、もちろんそのようなエピソードの羅列に終わることはない。つねに作曲家の全体像を捉えようとする大局観を失うことなく、その中で作曲家が生み出したすべての作曲活動を適切に位置づけようとする筆致は、どの著作にも共通のもの。そんな西原先生の日々の研究が、どれほどの時間をかけて生み出されてきたものなのか。同じ研究者として、西原先生の姿は遙かに仰ぎ見る巨峰に等しい。
最新刊『《ドイツ・レクイエム》への道~ブラームスと神の声・人の声』も、まさにそんな西原先生独自の視点に溢れており、他の誰にも真似のできない、唯一無二の「作品」となっている。本書は西原先生ご自身も述べておられるとおり、《ドイツ・レクイエム》のみを扱ったモノグラフ(作品論)ではない。もちろん創作過程、初演についての情報などは抜かりなく述べられているが、本作を生み出すに至った諸要素、ブラームスの故郷ハンブルクの音楽文化、ブラームスが重視した民謡と「人の声」、ブラームス自身がライフワークとしていたシュッツなどの古楽研究など、本作が生まれるに至った背景についても、可能な限りの目配りが為されている。とくに、哲学者ヘルダーが民衆の自然な「声」の発露たる民謡に重きを置いていたことにブラームスが注目し、自身も民謡を創作の根本に置いた、という指摘は、その謎多き創作世界を知るための大きな鍵となるだろう。民謡との関わりはこれまで歌曲とのそれで触れられてきた程度であり、ブラームスの創作世界全体に関わっていたとなれば、その理解はがらっと変容するはずである。
もちろん、《ドイツ・レクイエム》はブラームスのその後の創作、とくに作曲家の内面を、痛みを伴うような鋭さでえぐって生まれたような作品群の成立に、多大なる影響を与えてもいる。痛切なメッセージ性を伴う《アルト・ラプソディ》や《運命の歌》など、本作の存在なしには生まれなかっただろう。本書を通読すると、この作品が、あたかもブラームスの人生における大きな湖のように見えてくる。あらゆる支流がこの湖に注ぎ込み、そしてまた下流へと流れ出す。ひとつの作品から、ブラームスという作曲家の生涯の歩みを時には俯瞰し、時にはクローズアップし、自在の筆さばきで読み手を広大な世界へと誘ってくれる。これとても、西原先生が見渡しておられる世界のほんの一部なのだろう。ブラームスの全体像を知ることのできる『〔作曲家◎人と作品〕ブラームス』を傍らに読み進めていけば、西原先生が提示される新しい見取り図によって、ブラームスの歩みに、そしてクラシック音楽の歴史に次々と新しい風景が広がってゆくにちがいない。
西原先生が注がれる眼差しとはまた違った観点からブラームスをとらえよう、という著作からも学ぶことは多い。池辺晋一郎先生の人気シリーズ『ブラームスの音符たち』をひもとくと、作曲家がなにを考えていたのか、本当の意味で理解できるのは、やはり同じ作曲家なのだろう、と思わされる。本書を読んでから当該曲を聴くと、どれだけ豊かな旋律に溢れていようとも、それらを有機的に結びつけるモティーフや調性の力によって、曲全体の統一感、そしてブラームス特有の「美しさ」が立ち上がってくることが実感される。
そして、その作曲家自身の言葉・考え方に迫り、その音楽を演奏したい、聴きたいとおもうすべての人にとって、『ブラームスを演奏する』は格好のガイドとなる。ブラームスは完成稿以外の創作過程をすべて処分してしまうのが常だっただけに、演奏上の解釈についての同時代の証言は他の作曲家に比べてもはるかに貴重である。急激なテンポ変化を嫌い、楽譜に書かれたとおりの指示を守るように望んでいた、という著者の指摘(あとがきに端的にまとまっている)は、いまなおブラームスを適切に演奏・鑑賞するための指標として、我々は深く心に留めねばならない。
(本稿は『レコード芸術』2020年11月号に寄せた「BOOKMARK」に、加筆訂正を加えたうえで再掲したものです。)
※この記事は2021年1月に掲載致しました。
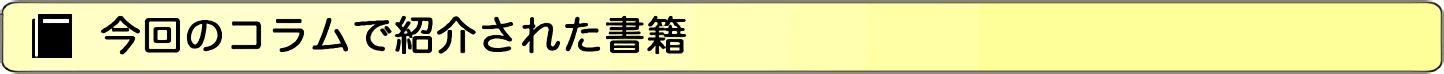
《ドイツ・レイクイエム》への道~ブラームスと神の声・人の声
ブラームスの創作の前半の頂点《ドイツ・レクイエム》は、聖書・古楽・民謡研究ほか、それまでの彼の多方面にわたる創作の成果が傾注されている。彼が若い時代から追求してきた「人の声」の思想の集大成でもあり、彼の深く考え抜かれた思想「死生観」が込められた、彼独自の宗教音楽でもある。
今日の私たちにも強い現実性をもって語りかける《ドイツ・レクイエム》は、現在でも演奏会のレパートリーとして親しまれている人気曲にもかかわらず、ブラームスは作品の草稿のほとんどを破棄したため、創作の背景がなかなか解明されなかった。
あの柔和で共感にあふれる音楽がなぜ書かれたのか。本書は、多角的な見地から《ドイツ・レクイエム》の創作の背景や、ブラームスの思想に迫る。
ブラームスを演奏する