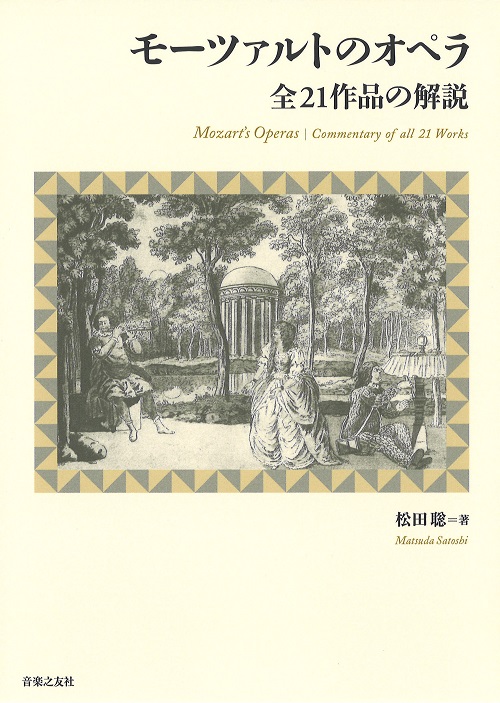第51回 独自のアプローチでオペラの魅力に迫る2冊
とにかく、長木誠司氏ほど、オペラの実演、そして映像を観倒しているひとは、少なくとも音楽関係者の界隈には存在しないだろう。かく言う評者も、まあまあオペラを観ているほうだとは思うのだが、それでも長木氏のそれにはまったくかなわない。あれほどお忙しい日々をお過ごしなのに、どうやって映像を観る時間を捻出しているのか、まったくわからない。本当に同じ24時間を生きているのだろうか。
かつて評者は、長木氏の別の本の書評を依頼された際に、いま考えてもかなり失礼だとは思うのだが、「過剰のひと」というキャッチフレーズをつけたことがある。とにかく、研究対象は云うに及ばず、その文章量も、熱量も、すべてがものすごい物量で読み手へと迫り、有無を言わさず納得させられてしまう。我ながら(失礼ではあるけれど)わりと氏の本質的な部分を衝いているのでは、と自画自賛しているキャッチフレーズではある。そんな氏の出す本はいずれも分厚さ、重量ともに読み手を圧倒するものであることが普通なので、『オペラ 愛の壊れるとき』を手に取ったときは、あれ、普通の分量の本だ、という感想をもってしまった(どこまでも失礼すぎる……)。
もちろん、その中身はまったく軽くないことを評者は知っている。『レコード芸術』誌に長年にわたって連載を続けている「ディスク遊歩人:音盤街そぞろ歩き」(2022年10月号で166回を数える)の連載でお先に読んでしまっているので、オペラについての記事をまとめた本書は、多少の加筆訂正はあると思うが、中身は(少なくとも評者にとっては)2度目にお目にかかるものばかりである。
オペラに関する本のタイトルが「愛の壊れるとき」というのは、なかなかに示唆に富んでいる。氏本人はあとがきで、ひとが歌いながら喜怒哀楽を表現し、歌いながら死ぬなどという奇妙な行動を許容するきっかけがあったはずだ、それが「愛」であろう、と断じた、と述べている(同書219頁)。
最後の章で採り上げられているのはリヒャルト・シュトラウスの《ばらの騎士》。第3幕、オックス男爵を追い払うべく、オクタヴィアンが周到な準備を重ね、ついにその計略が実現しようかというそのときに、オクタヴィアンも驚くようなタイミングで、元帥夫人がなぜ現れたのか、という問題をかなり正面から考察している。実は評者もまったく同じ疑問を持ち、演出家がこの問題にどのように取り組んだのかを、既出映像を見比べることで解こうとしたことがある。氏は、オックスの従僕が、男爵を助けるために元帥夫人に助けを求めることを思い立ち、その場を離れるというト書きを演出家がまともに採り上げることがほとんどない、と言及し、ザルツブルク州立劇場での上演で演出家ヨアヒム・ヘルツがこの問題を本気で考察している例を挙げている。もっとも、オットー・シェンク演出などぼちぼち採り上げている演出もあるので、ほとんどの演出家が無視している、というほどではないとは思うのだが、氏がこの問題を敢えて採り上げる理由は十分納得できた。ここでの、愛の「成就」「崩壊」をめぐる氏の筆致は、ぜひ本書でご確認頂きたい。若いふたり、オクタヴィアンとゾフィーの愛の成就をよそに、この作品の真の主人公である元帥夫人の諦念が、単に歳を取った自分がオクタヴィアンから身を退くということだけにあるのではない、という、本作における一歩も二歩も踏み込んだ考察こそは、あらゆるオペラを渉猟してきた氏の深い洞察に支えられており、有無を言わさぬ「過剰」なまでの説得力に満ちている。
長木氏の、あらゆるオペラを縦横無尽に論じる、全方位的な視点に支えられた著作に比べると、松田聡氏の『モーツァルトのオペラ 全21作品の解説』は、モーツァルトのオペラ作品を年代順に並べ、作品の成立背景、あらすじ、音楽的な聴きどころをわかりやすく、専門的にまとめたもの、という印象を受けるかたもおられることだろう。だが、松田氏が目指すところは、作品の成立事情と表現内容は密接に結びついていたはずとして、「モーツァルトのオペラ作品が、どういう背景から、どのようなものとして創作されたのか、という観点を中心に」する、と説明されている(同書3頁)。
全21作のオペラの解説は、作曲時期に応じて7つの章に分けられており、同時期に作曲された作品同士の関係とその主題が、歴史の流れの中から浮かび上がってくる。たとえば、これまで《後宮からの誘拐》と同時期に作曲された《カイロの鵞鳥》については、未完のままに終わってしまったという事情もあって、それ単体で論じられることはごく少なかっただろう。だが、ウィーンにおけるヨーゼフ二世のドイツ語ジングシュピールの振興策、そしてそれに付随するイタリア・オペラの上演復活という流れの中でこの2作が生まれた、という事情が歴史的な流れの中で同時に説かれることで、この2作の意義が、どのような類書よりもはっきりと、そして明解に頭の中に入ってくる。巻末に付された附録も、主要人物の紹介、アリアの楽曲形式など、この時期のオペラの諸要素を補完的に理解しやすいものとしてくれている。今後、モーツァルトについて、そのオペラ作品について知りたいという向きにとって、本書は最初に参照されるべきレファレンス的著作のひとつに挙げられるはずである。
オペラ研究に携わるもののひとりとして、オペラの魅力をどのように伝えることができるか、という手法は、他の作品論、あるいは作曲家論に比べても多彩な魅力に富んでいる、と感じる。書く側にとってはそれだけ工夫を凝らさねばならない、という悩みもあるのだが、この世界を牽引されてきたお二方の筆致には、深い研究と洞察に裏打ちされた説得力はもちろん、読者を引き込む独特の魅力に満ちている。自分には永遠にたどり着けない境地だな……、と遠い目で虚空を見つめつつ、お二方から日々学ばねば、という想いをあらたにした。自分と同じ研究領域の書評を書くのは、自分の研究にすべて跳ね返ってくるという意味でもツラいですね(本音)。
※この記事は2022年10月に掲載致しました。

オペラ 愛の壊れるとき
『レコード芸術』誌の好評連載「ディスク遊歩人」の中から、オペラに関する文章をセレクトしてまとめたもの。モーツァルトからヴァーグナー、ヴェルディ、プッチーニ、バーンスタイン、細川俊夫など古典的名作から最新話題作まで11曲を取り上げ、各作品での愛を巡る人物たちの葛藤、愛の成り立ちと挫折を、音楽とテクスト両面から読み解きながら、作曲家がいかなる創作上の、あるいは個人的な葛藤の下にいて、どのような深慮に基づいて音楽を付け、ドラマを創り上げたのかを探っている。聴き慣れたオペラに隠されていて、ふだんはなかなか見えにくいが、その実作品にとって本質的ともいえる部分をえぐり出しながら解釈し、これまでとは別の角度からオペラを観直そう、聴き直そうと思えるような視点を提供することによって、読者のオペラへの理解を深める。オペラ研究家としても名高い著者が世に問う、これまでにない観点から「オペラ」をとらえた画期的な一冊。
モーツァルトのオペラ
モーツァルトのオペラ研究の第一人者が、その全オペラを詳細に解説した日本語で初めての著作。「モーツァルトのオペラ作品事典」としても役立つ保存版。
全体は、モーツァルトのオペラ創作期を大きく7つに区分し、1章ずつを当てている。各章は、彼のオペラ創作を中心とした伝記である「創作活動」、各作品の「作品解説」からなる。
モーツァルトのオペラ創作は基本的に依頼に応じてのものだった。その作品を「天才作曲家ひとりが生み出した作品」のごとく捉えるだけではなく「往々にして偶然に与えられた、特定の状況の中で、様々な人物が関与して創作されたオペラ」として理解しようとする姿勢から、「創作活動」では創作の背景を詳しく解説している。
「作品解説」は、(1) 基本的な情報 (2)台本 (3)楽曲解説(場面ごとのあらすじ、音楽の解説も)の流れで解説。作品を構成する番号曲は、一覧表にまとめられている。「主要人名解説」ほか充実の附録、索引付き。