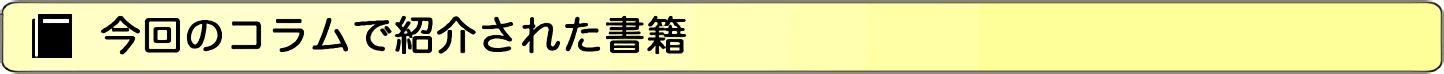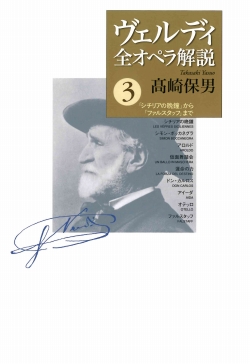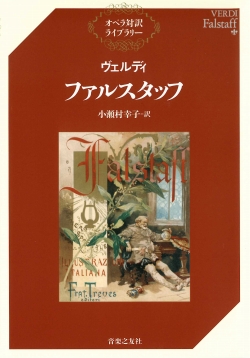第28回 ヴェルディの音楽は聴けばわかる!? とんでもない、解釈の可能性の宝庫です
ドイツの作品(というよりはワーグナーとシュトラウス)から始まった筆者のオペラ逍遙において、イタリア・オペラにたどり着いたのは比較的早かった(そのあたりの事情については、「ここ」にも書いたのでご参照いただきたい)。とにかく大学時代において、ヴェルディは《ドン・カルロ》以降のシンフォニックな作品ばかりを偏愛していた。 いまおもえば、本当に愚かなことだと思うが、ヴェルディの音楽は、威勢のいい伴奏に乗せて歌う単純なアリアばかり、というイメージをかなり長い間拭えずにいた。ワーグナーがオーケストラの力で描き出そうとしたことを、ヴェルディは歌手・声の力で描き出した、という違いは、ドイツとイタリア、ひいてはワーグナーとヴェルディの個性の違いでしかない。だがそれが音楽の優劣に結びついている、と考えてしまった若き日の自身の未熟さには、いまもなお身が縮む思いである。
ヴェルディの音楽が訴えようとしていることの「凄み」に気がつくことができたのは、《椿姫》がきっかけであったと記憶している。第1幕のはじめに置かれた有名曲〈乾杯の歌〉でさえ、その歌詞をひもとけば、真実の愛を求める青年貴族アルフレードと、かりそめの愛に生きる高級娼婦ヴィオレッタのすれ違う心が実に巧みに描かれていることがわかる。第1幕の最後では、それまで狂乱の場などで用いられていた技法であるコロラトゥーラが、ここでは真実の愛へと傾こうとするヴィオレッタの心の揺れを表す音楽として機能している。かつての音楽から次世代の音楽へ、ヴェルディも着実にその歩を進めていた。
こうしたヴェルディの全体像を眺め渡すとき、髙崎保男氏のライフワークとも言うべき『ヴェルディ 全オペラ解説』全3巻は、その格好の手引きとなってくれる。これまでもヴェルディの全作品を解説する類書は日本語でもいくつか存在したが、それらの多くはあらすじの解説に終始し、音楽的な分析や版の違いなどについては、とおりいっぺんに済まされることも多かった。髙崎氏が70年代から長い期間をかけて取り組み、このような形で完成させた各作品の解説において、もっとも特筆すべきは、その解説の冒頭に「ヴェルディにおけるこの作品の位置と意義」(章によって表現に揺れがあるのではあるが)という、序論と結論を同時に述べているかのような部分が置かれていることだろう。この部分がはじめにあることで、その後に続く成立と初演、ドラマと台本、登場人物と声種、あらすじ、音楽解説という全体の構造における特色を俯瞰し、わかりやすく提示している。このようなわかりやすさと、情報の多さ・深さが同居している本書のような解説は、なかなか他でお目にかかれるものではない。
作品によってそのフォーマットに違いがあるのは、おそらく初出の原稿の違いによるものだろう。直近の第3巻 では、以前の巻に比べてもさまざまな工夫が見られるのが興味深いところ。《オテッロ》では、そのあらすじと音楽分析がページの左側と右側にわかれており、著者がその都度作品に応じた適切な表記を目指そうとした痕跡も窺える。確かに、カヴァティーナ+カバレッタ形式のアリアが支配的な初期・中期作品でこの形式を採用するのは、いかになんでも説明過多となってしまうだろう。とくに《シモン・ボッカネグラ》や《ドン・カルロ》のような、稿と版の関係が錯綜している作品については、このような著作による明快な記述は大いにその理解を助けてくれる。
この種の解説では、作品全体の歌詞を対訳として載せることはなかなか叶わないが、その意味では「オペラ対訳ライブラリー」シリーズが、ちょうどこの種の著作と補完的な役割を果たしていることになる。以前の著作に比べて、小瀬村幸子氏、坂本鉄男氏によるヴェルディ諸作品(リゴレット、イル・トロヴァトーレ、椿姫、アイーダ、オテッロ)の訳業では、とくにその特殊なイタリア語の用法に数多くの注がつけられており、イタリア語の歌詞をより正確に『理解する』ことに重きが置かれているのが、そのもっともおおきな特徴だろう(これは同シリーズの他作曲家の対訳と比べても、その詳しさが際立っている)。とくに、《ファルスタッフ》のように、もともと下敷きとなるシェークスピア作品の理解が不可欠な作品であればなおさらのこと。第1幕第1部における「名誉」についてのファルスタッフの「演説」について、原作を参照した注は詳細をきわめている(38-39頁)。その原作を踏まえた上で、イタリア・オペラの歴史を見回しても類い希な文才を示したアッリゴ・ボーイトが、腕によりをかけた凝った文体は、それを日本語に移し替えただけの対訳だけでは、含意すべてを理解するのは難しい。ここまで詳しく、一語一語まで手に取るように解説してくれている対訳があるならば、実際にこの作品を歌う歌手の皆さんにとっても、得るところは大きいであろう。研究者にとっても作品のより深い理解のためには必要不可欠な参考資料となるはずである。
本年2月に上梓された、コンパクトな新書サイズにひとつのオペラのあらすじを1ページに収めた『新版 オペラ・オペレッタ名曲選』。本著においても、ヴェルディのオペラは、全28作品(改作を含む)のうち実に20作品が収められている。とくに、ヨーロッパでもとみに上演頻度が増えている、《リゴレット》以前の初期作品(《ロンバルディア人》《エルナーニ》《アッティラ》など)が多く含まれているところを見ても、これからのヴェルディ作品理解において、これらの作品への知識は必要不可欠と考える編者の見識が窺える。
髙崎氏も著作のあとがきで述べておられたが、作曲家生誕200年となった2013年、ヴェルディ関連の研究はヨーロッパでこそそれなりの盛り上がりを見せたが、日本でも同様の進展が見られたとは、残念ながらいいづらい。ヴェルディに限らず、イタリア・オペラ研究に従事する日本の学者の絶対数が少ない(というよりはほとんどいない)ことは以前からの傾向として存在するのだが、これには、ヴェルディの音楽はそれほど複雑ではない、聴けばわかる(従ってわざわざ研究するに値しない)、というような従来の風潮がいまなお名残としてあるのかもしれない。今回紹介したこれらの著作をすこしでもひもとけば、ヴェルディ作品がそのように単純なものではなく、いまなお研究の余地が多く残されている宝の山であることは一目瞭然である。曲が親しみやすいからといって、単純だとは限らない。19世後半のイタリア音楽をほぼ独占した感のある、力強いヴェルディの音楽世界には、まだまだ我々の知らない、解釈の可能性が無限にひらけている。
※この記事は2015年7月に掲載致しました。