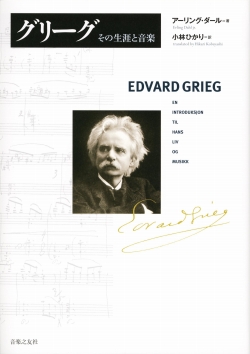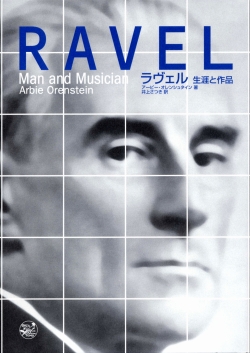第18回 新しい世代の伝記を切り拓く
まず、作曲家の伝記をひもとこうとする読者が絶対に知らねばならない事実がある。それは、「作曲家とは職人である」という事実。そして、そんな職人の日常は、政治家や芸能人のそれとは異なり、えてして単調であり、机に向かって音符を書き付ける、という営為の積み重ねに過ぎない、という事実である。
もしとある研究者が、とある作曲家に興味を持ち、その人物の生涯を巨細漏らさず知りたい、と志したとしよう。遺された一次資料、すなわち作曲家自身が書き記した日記、往復書簡、そして二次資料たる新聞記事、その他各種の記録などを積み重ねても、わかるのは「音楽そのもの」以外の公的・あるいは私的な生活であることがほとんどである。残念ながら、作曲家が日々の作曲活動と思考をどのように積み重ねたか、その工房のなかまでは(そのような場面をビデオで撮影でもしない限り)知ることはできない。あれほど私生活が派手に見えるワーグナーのような作曲家であっても、日々規則的に書斎の机に向かい、丹念に仕事を積み重ねていたのである。でなくては、質量ともにあれだけの作品を遺すことはできなかっただろう。そして、それだけ膨大な仕事を遺したワーグナーですら、工房のなかでなにをしていたのか、その詳細に立ち入ることはなまやさしいことではないのである。
つまり、作曲家の伝記を編むという営為は、その多くを結局「音楽そのもの」以外のエピソードに割かねばならない、という危険と常に隣り合わせなのである。ワーグナーがどの女と浮き名を流したとか、どれだけの国費を使い込んだとか、その種の話は確かに興味深くはある。それらの出来事が、作曲家の残した音楽に決定的な影響を与えた、という事例も数多い。だが、波瀾万丈の人生を送ったワーグナーのような作曲家などむしろ例外に属するのであって、基本的に書斎机に向かう職人の生涯は決して華やかとはいえない。時に指揮者として、ピアニストとして脚光を浴びることはあるものの、それは本来ならば「音楽そのもの」に焦点を当てるべき「作曲家」の人生を彩るサイドストーリーでしかない。いきおい、その種のサイドストーリーをなおざりにして、判明している事実だけで誠実に紡がれた作曲家の伝記は、どうしても無味乾燥なものに陥りがちである。
その意味で、今回ご紹介する三種の伝記は、敢えて読者受けするようなエピソードを羅列するのではなく、ストイックに作曲家その人、そして「音楽そのもの」へと接近しようとするアプローチを、三者三様のやり方で模索している(そしてこの三人ともに、ワーグナーほどにドラマティックな人生を歩んでいるわけではない。かろうじてドビュッシーがそれに比肩するくらいだろう)。読者の好奇心に必要以上に媚びることをしない、新しい世代の伝記のあり方の可能性を切り拓こうとする試みと言ってもよいだろう。
この三種のうち、これまでにない、もっとも特異な形で執筆されている伝記はアーリング・ダールの『グリーグ その生涯と音楽』である。本書は、グリーグの生涯を丹念に追いかけるというよりも、作曲家の生涯においてもっとも輝ける瞬間をそのまま切り取り、そこからグリーグの人となりをあぶりだすような手法を用いる。ノルウェーの民謡素材を用いつつも、それを普遍的言語へと高める努力を惜しまぬ結果生まれた《ピアノ協奏曲イ短調》作品16、そしてもっとも長大な分量が割かれる《ペール・ギュント》など、「音楽そのもの」を媒介として、そこから作曲家の生涯を浮かび上がらせていく。とりわけ、後者を巡るヘンリク・イプセンとの関係は興味深い。お互い完全に胸襟を開くわけではないものの、その志のありようをきちんと理解しあう友情は、互いの芸術を尊重するゆえの距離感なのだろう(このような詩人と音楽家の距離感の取り方は、ホフマンスタールとリヒャルト・シュトラウスのそれをある程度識る筆者にとっては、大変納得ゆくものだった)。
こうした特殊な、ある種の入門的・あるいは啓蒙的とも言うべき記述方法を採用したのは、そもそもグリーグの浩瀚な伝記は言うに及ばず、北欧音楽の研究書そのものが日本語ではまだまだ少ない(これは日本に限らず西欧諸国でも大差ないはず)という特殊事情にもよるだろう。寡作なグリーグの場合であれば、代表曲についての記述によって、その生涯をほぼ網羅できてしまう。
その全貌をいまだ知られているとは言い難いこの作曲家を多くの人に知ってもらう、という観点から見れば、この叙述方法は、考え得る幾多の方法のなかでも、もっとも適したものと思われる。まだ人目に触れることの少ないグリーグ関連の写真もふんだんに用いられており、それを見るだけでも豊かな発見に満ちている。もっとも、作曲家の人生とその作品を並置して描こうとするこの方法は、前者の体系的な叙述がある程度犠牲になることは避けられない。巻末の年譜を参照しながら読むことで、理解を補うことも必要になるだろう。作品へのアプローチも、その種の人間ドラマを紡ぐことに主眼があるために、「音楽そのもの」への言及はごく限られている。
これに対し、フランソワ・ルシュールの『伝記 クロード・ドビュッシー』(現在絶版)はいわゆる編年体形式、それも年ごとに区切るタイプの、伝記としてはもっともストイックな記述形式を採っている。膨大な資料からわかることだけを丹念に追いかけ、それを順番に記し、その相関関係から浮かび上がる推論をさらに検証すべく、新たな資料を積み重ねる。この方法ならば、かなりの程度まで、作曲家自身の思考・日常生活へ迫ることが可能になる。とりわけ多くの資料が遺されている《ペレアスとメリザンド》上演を巡る各種エピソードは、それ自身がひとつの読み物として独立した面白さに貫かれている。
これまでに編まれた伝記の記述を批判的に検討し、ドビュッシー家の経済状況をできる限りあきらかにしようとする筆致(275ページなど)を見てもわかるとおり、刊行から10年が経とうとする今でも、なお最初に参照すべき原典となる著作の座を譲っていない。ただ、人としてのドビュッシーの足跡を綿密に追いかけることが主眼となっているので、主要作品そのものの楽曲的な分析、すなわち「音楽そのもの」の記述に多くを割いていないことは、注意しておく必要があろう。
作曲家の足跡、および作品そのものの音楽的分析をともに含む、という意味で、アービー・オレンシュタインの『ラヴェル 生涯と作品』は、現在考え得る限りもっとも「よくばり」な作曲家の伝記であろう。第I部を「伝記と文化的背景」、第II部を「モーリス・ラヴェルの芸術」と題し、完全に伝記部分と作品部分を分けて記述する形をとっている本書のありようが、作曲家の伝記としてはもっともバランスが取れた、ふさわしいものかもしれない。本書の白眉は、なんといってもその自筆譜を丹念に読み込み、作曲の過程をつまびらかにした「第九章:創作過程」であろう。類書にはなかなか見られないこのみじかい章があるおかげで、筆者が常々もっとも知りたいと思っている、「音楽そのもの」を紡ぐ作曲家の「創作工房」に、ぐっと踏み込むことが可能になったのではないか。その一方で、個人的には伝記パートの記述にもう少し先行研究との比較検討を望みたかったところだが、おそらくそれは『ドビュッシー』を読んでしまった後だからこそ感じる無い物ねだりかもしれない。
西洋音楽史の回にも書いたことだが、歴史というものは、一人の著者がさまざまな歴史的事実を渉猟したうえで、そのなかから大事と思われる出来事を取捨選択して編み上げられた、ひとつの「物語」である。ある資料の読み込み方が、それを解釈する人物によっては180度異なる場合も当然存在する。そして、遺されている資料が多ければ多いほど、歴史における当該人物の重要度が高まれば高まるほど、その評価も毀誉褒貶相半ばするものとなることが多い。どうしても波瀾万丈の生涯を送ったように描かれてしまう作曲家の生涯。だが、それは読者を飽きさせないための「工夫」も込められている、と考えたうえで接するのがふさわしかろう。本に書いてあることが絶対なのではない。あくまでも著者なりの加工が加わった、伝記という「物語」なのだと考えながら読み進めるくらいでちょうどよい。
そして、「音楽そのもの」について、より広範な読者に、いかに専門用語に頼ることなく、その精髄を伝えることができるかを、筆者も含めもっともっと突き詰めて考えねばならない。作曲家の存在意義は、まず何よりも、生涯をかけて書き残した楽譜のなか、そしてそれが音となる瞬間にこそ宿るもの。三者三様の試みを通じ、「音楽そのもの」へと挑む伝記のありようは、新たな時代・新たな段階へと至ろうとしている。

グリーグ その生涯と音楽
グリーグ(Edvard Grieg, 1843-1907)の没後100年にあたる2007年に、本国ノルウェーで出版された伝記の日本語版。出世作のピアノ協奏曲や、国民的人気を獲得するに至った《ペール・ギュント》の音楽、生涯にわたって書き続けた十集からなる《抒情小曲集》といった名作を生み続けたこの作曲家の60余年の生涯を共感をもって追っている。作品にまつわる折々の作曲家の姿を、ノルウェーの自然や風土の中で丹念に描いたことで、「現代のグリーグ演奏につながる質の高い評伝」との評価を得た1冊である。著者が長年奉職したエドヴァルド・グリーグ博物館をはじめとする関係機関から提供された豊富な図版は、いずれも貴重で、しかも質が高く、本書の価値をますます高める特質のひとつである。
ラヴェル 生涯と作品
原著はもともと1975年のラヴェル生誕100年記念としてコロンビア大学出版局からハードカヴァーとして刊行され、ラヴェル研究文献の決定版として欧米で長期にわたり高い評価を得てきたもので、邦訳の登場が待たれていた。本書においては、1990年に原著の作品目録部分に多くの新情報を追加し、改訂版として刊行されたペーパーバック版(ドーバー社版)を底本としている。
第Ⅰ部では、その生涯を6つの時代に分けて、挫折と栄光、音楽家としての成長、さまざまな作品の創作時エピソードなどをつぶさに追っている。また第Ⅱ部ではこの天才作曲家の創作の秘密に迫る。比較的寡作の作曲家ながら、第8章の全作品解説は圧巻である。写真や自筆譜など、貴重な図版も多数収載。巻末の作品目録は、自筆譜情報、出版、初演等に関するデータが詳しい。