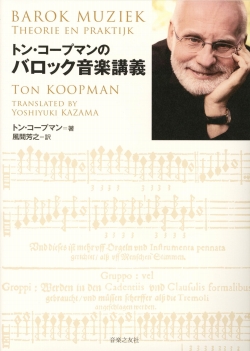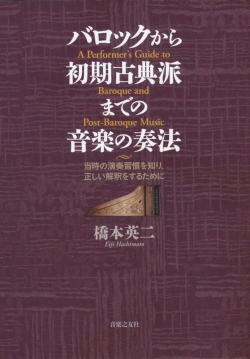第13回 バロック音楽演奏の息吹に触れる
今回、本欄を書くにあたって、筆者がいわゆる「古楽奏法」「ピリオド奏法」による演奏に巡り会ったのはいつだったかを思い出そうと試みたが、正確な年代は結局思い出せなかった。いずれにせよ、大学生時代に(90年代半ば)ガーディナーかアーノンクールの演奏をCDで聴いたのが、その最初であろうと記憶している。
自分の無知・センスのなさをさらけ出すようで恥ずかしいのだが、正直に書いておかねばならないだろう。はじめて「ピリオド奏法」なるものに触れたときの印象は、はっきり言って最悪だった。幼少期から演奏してきたピアノとヴァイオリンの影響で、当時の筆者の絶対音感はA=442Hzに完全に固定してしまっていた(現在ではだいぶ柔軟に聴くことができるようになってはきたけれど)。彼らの奏でる音楽は、端的に言ってしまえば全て半音低く聞こえてしまう。音楽の善し悪しを鑑賞する以前に、そうした団体の奏でる音楽に、批判を承知で書くならば「生理的嫌悪感」を抱いてしまった。思えば不幸な出会いであった。
今ならば、こんな話も懺悔とともに語ることができる。いまや「ピリオド奏法」による演奏は、クラシック界の確固たる一翼を占め、普通のモダン・オーケストラでもピリオド奏法を試みる団体が現れる時代となった。いや、むしろそのような分け方すら、いまや時代錯誤として批難されかねない。ピアノ、ヴァイオリンを初めとする器楽奏者にも、モダン楽器とピリオド楽器をその時々に応じて使い分け、それぞれに適した奏法で弾き分けることのできる奏者までが登場しはじめている。オペラの世界ではモンテヴェルディはいうまでもなく、ヘンデル、ラモーなどが完全に復権し、各地の歌劇場が優れた上演の数々を繰り広げている。時代は確実にひとつの区切りを迎えた。
ピリオド奏法を志す演奏家は、程度の差こそあれ、自らが演奏する時代の奏法に対して研究を重ね、音楽学者も顔負けの造詣を有していることがほとんどであろう。というよりも、それを勉強し、研究せねば、理想とする演奏に近づくことは叶わない。そして、バロック音楽とはいかなるものなのか、現在我々が「クラシック音楽」として消費している古典派以降の音楽との違いはどこにあるのか、その奏法を復活させて演奏させることにどのような意味があるのか、といった諸点について、ニコラウス・アーノンクールとトン・コープマン以上に雄弁に語ってくれる一流演奏家はいない。
限りなく乱暴に言ってしまえば、アーノンクールが『古楽とは何か――言語としての音楽』で訴えたいこと、そしてコープマンが『トン・コープマンのバロック音楽講義』で訴えたいことはまったく重なっている。二人いわく、バロック音楽の何たるかを知るには、当然その音楽史のみならず、同時代の政治史、社会史にも目配りし、イタリアとフランス、ドイツ、イギリスの文化的違いを知り、さらにその各国における実際の演奏法の違いを考慮せねばならない。
バロック音楽と古典派以降の音楽の違いとして、アーノンクールとコープマンの眼差しは、まず何よりもトリルやモルデントといった装飾音の奏法、そしてアーティキュレーションやテンポの問題に向けられる。過剰なまでの表現への意志、そしてその可能性を追求したバロック音楽。そうした表現の多彩さこそが、バロック音楽の本質にもつながっているはず(バロックという言葉の由来たる「いびつな真珠」という言葉を思い浮かべれば、こうした過剰さも腑に落ちよう)。少しでもピアノに取り組んだ人ならば、バッハやスカルラッティの鍵盤作品に記されている装飾音をどのように演奏すべきか、ピアノの先生から学んだご記憶がおありだろう。この種の演奏法は、様々に残っている記録をたよりに辿っていくより方法がない。バロック時代の演奏法の伝統が一旦途絶えてしまった以上、それを再現することの途方もない困難は、想像するにあまりある。アーノンクールも、コープマンも、それぞれのやりかたで、そして言葉という形で苦闘の跡を残してくれていることは、われわれ読者にとって、えてして演奏家側視点からのまとまった意見表明を目にする機会が少ないことを考慮すれば、本当に貴重なことである。
バロック音楽の表現法を学ぶには、装飾音の問題のみならず、まだまだ大きな課題をいくつも乗り越えなければならない。誰もがすぐに思いつくのは「通奏低音」であろう。さらには「修辞法」。特定の表現を表すために用いられる、ある特定の音型のことを指す。「ため息の音型」などが有名ではあるが、こうした音型をあらかじめ学び、それを愉しむという文化的な素地がほとんど途絶えてしまった以上、われわれはそれを新たに学び直すより他にない。
さらには鍵盤楽器における「調律法」の問題もある。そもそも、一オクターブの中を12等分しても、その全ての音程が純正(完璧に調和する音程比による響き)にはならない。17世紀末、数ある教会旋法の中から長音階だけが残り、同じ音階を調性の違いによって描き分けるため、鍵盤楽器においては、平均律という調律のシステムがその後の音楽を支配するに至るが、それまでは、長三度で正しい響きを出すことを優先する「中全音律」、あるいは完全5度の響きを少しずつ狭めることで他の音程を純正に保った「ヴェルクマイスター調律法」などが用いられていた。当時の楽器を用いて演奏する以上、こうした調律法の問題も、避けて通ることはできない。バッハがロ短調という調性をここぞというときに選んだ理由も、この調律法との関連で説明されるようになってきている昨今、われわれ聴き手の側も、決して無関心でいることはできなくなっている。
そんなわれわれに対し、アーノンクールは「さらに励めよ」と叱咤激励し、コープマンは「こんなに愉しいよ」とやさしく励ましてくれる、という筆致の違いはあるものの、バロック音楽の豊穣な世界へと導いてくれる。二人は、それぞれのやり方で、なぜこれらの知識がバロック音楽の理解、演奏に必要なのかを、手を変え品を変え力説してくれるが、実際にその知識を著作の中で綿密に教えてくれる訳ではない。純粋に理論的な側面を知りたい場合、これまではそれぞれの問題を詳説している海外の学術論文をひもとくより他に、ほとんど手だてがなかった。だが、橋本英二氏の労作『バロックから初期古典派までの音楽の奏法――当時の演奏習慣を知り、正しい解釈をするために』によって、これまで掲げてきた装飾音、テンポ、アーティキュレーション、調律法、そして通奏低音の実際までを、たった一冊の本で俯瞰できるようになった。もちろん、自分が演奏する際に気になる箇所を、事典的に参照する使い方が想定されてはいるが、バロック音楽に少しでも興味と関心がある人ならば、是非通読をお薦めしたい。
こうした演奏法の探求を通じてようやく、われわれ現代人は、17世紀・18世紀という時代を知り、その時代に生きた人の考え方を知り、そしてその社会の息吹を知ることができる。大学生時代の自分は、明らかにこの努力を放棄していたのだ。遙かなる時代と文化の違いを乗り越え、その時代に生きたひとたちの息吹に触れることこそ、歴史を学ぶ醍醐味でもある。われわれが学べば学ぶほど、過去からのメッセージは、より豊かに心の中へと届くようになるはずなのだから。

トン・コープマンのバロック音楽講義
世界的に著名なオルガニスト、チェンバロ奏者、指揮者である著者が、バロック音楽の演奏解釈法を簡潔にまとめたもの。演奏家が作曲家の意図を最大限に汲むためには、作曲当時の人々の音楽に対する考え方、記譜や演奏の習慣を知ることが必要で、そのためには演奏者自らが原典資料、当時の文献などを渉猟して自分なりの結論を出さねばならない。本書は、各国語による原典資料のファクシミリを利用して、それら原典の読み方、解釈の仕方を読者にアドバイスするもので、日本でますます隆盛を極めるオリジナル楽器演奏への貴重な指針となることはもちろん、音楽大学などでの演奏習慣についての授業では格好の教材となろう。これまで音楽学者たちによって書かれてきたバロック音楽の演奏法研究とは異なる、演奏家ならではの実践的な視点が本書の最大の魅力であろう。
バロックから初期古典派までの音楽の奏法――当時の演奏習慣を知り、正しい解釈をするために
20世紀後半の古楽研究の発展とそれにともなう古楽ブームの結果、古い音楽を演奏するさいには、装飾音、リズム、ダイナミクス、アーティキュレーションなどについて、当時の演奏習慣にもとづいた適切な解釈をすることが常識となった。現在では、古楽器演奏家はもとより、モダン楽器の演奏家のあいだでもこうした考え方が一般的となっている。 本書は、プロ、アマチュアを問わず、バロック音楽から初期古典派までの音楽を演奏するさいに留意すべきさまざまな事項を、J. S. バッハ、F. クープラン、ラモー、クヴァンツ、テュルク、C. P. E. バッハ、L. モーツァルトなどの当時の教本(理論書)の記述にもとづきながら、実践的に解説した、わが国でははじめての書。