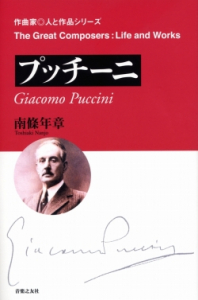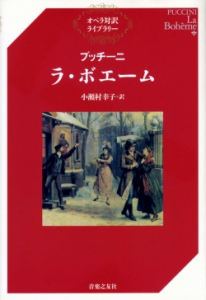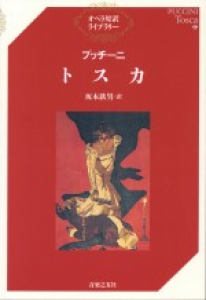広瀬 大介(ひろせ・だいすけ)
1973年生。青山学院大学教授。日本リヒャルト・シュトラウス協会常務理事・事務局長。
著書に『楽譜でわかる クラシック音楽の歴史』『もっときわめる!1曲1冊シリーズ ③ ワーグナー:《トリスタンとイゾルデ》』(以上、音楽之友社)、『リヒャルト・シュトラウス 自画像としてのオペラ――《無口な女》の成立史と音楽』(アルテスパブリッシング)、『帝国のオペラ――《ニーベルングの指環》から《ばらの騎士》まで』(河出書房新社)、訳書にベルリオーズ、シュトラウス『管弦楽法』(音楽之友社)など。
さらに各種音楽媒体などへの寄稿のほか、曲目解説・ライナーノーツの執筆、オペラ公演・映像の字幕対訳を多数手がけている。
Twitter ID: @dhirose
第57回 観客を揺さぶり続けて1世紀、プッチーニ作品への扉
普段ドイツ・オペラのことばかりを書いているため、イタリア・オペラのことについて書かせて頂けるのは、それだけで普段よりも少しアドレナリンが多めに出てしまう。それがジャコモ・プッチーニ(1858-1924)とその作品となれば、なおさらである。どんな気分の時でも、《ラ・ボエーム》の幕切れ、ミミの死にしばらく気付かないロドルフォの振る舞いに涙しないことはないし、《トスカ》の第2幕のスカルピア殺害で手に汗握らないことはない。これから何が起こるのかなど歌詞まで諳んずる勢いで知っているのに、こちらの感情に直接手を突っ込んで揺さぶってくる感覚。こればかりは、ワーグナーでもヴェルディでも味わえない、プッチーニの音楽が持つ独特の魅力であろう。プッチーニの音楽の最大の特徴は、音楽的な進行と、舞台上の時間進行が完全にシンクロしている点にある。先ほど例に挙げた《トスカ》のスカルピア殺害で言えば、事細かなト書きと音楽の進行は完全に計算され尽くされており、音楽そのものが時間の進行を縮めたり長くしたりすることは基本的にあまりない。20世紀的、映画的リアリズムが台頭してくる世の中において、この音楽的処理は大変斬新に聞こえたであろうことは疑いなく、そしていまでもその力を喪っていない。
そして、今年は没後100年。これを機に、まずはこの世界観をひとりでもおおくのひとに味わってもらいたいと感じている。
プッチーニの伝記、あるいは数多く伝わるエピソードを読むほどに感じるのは、台本に対する異様なまでのこだわりである。完璧主義、というべきなのかもしれないが、自身が納得するまで台本作家たちに訂正を迫ったと言われる。仕事相手を疲弊させ、神経衰弱へと追い込むほどの作曲家の執拗さが、あの名作の数々につながった、ということなのだろう。
台本を手がけたのは、初期の2作品《妖精ヴィッリ》《エドガール》がフェルディナンド・フォンターナ、《マノン・レスコー》から《ラ・ボエーム》《トスカ》《蝶々夫人》まで、もっとも上演機会の多い作品群がルイージ・イッリカとジュゼッペ・ジャコーザ、《西部の娘》だけが(あまり言及される機会がないので知名度も低いが)グエルフォ・チヴィニーニとカルロ・ザンガリーニ、《つばめ》《外套》がジュゼッペ・アダーミ、《修道女アンジェリカ》《ジャンニ・スキッキ》がジョヴァッキーノ・フォルツァーノ、《トゥーランドット》が先述のアダーミとレナート・シモーニである。リスト的に名前を列挙してしまったが、大体前半生がイッリカとジャコーザのコンビ、後半生がアダーミ、という感じになるだろう。
プッチーニが、台本選択の段階から推敲、完成に至るまで、いかに苛酷な条件を突きつけたかは、ぜひ『プッチーニ』(作曲家◎人と作品) の伝記的記述をご参照いただきたい。台本選択という問題を考えるにあたっては、家族的親密さでプッチーニを庇護し続けたジュリオ・リコルディがかなりの影響力を及ぼしており、19世紀、20世紀の同業オペラ作曲家に比べても、あまりその点に関する自由を持ち合わせていなかった、という特殊事情があった、というあたりはおさえておくべきかもしれない。著者の南條年章氏による、歌手ならではの踏み込んだ考察も、類書にない特徴のひとつだろう。
また、輝くような才能の持ち主だったプッチーニに対する悪意や嫉妬、それによる上演妨害の試みも常軌を逸するレヴェルであったことにも驚かされる。時代を牽引する存在であったからこそ集める注目、あるいは嫉妬や反感といったプレッシャーと戦わねばならなかったつらさも、前述の完璧主義の背景にあったことが窺われよう。
『スタンダード・オペラ鑑賞ブック【新装版】イタリア・オペラ』 は、1998年に発行された同名の書籍が、内容の改訂を経て四半世紀ぶりに新装版として生まれ変わったものである。当時20歳台だった評者も、この本を片手に、多くの作品を知ることができて、大変懐かしい想いとともにこの新装版をひもといた。かつては上下巻2冊として発行されていたが、作品を厳選したうえで1冊に集約されて復刊した。
同書に収録されているプッチーニ作品は、《ラ・ボエーム》、《トスカ》、《蝶々夫人》、《トゥーランドット》の4種。奇しくも、「オペラ対訳ライブラリーシリーズ」 で採り上げられている4作品と共通している。この対訳シリーズのもっとも大きな特徴として、原語と日本語をブロックごとに配置していること、そして、訳者の個性はもちろんそれぞれに出てはいるが、基本的には原語の直訳に近い表現を用いて、原語そのものの理解を助ける方針を採っていることが挙げられよう。
とりわけ、『ラ・ボエーム』 における小瀬村幸子氏の飜訳においては、原語の細かなニュアンスに至るまで解説する詳細な注が付けられており、これを読むだけでも、台本の行間に、登場人物のあらゆる心情が込められていることが実感される。多くの日本人歌手にとっても避けて通れない本作の理解を深めるためには、これらの懇切丁寧な解説が、自身の音楽表現を高め、そして深めるためには必須のものとなることだろう。同じく、ドイツ語で同様の仕事に取り組んでいる評者にとっても、仕事に対する丁寧な取り組みには見習うべき点が多く、これらの仕事を積み重ねた小瀬村氏、そしてもちろん戸口幸策氏、坂本鉄男氏にも、心からの敬意を捧げたい。
最後にもうひとつ。プッチーニそのひとのイメージとして、評者の中で抜きがたく居座り続けているのは、2008年に制作されたパオロ・ベンヴェヌーティ、パオラ・バローニ監督による映画『プッチーニの愛人』である。有名な「ドーリア・マンフレディ事件」を扱った作品(事件の内容はぜひ伝記でご参照のほど)で、登場人物の心情の多くは、役者自身が発する台詞よりはむしろ、実際の手紙を読むモノローグとして伝えられるのが新鮮であった。華やかなプレイボーイといった先入観でプッチーニを捉えていると、これらの本をひもといたときと同じく、その芸術家的な内省のありようとのギャップに、少なからず驚かされるのではなかろうか。もし興味と機会があれば、この映画も是非一見をお勧めしたい。
※この記事は2024年4月に掲載致しました。