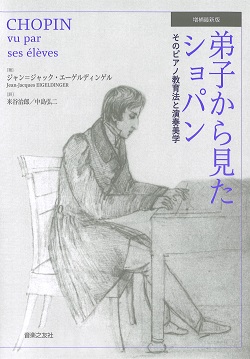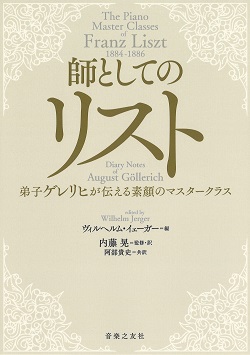第48回 “教育者”としてのショパンとリストに触れる
かつて落語家の立川談志がこんなことを云っていたという。曰く、「芸は盗むもの」というが、芸を盗むには盗む側にもキャリアが必要、と。確かにそうである。初学者のうちは、教えられたことを吸収するので精一杯。とてもじゃないが、盗む暇なんてない。言葉で教えられることなく、師匠の芸を弟子が「盗む」には、師匠の芸術の本質を見抜くほどの鋭い目が必要になる。
師匠と仰ぐ人物が、当代一とされるほど偉大な存在であるならば、その難しさはさらに大きくなるだろう。そもそも、そのような人物に教えてもらうとなれば、その師匠から見込まれるような存在でなくてはならない。弟子間でも競争心は芽生えるはず。偉大な師匠と相対して、貴重な教えを受けたとしても、弟子にそれを受け取る準備が整っていなければ、結局は無駄骨になってしまう。
弟子の側に、それを受け取る準備が整っていなかったとしても、師匠からの教えを無にしない方法のひとつとして、その師匠からの教えを、一言一句書き留めておく、というのは有効な方法だろう。いまはその教えを消化できなくとも、時の経過とともにみずからが成長し、師匠の見ていた風景を自分も見られるようになることで、その言葉が意味するところをはっきりと理解できるようにもなるはず。
フレデリク・ショパン、あるいはフランツ・リストといった音楽史上の偉大な人物には、作曲家、あるいは演奏家としての実像に触れる機会は数多く提供されている。だが、後進を育てる教育者としての実像を知ることのできる機会は決して多くはない。師と弟子だけの空間におけるやりとりは表に出てくる性質のものではない以上、しかたのないことではある。とはいえ、偉大な師への敬愛ゆえに、その言葉を細大漏らさず手に入れるために、そして、その教えを自分よりもさらに後世のひとたちに遺すために、それらを綿密に書き留めてくれた弟子たちには、いまあらためて感謝を捧げずにはいられない。
驚くべき厚さを有する『弟子から見たショパン:そのピアノ教育法と演奏美学』(増補改訂版)
をひもとけば、この本が、決して数多いとは言えない師の言葉を伝える弟子たちの証言をより確かに理解するため、注や付録によって埋め尽くされていることがわかる。おそらくは、ショパンは自分の考えていること、自分が音楽を表現する上で心がけていることを、言葉ではなく音楽そのもので伝えることのほうを好んでいたのだろう。ショパン自身は、未完に終わってはいるものの、みずからの経験に裏打ちされたピアノ奏法を文章のかたちで後世に伝えようとしていた。だが、それが未完に終わってしまっている、という事実そのものが、言葉を紡ぐことに倦(う)みがちなこの作曲家の心性を表している。
もちろん、ショパンが弟子たちに与えた助言からは、この音楽家がピアノという楽器をどのように捉え、どのような音楽を理想としていたのか、さまざまな側面が見えてくる。その多面性をどのようにとらえるかについては、実際に本書をひもといた読者それぞれに委ねたいが、評者としては、ショパンが鍵盤楽器であるピアノから、いかにして「歌」の要素を引き出そうと試みていたかを強調しておきたい。
1830年代におけるベルカント唱法、そしてそれを活かしたオペラに魅了されていたショパンは、自作にカンタービレやルバートの手法を採り入れ、演奏では旋律を「歌う」ことに徹する。ピアノからオーケストラのような響きを導き出そうとする、ドイツ的な、効果を重視するようなやりかたには背を向けようとするショパンの音楽の神髄が、自身のさまざまな言葉で説明されている。
音楽において「効果」を求めることに本能的な嫌悪感を示していたショパン。その嫌悪感の源泉には、フランツ・リストという、ピアノの演奏にヴィルトゥオーゾ的効果を求める同時代人の存在もあったのだろう。だが、そのようなヴィルトゥオーゾ・ピアニストとしての活躍を1840年代で終え、その後はヴァイマールなどで作曲・指揮活動に比重を移していったリストの行く末を、ショパンは見つめることはできなかった。晩年のリストは、多くの弟子たちを無報酬で教える卓越した教育者として、すぐれたピアニストを世の中に送り出している。
最晩年のリストに私淑し、レッスンを中心とした師との交流を、細大漏らさず書き遺した弟子がいる。アウグスト・ゲレリヒ。1882年にワーグナー《パルジファル》のバイロイト初演時にリストと初対面を果たし、1886年のバイロイトでの客死時にもその枕頭に立ち会っている。
当時のリストは、ドイツ・ヴァイマール、イタリア・ローマ、ハンガリー・ブダペストの3都市を順に経巡る生活を続けていた。1884〜86年、ゲレリヒはまさにその師を追いかけるように付き従い、そのエッセンスを吸収すべく、自身のレッスンのみならず、他の弟子(といっても、そのいずれもが当代きってのピアニストである)のレッスンも聴講し、その折の師の言葉を書き留めている。作品の本質を短い言葉で指し示すこともあれば、弟子たちが持参した曲への思い出話に花が咲くこともある。奏法を手取り足取り教えるような弟子はいないが故に、そして自分に残された時間が少ないと自覚しているが故に、寛いだ雰囲気の中で、自身の経験とセンスをすべて後進に注ぎ込もうとするリストの生き様が、実感とともに伝わってくる。
ショパンとリスト、それぞれの肉声が伝わってくるような今回の著作を同時に読み進め、評者としては、リスト最晩年のさばけた個性により大きな親しみを覚えた。一方でショパンのコメントには、どうしても神経質さが目立ってしまうのではあるが、それ故に音楽への真摯さも伝わってくる。師の技を「盗もう」と必死に格闘する弟子たちの姿もまた、昔から今へと変わらずに繰り返されている。
※この記事は2022年2月に掲載致しました。

弟子から見たショパン 増補最新版
そのピアノ教育法と演奏美学
本書は、初版発売以降の約40年にわたる研究成果が反映された第4版に、未刊の原資料を加えた邦訳新版である。
直接の弟子を中心に、同時代の作曲家、演奏家、親しかった人たちなどの証言、楽譜、書簡集などから、疑いの余地のない資料のみを抽出。それらを丁寧に分析しながらピアノ技法とその教育法に対するショパンの考え方を読み取り、それらがどのような音楽的美学的背景から生まれたものかを探っていく。多くの資料に目を通すにつれ、個々の資料の持つ意味がより鮮明に浮かび上がっていくよう、資料類を著者による詳細な注釈とは別に独立した形で提供するという配慮もなされている。
「ショパンの真の意図を知りたい」という著者の強い思いから生まれた“ショパン研究の決定版”!