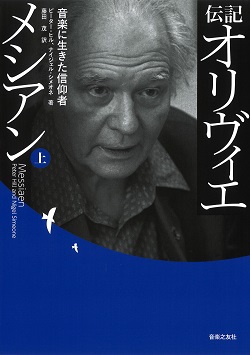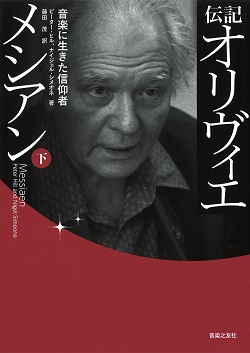第45回 メシアンの知られざる実像が、新たな資料から明らかになる!
21世紀に入ったのはつい最近のような気がしていたが、すでに20年が過ぎてしまった。近年の音楽界を観ていると、いわゆる第二次世界大戦以降の音楽を「現代音楽」として一括りにするような論調が徐々に薄らぎ、むしろ「20世紀音楽」という新しい枠組みの中で論じようとする方法論が次第に勢いを増しているように感じられる。
戦後、セリー音楽を率いたピエール・ブーレーズやカールハインツ・シュトックハウゼンなどがそれぞれに開拓した前衛音楽を筆頭に、さまざまな作曲家がその活躍場所を拡げていった。そのような中で、戦後世代作曲家の精神的支柱でもあり、多くが師と仰いだオリヴィエ・メシアンはその核のような存在でありつつ、個々の作品の知名度こそ高いが、作曲家その人の実像などにはあまり触れられることがなかったようにも思われる。
これは、メシアンが自身について語ることを避けていた、ということを意味しない。むしろ、自身の音楽理論については饒舌なまでに語り尽くすタイプの作曲家であった。だが、それは作品そのものの説明であり、それを作るまでにどのような思考を続けたのか、どのような状況で作曲されたのか、という部分を明かすものではなかった。
いわば、自作品・自身の音楽について語るメシアンはいても、それを生み出すメシアンそのひとが浮き上がってくるような言説ではなかった、というべきだろう。外に現れた部分を語ることには積極的でも、それよりも中には踏み込ませなかった。後年になるに従って、メシアンは秘密主義をよりいっそう徹底させ、自身がいまどのような作品を作っているのかすら、決して明かそうとはしなかった。超大作となった歌劇『アッシジの聖フランチェスコ』の制作は長年にわたって続けられたが、最初の6年間、その計画を知っていたのは委嘱したパリ・オペラ座の音楽監督ロルフ・リーバーマンとメシアン本人だけだったという。
本書のユニークなポイントとして強調されているのは、夫人イヴォンヌ・ロリオが所有していた夫の遺品を多数用いることによって、メシアンのこれまで知られていなかった実像をあきらかにした、という点に尽きる。作品のスケッチ、往復書簡、講演や講義のためのノート、メモ書き、1939年以来つけてきた手帳のメモ書き(ほぼ日記としての役割を果たす)。これらの資料を通じ、有名な作品の数々とその言説の背後に隠れていたメシアンそのひとの生きざまが、ようやく「歴史」として俯瞰できるようになった、ということになる。大げさに言うならば、これまでメシアンの作品について語り継がれてきたことのほぼすべてに対して、新たな視点からの学術的検証が入り(もちろんメシアン自身が遺したこれらの遺品・言説もその妥当性においてチェックの対象となる)、語り伝えられてきたエピソードについてもさまざまな訂正が試みられている。
そのもっとも端的な例として、ここでは有名な《時の終わりの四重奏曲》を例に引いておこう。メシアンが第二次世界大戦でドイツ軍の捕虜となり、ゲルリッツ収容所で暮らしていた際、音楽好きのドイツ軍将校の助力を得てすべての作業を免除され、この作品を作曲・初演した、というエピソードは、これまでさまざまに語られてきた。大筋においてその内容にちがいはないのだが、本書において新たに判明した事実をまとめると、実態は次のようなものであったとされている。
・ふたつの楽章(賛歌、ヴァイオリンとチェロ)はすでに作曲されていた作品の転用であった。
・「鳥たちの深淵」(クラリネット)はトゥルの仮設キャンプで作られたもの。
・ゲルリッツではこの3つの楽器による「間奏曲」から書きはじめられた。
・メシアンにピアノが用意されると、本格的に四重奏部分(残りの4つの楽章)が作られた。
・メシアンは収容所での初演の際、「聴衆は5,000人で、チェロには弦が3本しかなかった」と回想しているが、この時のチェロ奏者だったエチエンヌ・パスキエは、会場のキャパシティは400人程度で、チェロにはちゃんと4本の弦があった、と証言している。
とくに初演時のエピソードについては、パスキエの証言を事実とするならば、メシアン自身がこの時の出来事を脚色して語っていることになる。筆者自身も旧来の説明をそのまま鵜呑みにしていたところもあるので、最新研究に基づく更新が必須となろう。歴史を歴史として語ることの困難を、あらためて思い知らされる。
前妻クレール・デルボスの闘病生活と息子パスカルとの関係、後妻イヴォンヌ・ロリオとの二人三脚の活動、ブーレーズやシュトックハウゼンなど弟子たちとの関係など、どのページを開いても新鮮な発見と驚きに満ちている。訳者・藤田茂氏の紡ぐ自然で読みやすい日本語も、よりよい理解をもたらす一助となるだろう。なにより、20世紀最大の音楽家のひとり、オリヴィエ・メシアンが、活き活きとした「人間」として我々の前にようやくその姿を現したことに、自分でも驚くほどの知的興奮を感じている。
※この記事は2021年4月に掲載致しました。
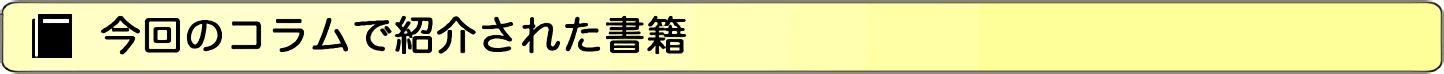
伝記 オリヴィエ・メシアン(上)
音楽に生きた信仰者
20世紀フランスを代表する作曲家、オリヴィエ・メシアン(1908-92)の伝記。ロリオ=メシアン夫人が生前に管理していた膨大な資料をもとに、これまで公式発言の奥に隠れて見えなかった人間メシアンの真実に迫る。東京音楽大学教授・現代フランス音楽研究の第一人者の藤田茂が、読みやすい文章で訳した。メシアンのプライベート写真や手稿譜などの貴重な資料を上下巻で合計約200点掲載。上巻では、メシアンの誕生から50代はじめまでが描かれる。詩と音楽に見守られて育った少年が、いかにして音楽家として自己を確立していくのか。活動と瞑想のあいだを往復しながら世代をリードする存在となった作曲家が、何を探し、何を見出し、何を作り出したのか。2度の世界大戦に見舞われた20世紀という複雑な時代を、神の愛とともに生きた人間の実像が鮮烈に浮かび上がる。
伝記 オリヴィエ・メシアン(下)
音楽に生きた信仰者
20世紀フランスを代表する作曲家、オリヴィエ・メシアン(1908-92)の伝記。ロリオ=メシアン夫人が生前に管理していた膨大な資料をもとに、これまで公式発言の奥に隠れて見えなかった人間メシアンの真実に迫る。東京音楽大学教授・現代フランス音楽研究の第一人者の藤田茂が、読みやすい文章で訳した。メシアンのプライベート写真や手稿譜などの貴重な資料を上下巻で合計約200点掲載。下巻では、50代はじめから83歳で亡くなるまでが描かれる。いまや国家的な作曲家となったメシアンが、いかにして社会的な栄誉の向こうに創作の孤独を守ろうとしたのか。そして、畢生の大作となったオペラ《アッシジの聖フランチェスコ》の後に、いかなる危機をくぐり抜けて、この世の先を見つめるようになったのか。神の愛にとどまりつづけた人間の人生のドキュメントがここにある。作品目録・参考文献・索引つき。