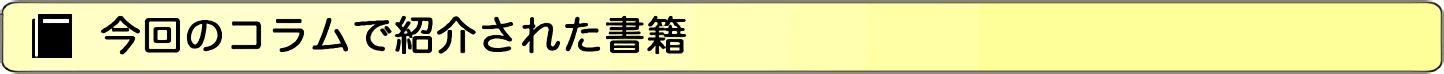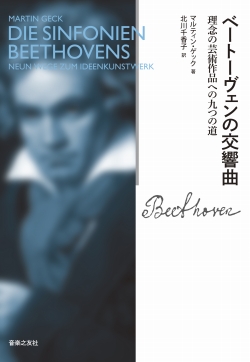第38回 碩学ゲックが語るベートーヴェン交響曲
浜の真砂は尽きるとも、世にベートーヴェンの種は尽きまじ。演奏会に出かければ、CDを購入すれば、その曲目解説はきちんと新しい書き下ろし。新刊案内にその名を冠した本を見ないことはほとんどなく、しかも最新の知見をもとにあらたな発見を得ることも少なくない。クラシックに親しむようになった当初から、折に触れてその音楽を聴き続け、そして今となっては知り尽くしたようでいて、決してその全体像にたどり着くことはできない。少なくとも自分にとって、ベートーヴェンはそんな存在であり続けている。
そしてまた、ベートーヴェンの新刊が登場した。だが、浩瀚な記載を期待してしまう「交響曲」という題材にもかかわらず、コンパクトな、本文わずか160ページの著書というのはかなり意外。しかもその著者が、ドイツ音楽学の碩学であり、齢傘寿を越えたいまも、なお旺盛な活動を続けているマルティン・ゲックというのだから、なおさらであろう。すでにゲックの著作としては、2013~14年に上下巻から成る『ワーグナー』(岩波書店)が飜訳されたばかりである。共訳者に名を連ねておられる北川千香子さんが、この情熱的な音楽学者の口跡を、今回のべートーヴェンでもそのままに伝えてくれるのは本当にありがたいことである。
この著作全体は、ひとつのまとまりをもって書かれたというよりは、個々のテーマについて、ゲックが普段から考えていたことを集めた、アンソロジー的性格を持ち合わせている。曲ごとの紹介もさることながら、その前におかれたベートーヴェンと社会的な関わり(とりわけナポレオン・ボナパルトとの関係には興味深い考察が捧げられている)も、テーマ別の読み切りエッセイといった性格が強い。決して簡単ではないゲックの論旨を追いかけるには、興味の湧いた部分から順不同に読むのがよいだろう。個々の曲についても、いわゆる曲目解説というよりは、その曲が生まれた社会的・歴史的背景、そしてそれが実際の音楽にどのように反映しているか、といった視点から書かれており、広範な知識を有した著者にしか執筆し得ない内容であることはいうまでもない。
個人的にもっとも納得し、なおかつ新鮮な着眼点を与えてくれたのは、「ジャン・パウル風の「山羊の足」――「ロマン派」ベートーヴェンというパラダイム」と題された章である(37-44頁)。ジャン・パウル、ベートーヴェンと同時代の人たちが、高名な詩人とこの作曲家が共通して持ち合わせていると見なした要素、すなわち「幻想的なもの、それゆえに規則に逆らうものを登場させたり、高尚なスタイルと低俗なスタイルを混ぜ合わせたり、暗示や省略を盛り込んだり、両極的な感情の状態の間を思いがけなく転化したりすることを好む両者の創作の流儀」(37頁)は、ベートーヴェンを一義的に「ウィーン古典派」の作曲家と名付ける伝統的な時代区分に対して、大きな変革を迫るものでもある。詳しくはぜひ本文にあたって頂きたいが、真の創造的芸術家は、伝統を踏まえた上で、その伝統を縦横に駆使しながら自己の個性を発揮していくものである、という本質が、手を変え品を変え、ゲックの博識から論証されていく。たったひとつの工夫であっても、それが見るもの、見る角度によってはまったく違った様相を呈するものであること、そしてそれこそが、優れた芸術について語る言説が次から次へと生まれてくることの意味なのだろう。そして、ここに、もうひとつ、ベートーヴェンについて語る小文が生まれたわけで……。
※この記事は2018年1月に掲載致しました。