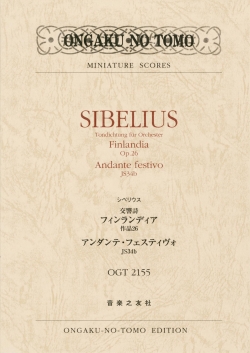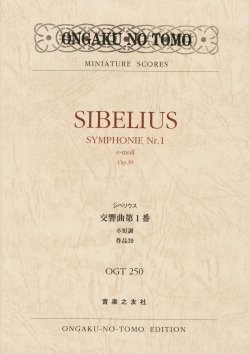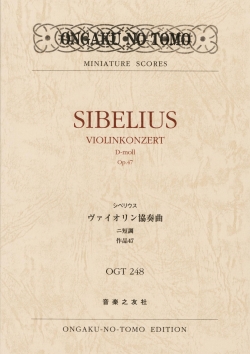第31回 シベリウスが背負った時代と作品への帰結
十数年ぶりにジャン・シベリウス(1865-1957)の《フィンランディア》のスコアを手に取り、学生の頃、この作品の95小節目から始まる勇壮かつ崇高な旋律が大好きで、わけもなく心を躍らせていたことを思い出す。なにより、ハ短調から変イ長調へと移り変わるその響きが、一条の光が差し込むように感じられた。そして、その旋律の後半部分が、ほとんど形を変えぬまま、まったく違った曲想で登場する、いわゆる「賛歌」の部分(132小節目)では、敬虔な気持ちにすらなった。まるで宗教的な祈りが込められているかのようなこの旋律には、単なるロシアからの独立をこころざすフィンランド人の矜恃、といったもの以上の何かが込められているのではないか、と。
そんな自分のもやもやとした想いがどこからやってくるものなのか、シベリウスを中心とした音楽を専門とされている神部智氏は、丁寧な筆致で明瞭な言葉に紡いで下さっている。《フィンランディア》の解説にもはっきりと、この作品の最後のクライマックス、変イ長調の和音進行が I-IV-I、典型的なアーメン終止であることが指摘されている。なるほど、確かに、言われてみれば確かにそうだけれど、言われないと気に留めないくらいさりげなくもある。この作品が、戦闘的にフィンランドの独立を勝ち取ろう、とするような鼻息の荒いものではなく、むしろ祖国に対する愛をより静かに、より深く表現するための方法であったのだろう。シベリウスの作品に、声高に何かを叫ぶような身振りは似合わない。
ジャン・シベリウスは、昨年2015年で生誕150周年を迎えた。この記念年に上梓された神部氏の著作『シベリウスの交響詩とその時代』における氏のねらいを挙げるならば、それは自身で示しておられるとおり、「『フィンランドの国民作曲家』というこれまでのイメージでは捉えきれない、複雑なパーソナリティを持ったシベリウスの人間像、作曲家像」(282ページ)を描く、ということに尽きるのだろう。そして、シベリウスという人物がそのキャリアの初期において、ロシアとフィンランドの対立、というナショナリズムの図式に、自身の意志とは無関係に巻き込まれ、「フィンランドの国民作曲家」という看板を背負わざるを得なかったことに思いを致すべきだろう。19世紀半ばにおいて、ヴェルディがイタリアを、ワーグナーがドイツを、そしてスメタナやドヴォルザークがチェコを背負わねばならなかったように、シベリウスもフィンランドを背負わねばならなかった、いや、背負わされたのである。
再び神部氏の著作から一部を引用し、シベリウスが抱えていた現実と理想の違いに思いを致してみよう。「シベリウスがこうした社会の混乱期にあえて抽象的な交響曲の創作へと向かったのは、(中略)タイトルや標題、テクストが作品世界に導入されない以上、そこでは原則的に無用な音楽外的想念が持ち込まれる余地もないからである。つまりシベリウスにおける交響曲の選択は、ナショナリズムを標榜する時代に身をおかざるをえなかった音楽家が、自らの芸術作品の美的自律性を擁護する目的も担っていたと考えられるのである。」(131ページ) そして、シベリウスが自身を《フィンランディア》や《悲しきワルツ》の作曲家として(のみ)認識されることにも神経質であった、と。
1917年のフィンランドの独立は、予想に反して重苦しい雰囲気に終始したという。食糧難やインフレ、ひいては翌18年のフィンランド内戦の勃発によってフィンランドは新たな危機を迎え、シベリウス自身も一時期フィンランド南部を制圧した赤衛隊に命を狙われているのではないか、という不安の中で暮らさざるを得なかった。自作に対しても厳しい批判の目を向けるシベリウスの創作ペースはさらに落ち、孤独感に苛まれる。そんな中で最後にシベリウスがたどり着いた《タピオラ》は、「単一楽章という形式構成のうちにあらゆる要素を凝縮しようとした晩年期シベリウスの『作曲理念の帰結』でもあった。その意味で《タピオラ》は、伝統的なジャンルのコンセプトとシベリウスの目指した表現世界の両者が見事に融合した、まことに類い希な音楽といえるだろう」(279ページ)と結論づけている。20世紀初頭には交響詩と交響曲の作曲原理を明確に分けて考えようとしたシベリウスが、最終的にはその両者を融合する地点にまでたどり着いている。ここには、20世紀前半という、人類史においてもっとも多くの人間の運命を翻弄したであろう世界大戦の時代において、その荒波に飲まれつつも、最終的には自己の内面を見つめ、たどり着くべき場所へとたどり着いたひとりの芸術家の生き様を見ることができる。
タイトルにあるとおり、「交響詩とその時代」のみを採り上げている本書においては、まだ交響曲における諸相が本格的に採り上げられるには至っていない。だが、すでに神部氏が手がけるポケットスコアの解説は『第1番』『第2番』『第3番』まで進行しており、この研究成果もやがて、まとまった形で読める日が来るに違いない。また『ヴァイオリン協奏曲』の解説においても、初稿から改訂稿の成立に至るまで、なぜシベリウスが敢えてヴァイオリンパートを「やさしく」するかたちでの改訂に踏み切ったのか、興味深い考察は一読の価値がある。
※この記事は2016年4月に掲載致しました。

シベリウス 交響詩 フィンランディア 作品26
シベリウスの数ある作品のなかでも、もっとも人口に膾炙し、吹奏楽版への編曲や歌詞を伴った準国歌として親しまれている作品と、作曲家の創作期最晩年に書かれた小品を組み合わせて刊行。「フィンランディア」はロシアの属領化政策に抵抗して企画された民族的歴史劇のための音楽。のちにパリで開催された万国博覧会でヘルシンキのオーケストラが演奏して、注目を集めた。一方、「アンダンテ…」は、交響曲第6番・第7番と作曲時期を同じくし、オリジナルの弦楽四重奏曲から作曲者自身が編曲した弦楽合奏版は、ニューヨークで開催されていた時の万博で全世界へラジオ中継された。解説は、気鋭のシベリウス研究者、茨城大学の神部智。これまでに論じられたことのない視点を掲げ、また各種資料に典拠しながら、これらの曲の新しい聴き方を提示する。