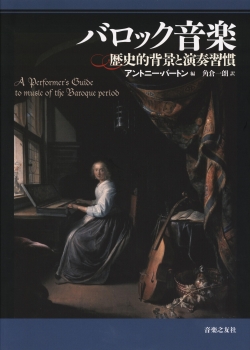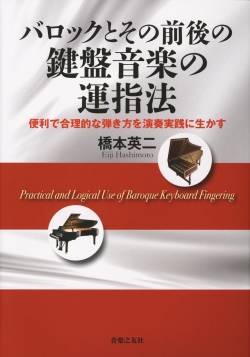第27回 最先端の演奏家に、時代様式による演奏を学ぶ
いささか季節外れな話題で恐縮だが、筆者が学生生活を過ごした大学では、クリスマス前にキャンドル・ライト・サーヴィスという礼拝を行なうのが通例となっていた。指揮を執られるのはかの金澤正剛先生。隔年で曲は入れ替わるのだが、やはり、ティンパニの勇壮な連打に導かれ、トランペットの有名な旋律が高らかに鳴り響く、マルク=アントワーヌ・シャルパンティエの《テ・デウム》が、学生の間ではもっとも人気が高かった。
筆者もヴァイオリンとしてオケの一員に加わっていた。楽譜には普通にトランペットの旋律を支える4分音符と8分音符が並んでいる。いざ弾こうとしたその時、金澤先生からヴァイオリン・セクションに向けて「あ、その8分音符ね、当時は付点を付けて弾いてたの。イネガルって言ってね。だから、そのまま弾くんじゃなくて、付点のリズムにして弾いてね」と、突然のお達し。
当時はようやく古楽・ピリオド奏法という言葉が知られてきている頃ではあったが、そこまで市民権を得ているというほどではなく、不勉強な学生だった私は、当然そんな慣習を知るよしもない。ただ、譜面をそのまま演奏するよりも、付点を付けて弾く方が、確かに活気は出て愉しかったことは確かである。その時は、「イネガル」というその奏法の名前だけが記憶にとどまったものの、どうして付点を付けて弾くのか、どうしてそれをそのまま楽譜に記さなかったのか、モヤモヤは残り続けた。
バロック音楽を演奏する上で、当時の演奏習慣を踏まえて演奏することはいまや常識となっている。それをあきらかにするのが、音楽学という学問が存在する意義のひとつではあるのだが、これは研究する側だけでなく、演奏する側にとっても大きな問題のひとつであろう。現代から時代を遡れば遡るほど、演奏者と音楽学者の距離感は縮まっていくようにも思われ、音楽学者が演奏を、演奏家が研究を手がけることも珍しくない。
アントニー・バートンが著している『バロック音楽』『古典派の音楽』(後者が新刊)の原書は、ロマン派を加えた三巻本で、いずれも共通の「歴史的背景と演奏習慣」という副題がついている。それほど分厚くない本書が、単に研究者や音楽ファンのためだけなく、演奏家に向けても、この時代の演奏がどのようなものであったのか、その全体像を知らしめるために書かれていることは、容易に想像がつく。先述のシャルパンティエについては、『バロック音楽』第2章:記譜法と解釈「リズムの変更」(58頁)に詳しい記載があり、学生時代の自分がこれを読むことができれば、当時感じたモヤモヤも、イネガルのなんたるかについても、一瞬で解消したはずなのに、と、いささか残念でもあった。鍵盤楽器、弦楽器、管楽器など、各分野において最先端を走り、それらの研究を踏まえて独創的な演奏活動を続ける実際の演奏家によって分担して書かれているのも、本書のもっともおおきなセールスポイントのひとつだろう。
ここでは、このシリーズの飜訳の労を執られた角倉一朗氏の言葉を紹介しておきたいとおもう。一連の時代(ピリオド)様式による演奏は、バロック音楽から古典派の音楽へも進出してきている。氏が両書で繰り返し強調するのは、ピリオド楽器によって耳慣れた音楽がまったく新たな姿を見せるものであること、そして同時に、演奏は一種の創造行為であり、過去の音楽の(近似的)再現が目的ではない、という点である。得てして、ピリオド演奏が過去の演奏の再現だけを目指してしまうこともあるが(こういうのをまさに「手段の目的化」と呼ぶのだろう)、現在では本来の作曲家の意図を踏まえた上で、現代人による、現代人のためのピリオド演奏というスタイルが、あらたに確立され、根付いてきているようにもみえる。そうした流れを俯瞰的にまとめてくれている著書として、この飜訳を心から喜びたい。いずれ、最終巻となるロマン派も出版予定とのことである。
橋本英二氏による『バロックとその前後の鍵盤音楽の運指法』は、特に鍵盤楽器、とりわけ運指法そのものに焦点をあてている、という意味で、類書にはあまり見られない独自性を有している。当時の理論家と演奏家が、それぞれの立場から、作品を弾きこなすためのもっとも合理的な運指法を暗中模索していく過程は、そのまま鍵盤楽器の発展の歴史として読むこともできるだろう。練習曲、というジャンルは、19世紀に市民レヴェルで音楽という『娯楽』が成立する中で爆発的に広まったものであり、バロック期のそれは、はるかに限られたひとだけが接するものではあっただろうが、それでもかなりの緻密さをもって執筆されていたという点は、筆者にとって驚きでもあり、教えられることが多かった。
シルヴィ・ブイスー(訳:小穴晶子)による『バロック音楽を読み解く252のキーワード:ア・カペッラからサルスエラまで』(現在絶版)の大きな目的のひとつは、それまで20世紀初頭のドイツ人による音楽学的時代区分が、フランスのそれにうまく適合しないもかかわらず、いまなお普遍的に用いられているという実情を踏まえ、そうした現状を少しでも打破し、より複眼的な視座を与えることにある。それ故に、ここに挙げられている用語はフランスのそれが優先されている。さらには、与えられている語義や解説も、初学者にそれが何であるかを懇切丁寧に説明するものというよりは、従来はこういう定義であったが、このような捉え方もできる、このように捉えるべきである、という表現が多用される。この本は、想定されている辞書的な使い方もさることながら、この時代についてある程度の知識を有する読者ならば、むしろ普通に通読するほうが面白いのではなかろうか。

古典派の音楽
最新の知見に基づいて、鍵盤、弦、管、声楽の各分野をそれぞれ第一線で活躍する演奏家が執筆し、その前後にすべての分野に共通する章(「歴史的背景」「記譜法と解釈」「原典資料とエディション」)が置かれている。それらはすべて学問的知識のみならず(多くは最高水準の)演奏体験をもつ音楽家によって書かれた。様式にかなった演奏を実現するための貴重な情報源であり、演奏家のみならず、近年ますます研究が進展している古典派の時代様式を知りたいすべての人の必読書である。 本書は3冊シリーズで、『バロック音楽――歴史的背景と演奏習慣』に続いて刊行される2冊目。日本語版には、訳者による懇切丁寧な註、詳細な人名索引と事項索引付き。
バロック音楽
本書の特色は、何と言っても一流の古楽専門家(クリストファー・ホグウッド、ジョージ・プラット、ピーター・ホールマン、ダヴィット・モロニー、アンドルー・マンゼ、スティーヴン・プレストン、ジョン・ポッター、クリフォード・バートレット)による豪華執筆陣。内容は、「歴史的背景」「記譜法と解釈」「原典資料とエディション」といった重要な知識や情報と、鍵盤・弦・管楽器・歌唱の奏法がバランスよく収められている。当時の楽譜のファクシミリや絵画も掲載され、想像を助けてくれる。バロック音楽の演奏習慣や原典資料については、研究が著しく進んできたが、特にアマチュア音楽愛好家が、ピリオド楽器や奏法、楽譜エディションなどの知識を得るのに手ごろな書籍が少ないなか、本書は、アマチュア・プロの演奏家、リスナー、そしてバロック音楽の背景に興味があるすべての方に、啓発的な知識とインスピレーションを受け取ってもらえる1冊となっている。
バロックとその前後の鍵盤音楽の運指法
ピリオド楽器、モダン楽器の別を問わず、バロック音楽を演奏する鍵盤楽器奏者のために、運指法の概要から個々の事例まで網羅した必携の一冊。第1部では、ドイツ、スペイン、イギリス、イタリア、フランス各国の教本・理論書の記述を、時代別に紹介。J.S.バッハ、F.クープラン、ラモー、D.スカルラッティ、C.P.E.バッハ、マールプルク、テュルクなどが実践した指使いを検証する。第2部では、各指の使用法や手の位置、アーティキュレーションと指使い、並進行、装飾音など演奏実践に即した項目別に解説。膨大な資料から要点をまとめ、実際の楽曲を含む譜例を多数掲載して、現代の奏者が演奏に生かせるよう目配りが行き届いている。R.カークパトリックの直弟子であり、シンシナティ大学名誉教授の橋本英二による、既刊『バロックから初期古典派までの音楽の奏法』に続く書き下ろし。著者の専門領域である運指法についての待望の解説書。