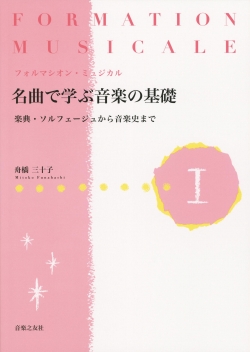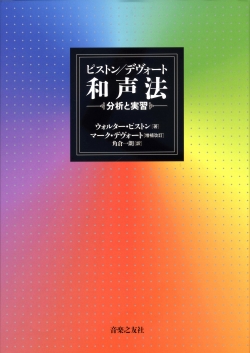第25回 音楽上の規則の意味を、実際の音楽に求める
初等教育を過ぎ、中等教育を過ぎ、高等教育へさしかかった頃に、ひとは往々にして初等教育で学ぶべき内容に再び取り組まねばならないときが訪れる。だが、いったん大人になってしまうと、ひとは小学生や中学生のように、世の中の仕組みを、そのエッセンスだけを抽出したようなかたちでは覚えられない。あるいは、覚えようともしない、というほうが正確だろうか。小さいときは、英語の不規則変化動詞や数学の複雑な公式を、その意味も問わずにまるごと覚えていたにもかかわらず、すくなくとも大学生以上になってしまうと、その種の努力をなぜかまったく放擲してしまうのである。
もちろん、若い脳みそのほうが何事においても吸収が速く、あらゆる事象を呑み込んでしまえるものであり、歳を取ればとるほど、丸暗記は苦手になる。とはいえ、丸暗記が苦手になっていくのは、別の理由があるようにも思われる。歳を取り、自分と身の回りの世界だけでなく、大きな社会全体が見えてくるようになると、なぜある特定の動詞は不規則な変化をし、どのようにしてその公式へとたどり着いたのか、ひとはそのわけを知りたくなる。いや、そのわけを知ることなしに、公式だけを覚えられるような脳みその構造からは徐々に離れていくのかもしれない。
筆者が大学、しかも音楽大学ではない、教養として音楽を学ぶ一般大学という場で、楽譜の読み方の基礎である楽典、そして和声学や対位法の基礎を教えるにあたり、真っ先にぶつかったのはこの問題だった。なぜドレミファソラシドとハニホヘトイロハは併存しているのか、どうして調性には二種類(長調・短調)が存在するのか、次々と押し寄せる学生からの疑問の声に、教師として可能な限りの最適解を与え続けなくてはいけない。最適解を与えるためには、まず自分自身が、あまり深く考えもせずに覚え続けてきた音楽のルールそのものについて、そのルールを決めることになったおおもとへと遡る旅をはじめなくてはならなかった。
幸い、そのための指標、そしてお手本は、すでに知っていた。以前本欄でもご紹介した、ウォルター・ピストンの『和声法』を自分の大学生時代に教科書として使っていたことが幸いした。無味乾燥になりがちな和声の課題であっても、減七和音、ナポリの六度といった用語が何を意味し、どのような響きであるかを知ること自体はさほど難しくない。しかし、それが実際の作品の中でどのように使われ、なぜそのような規則が生まれたのかを知らなくては、紙の上で血の通わない知識を積み重ねるだけである。楽典においても、なぜそのような音楽上の規則ができたのか、その理由を実際の音楽に求めることで、知識としてだけでなく、聴覚上の経験として定着させねば、何の意味もない。規則を規則として活かすためには、それを生み出すもととなった世界の奥の深さを、可能な限りみずからの力で知ろうとせねばならないだろう。
もちろん、自分一人の力でそれを成すには限界がある。そして、筆者と同じ問題意識を共有してくださっている著者の方々が、それぞれのやり方に従って、理論と実際の世界を結びつけるべく、様々な試みをおこなっておられる。西尾洋氏による『応用楽典 楽譜の向こう側』は、まさにそうした演奏者の視点から、なぜ楽典におけるさまざまな約束事が生まれたのかを解き明かそうとする。各章にはかならず「~に意味がある」という語尾が付され、「音階」や「音程」、「調」における「意味」を実例とともに解き明かそうとする。調が変わる、転調するということの意味は、「音楽の表現する何か(場面、情景、心情など)が変わるということ」である、と、簡潔かつ明瞭に定義される(40ページ)。シューベルトの《冬の旅》から〈郵便馬車〉を例として、変ホ長調から変ホ短調(同主調)へと転調することによって、失恋の哀しみが描かれる、と、楽譜を用いてその実際が示される。「音型」においては、ラメントバス、狩りの音型、パストラーレといった音型やリズムが、ある特定の意味を伝えるために慣用的に用いられる、という、意外と一般的な本ではお目にかかることのできない、しかし重要な情報もさりげなく解説される。実際の楽譜の中に隠された作曲家の意図を汲み取るためのきっかけが、次から次へと示される本書を用いて、音楽からさまざまな意図を聴き取ることができるようになれば、漫然と聴いている音楽にも、汲めども尽きせぬ意味が隠されていることが実感されよう。
西尾氏やピストンと同じスタンスで、無味乾燥な和声法を、実際の譜例によってより立体的に学習するための教材として、柳田孝義氏の『名曲で学ぶ和声法』をも挙げることができる。ピストンの本と異なるところは、より日本における和声法の実際に鑑み、それに即した練習問題が充実している点であろう。譜例の多くをベートーヴェンやショパンのピアノ曲に拠っているのは、オーケストラのリダクションではなく、オリジナル楽曲を載せることに意味を見出し、重視しているためだろうか。舟橋三十子氏の『名曲で学ぶ音楽の基礎 I、II』は、この和声法よりもさらに目的がはっきりしており、音楽大学・高校、音楽教員採用試験の勉強として、あるいは教科書として、とはっきり銘打たれている。音楽における「楽譜を読む、書く、演奏する」という基礎的な能力の向上を目指すことが第一義ではあるのだろうが、掲げられた有名作品に直接触れ、その魅力に気付くことができるよう、さりげなく導かれてもいる。
近年は、音楽についての文章を書く際に、楽譜を使わずに言葉だけで易しく解説してほしい、という依頼を受けることがしばしばある。もちろん、楽譜を読める読者ばかりではない、ということはわかるのだが、楽譜を示せばひとめで済むものが、それがないために延々と言葉を連ね、却ってわかりづらくしてしまうことも一再ではない。音が上がる、音が下がる、ということさえオタマジャクシから感じられるのであれば、その楽譜を眺めるだけでも伝わることはある、と筆者は信じている。言葉を尽くして説明し、その上で最後は楽譜に語らせるのが理想なのだろう。音楽というものが秘めている可能性について、作曲家みずからの「言葉」である楽譜そのものから感じ取ってほしい。拙著『楽譜でわかる クラシック音楽の歴史』は、そんな思いで記した。

応用楽典 楽譜の向こう側
楽譜を「分析」してそれをどう「解釈」するのか、楽典を切り口に、楽譜に書かれていること、書かれなかったことを読み解き、独創的な演奏につなげる方法を考える読譜の入門書。
日本では、楽典、ソルフェージュ、演奏実技がそれぞれ独立して教えられ、楽譜も読めてソルフェージュ能力もあるのに、それらを統合した演奏表現に活かせていないことが多い。「あなたは、なぜそう弾くのか?」「なぜ作曲者はそう書いたのか?」「そして、あなたはそれをどう理解したのか?」――楽譜に書かれたものだけでなく、その背後にある「意味」を、自ら探り、学びとることで、表現は説得力をもち絶対的になり、それが独創的な表現につながっていく。本書は、そのためのさまざまな可能性の探り方を、具体的な譜例を多数挙げながら提示する。
ピティナ(一般社団法人全日本ピアノ指導者協会)やヤマハマスタークラスのアナリーゼ関連の講座で人気を誇る著者は、これが初の著書となる。
楽譜でわかる クラシック音楽の歴史
古典派(18世紀後半)から20世紀にいたるヨーロッパ音楽の歴史について学ぶ際、その拠り所となる音楽史の教科書はすでに数多く存在する。本書では、主に一般大学の学部生レヴェルの初学者を対象とし、数ある作品の中から、ある程度の分量を有する譜例を掲載し、作曲家が得意とした音楽様式上の特徴を実際の作品から具体的に学ぶことをその最大の特徴とする。
譜例を数多く掲載した音楽史の本は類例がなく、大学の一般教養科目のテキスト(半期)として最適。
ひとつの楽曲につき、本文記述は半頁~1頁、楽譜は1~6頁。古典派(C. P. E. バッハ)から20世紀前半(新ウィーン楽派)までの楽譜(抜粋含む)を掲載し、音楽様式上の特徴を楽譜への書き込みによって示す。時代背景、作曲家の個性を捉えた本文は読み物としても充実。
※譜例掲載曲の音源を聴取できる特設サイトを、ナクソス・ジャパン株式会社のご協力のもと、開設しました。47曲を試聴することができます。ぜひご活用ください。
名曲で学ぶ音楽の基礎 I
フランスで行われている、名曲やよく知られた曲をテキストにして、音楽を多角的な面から考え、真の音楽家が身につけるべき広い教養と高い音楽性や創造性を目指す学習方法――この考え方は“フォルマシオン・ミュジカル” (Formation Musicale)と呼ばれている。本書は、フォルマシオン・ミュジカルを今の日本の現状に合わせて、幅広い視点から音楽を捉えるという考え方に基づいて構成された問題集。全2巻。Iは初級。
「ソルフェージュ」「楽典」「楽式」「和声」「音楽史」など、音楽に必要な基本が身に付く。さらに発展した知識と教養を身に付けるために、各曲(章)の終わりに「コラム」を設けた。オーケストラ、ピアノ曲を中心に、声楽・合唱、室内楽、協奏曲も収載。
近年、多くの音高・音大入試で出題される、実曲を使った問題への試験対策をはじめ、教員採用試験対策、音高・音大の授業教材、普段の楽器のレッスンの副教材として最適。
名曲で学ぶ音楽の基礎 II
フランスで行われている、名曲やよく知られた曲をテキストにして、音楽を多角的な面から考え、真の音楽家が身につけるべき広い教養と高い音楽性や創造性を目指す学習方法――この考え方は“フォルマシオン・ミュジカル” (Formation Musicale)と呼ばれている。本書は、フォルマシオン・ミュジカルを今の日本の現状に合わせて、幅広い視点から音楽を捉えるという考え方に基づいて構成された問題集。全2巻。IIは上級。
「ソルフェージュ」「楽典」「楽式」「和声」「音楽史」など、音楽に必要な基本が身に付く。さらに発展した知識と教養を身に付けるために、各曲(章)の終わりに「コラム」を設けた。オーケストラ、ピアノ曲を中心に、声楽・合唱、室内楽、協奏曲も収載。
近年、多くの音高・音大入試で出題される、実曲を使った問題への試験対策をはじめ、教員採用試験対策、音高・音大の授業教材、普段の楽器のレッスンの副教材として最適。
名曲で学ぶ和声法
名曲の譜例をもとに和声法を学ぶことのできる画期的な一冊。本書は、音楽大学や教員養成課程で和声法を学ぶ学生の多くが、実際の音楽で和声がどのような役割を果たしているのか、なぜ和声法を学ぶ必要があるのかを十分に理解することなく、規則や禁則を覚えて課題を実施することのみに終始しているのではないか、という視点から生まれた。掲載されている譜例は、どれも一度は耳にしたことがあるだろう名曲ばかり。
学習者が耳で直接和声の変化を感じることができるよう、演奏形態にかかわらずすべての譜例がピアノで演奏できるようになっている。全体は第1部基礎編と第2部実習編からなり、第2部の各章には練習例題とその参考実施例、さらに実習課題が用意されている。巻末には実習課題の実施例集も掲載されているので、学習のための手助けにして欲しい。『名曲で学ぶ対位法 書法から作編曲まで』の姉妹書。
和声法
1941年の初版以来、48年、62年、78年、そして最新の1987年の第5版まで改訂増補されつつ版を重ね、アメリカの音楽大学や総合大学の音楽学部でもっとも広く使用されている和声法教本の全訳。最大の特徴は、和声法の理論と実習と分析が一体化していることで、一定の規則を示すだけでなく、つねに実作品の譜例を参照しつつ、規則や定型を現実の音楽から抽出しているため、大学などのテキストとしてはもちろん、独習にも最適の内容である。また和声にかぎらず、リズム・旋律・構造についても論じており、18世紀~20世紀初頭(バッハからヴェーベルンまで)の西洋音楽のしくみを総合的に理解することができる(つまり、理論だけでなく、音楽史を学ぶことができる)。記述はきわめて簡潔明快で、各章末の実習課題も、通例のバス課題と旋律課題にとどまらず、さまざまな工夫がこらされている。