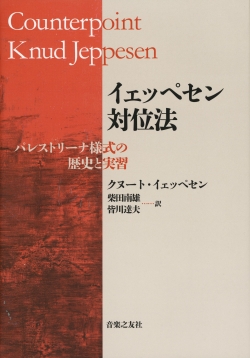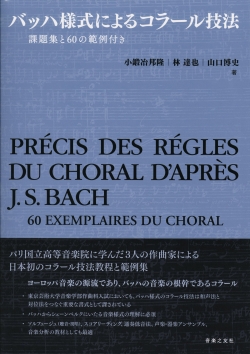第23回 西洋音楽を決定づけたイェッペセンとバッハ
対位法の本が目白押しである。次から次へと対位法に関する本が世に問われ、こんなに出てきてしまって大丈夫なのだろうか、と心配になってしまう。筆者もすでに、対位法について書くべきことは、あらかた第20回に書いてしまい、いまさら付け加えることも、という感じではあるので、早速本題に入ってしまいたい。
クヌート・イェッペセンによる著書『イェッペセン対位法――パレストリーナ様式の歴史と実習』は、なんと1955年(昭和30年)に日本語の初版が登場している。それから数えれば、実に58年ぶりの復刊であるとか。柴田南雄、皆川達夫という両巨頭による飜訳がいまなお示唆に富むものであるからこそ、この復刊にはおおきな意義がある。
その意義については、すでに皆川先生がご自身で、巻末の「訳者あとがき」の中にすべて説き起こされているので、ここではその内容を要約するに留めておこう。すなわち、
1) 対位法の学習には、純粋に線と線の関係を追求するパレストリーナ様式によるものと、機能和声の考えの基に線を動かすバッハ様式によるものと2つの方法があるが、本書は前者の解説書である。
2) パレストリーナ様式による対位法の教科書は、フックスのそれが基本となっているが、今日から見ると欠陥も多い。イェッペセンはこの領域の第一人者であり、本書の内容も、従来の類書と比べれば格段の開きがある。
3) 本書第1部にはパレストリーナ様式成立までの歴史的概観と理論の発達史が述べられるが、それはこれまで重要でありながら見過ごされてきた。また、音楽についての幾多の本質的な問題についても、美学的に論じられている。
4) 第2部にはパレストリーナの実作例が豊富に引用されており、これ自体が得がたい資料である。
5) 訳書では、ハ音記号で記される各声部記号を、すべて高音部(ト音)記号と低音部(ヘ音)記号に統一した。読譜を容易にするばかりでなく、この種の対位法を近づきがたいものとしていた主要な原因を払拭することに役立てば幸いである。
……といった具合である。もっとも、第1部の記述は相当に中世・ルネサンスからバロックに至る音楽史の知識を前提とするものではあるので、たとえば対位法形成にあたって15世紀・ナポリのティンクトーリスがいかに独創的な考え方を編み出したか、などの諸点に関しては、むしろ対位法そのものの実習をこころざすひとよりは、この時代の音楽をより深く知りたいと思う研究者や音楽ファンに喜ばれるべき性質の読み物であろう。
歴史的な対位法の変遷を鑑みれば、横の線(旋律)よりも縦の線(和声)を重視するかたちで生まれたバッハの対位法は、またまったく別の次元で語られるべき性質を有している、というべきだろう。小鍛冶邦隆・林達也・山口博史の共著による『バッハ様式によるコラール技法――課題集と60の範例付き』では、その考え方が余すところなく示されている。やはり第1部で、小鍛冶先生がバッハの対位法についての考え方、そしてそこから生み出されたコラール書法について紹介して下さっているので、ここでもそのエッセンスをごく短くまとめておきたい。
1) ヨハン・ゼバスティアン・バッハは、その作曲の指導法において、パレストリーナ様式に基づく、伝統的ではあるが無味乾燥な対位法を省略し、4声体の通奏低音から始めた。そこから4声コラールへと進み、旋律に対してバス旋律を教師(バッハ)が与え、学生にアルト・テノール声部を補わせ、生徒自身がすべてを仕上げられるようにしむける。フーガについては別途2声体のものから学習する。
2) コラールはプロテスタント教会で歌われる讃美歌であり、その旋律をもとに作曲を行なうコラール編曲の技法が重要となる。こうした旋律がバッハの教会音楽、受難曲、カンタータの中核的素材となる。
3) 通奏低音法は、演奏実践の技法であることはもちろんながら、すべてを記譜せず、作曲プロセスをある程度開かれた状態で形成する歴史的作曲技法でもある。演奏技法としての通奏低音法と、作曲技法としての和声法はかならずしも一致しないが、通奏低音法を通じて和声法を習得する、という側面は事実であろう。ルネサンス期までの、対位法を通じた作曲技法の習得は、バッハにおいては和声法としての通奏低音法から対位法に至る、という、近代的な学習過程へと変化していった。
第2部ではこれらの諸点を踏まえ、和声法における禁則などの確認を経つつ、バッハの実作例で、コラール書法の基礎を学ぶことになる。そして学習者は第3部において、実際に与えられた(林・山口両氏自作の)コラール旋律から、4声体によるコラールを実作する、という、高度に専門的な用途にも対応できる作りとなっている。『イェッペセン 対位法』では退けられたハ音記号による記譜法も、ここでは敢えて踏襲されており、本書の専門性が窺える。
本来は横の旋律を意識することで生まれた西洋音楽が、バロック期において、バッハというたゆまざる努力を紡ぎ続けた「天才」の力によって、縦の和声をより意識して作られるものへと質的な変化を遂げた。この2冊を丹念に繙けば、連綿とつづいてきた西洋音楽の世界においても、その音楽観に決定的な違いが生まれた瞬間がいくつもあった、ということが実感できることだろう。ピアノを嗜む方であれば、ぜひこの2冊に含まれる譜例を、ご自身で音を拾いながら弾いてみることをお薦めしたい。あるいは単純に各声部の旋律を歌うのもよい。文章だけでは実感できない音楽の仕組みを、実感を伴うものとして、より深い理解へと誘ってくれるはずである。

イェッペセン 対位法 パレストリーナ様式の歴史と実習
和声を内包した線的な音楽であるバッハの様式に対し、純粋に線と線の関係を追求するパレストリーナの様式について書かれた名著中の名著、ついに復刊!
原書は、1931年の初版以来、高い評価を得ている。その日本語訳である本書は、東京創元社より1955年に刊行されたのち絶版となり、長らく復刊が待たれていたもの。
全体は、対位法理論の歴史的概観、パレストリーナの技法上の諸特長、実習の順で構成され、カノン、モテット、フーガにもふれている。明晰な説明、豊富な譜例に加え、理論と実践の問題が絶妙のバランスで扱われている点で、実習書としてばかりでなく、音楽学の演習書としても利用可能。本書を通じて、16世紀の声楽ポリフォニー様式の「実態」をぜひ学んでほしい。