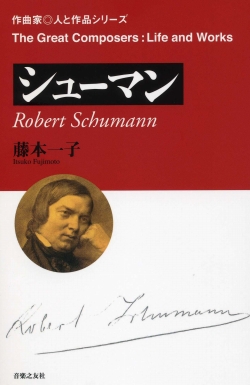第22回 シューマンの音楽にひそむ「なにものか」を言葉にする3作
ロベルト・シューマンの音楽が、ずっと苦手だった。
構造的に確固たる形式を有し、揺るがぬ、力強い音楽ですべての聴き手を圧倒するようなベートーヴェンのピアノ作品を、さんざん聴かされ、弾かされて育ったせいかもしれない。あるいは、とてつもなく長く、同じような繰り返しばかりに感じられつつも、どこかその中に陶酔感を感じさせるようなシューベルトの作品にも心惹かれていたせいかもしれない。
でも、それはきっと、言い訳なのだろう。もっと率直に言えば、若い頃は、シューマンの音楽は何をどう聴けばいいのかがわからず、そのきっかけすら掴めなかった。2つの主題が戦い続けて、最終的に圧倒的な大団円へと至るような筋書きを、無理矢理シューマンの音楽のなかに見つけようとしては、それに失敗してばかりきたような気がする。ベートーヴェンのような聴き方でシューマンにアプローチしようとしても、それは無理な話。若い頃はそんなことにすら、まるで気がつかなかった。
シューマンの伝記や解説にもあるとおり、尋常ならざる情熱と、それを制御しようとする理性の狭間で悩み苦しむ作曲家の姿こそが、19世紀前半の「ロマン派」を牽引し、代表する存在であったことも、頭ではわかっている。が、シューマンが覗き込んだ精神の闇を、音楽そのものから感じ取ることはなかなかできないでいた。シューマンが形式の枠を大胆に乗り越え、破調をもってしてまで描こうとするその世界が、自分にはひたすら遠いものとしてしか感じられない。明晰な精神を保ち、すべてを完璧なコントロール下に置きながら作曲するような、たとえばハイドンやドヴォルザークのような音楽とはまるで異質に思え、世に「シューマニアーナ」と呼ばれるひとたちは、自分には覗き得ないその「闇」が見えるのだろう、と思っていた。
シューマンの「闇」が、ほんのすこし見えたような気がしたのは、つい数年前のこと。《交響曲第2番》で、ほぼ全曲に渡って用いられる「C-C-C-G」のモティーフ。第1楽章冒頭のファンファーレとして登場するのみならず、第2楽章で音楽がカタストロフへと向かって疾走していく時にも、唐突に登場する。これを際立たせて演奏する解釈に出会ったとき、諸々がなんとなく腑に落ちた気がしたのである。何かにせき立てられるように、せわしなく動き回る音楽は、シューマンが抱えていた心の「闇」の世界への入口であったのか、と。かのモティーフも、その世界に踏み入れてしまったことを示すファンファーレなのか、と。様々な形式の形をとりつつも、その形式を軽やかに乗り越え、さまざまな要素を混在させていくシューマンの音楽。その音楽をたぐり寄せるためのひもを一本だけ、掴まえたような気持ちになった。歌曲においても、《詩人の恋》第1曲での移ろう和声、終曲で長い、長い後奏を付けたくなるその気持ちに寄り添うことで、少しずつその音楽世界に親しめるようになっていったとは思う。
だが、いまだに、筆者にとってもっとも難しいのは、比較的その初期にまとめて作曲されたピアノ曲。とりわけ、既存の形式の枠では解釈することが難しい作品群については、いまだにそのハードルは高い。というわけで、今回はその中でも、自らの苦手意識が強い《フモレスケ》作品20変ロ長調について、トモシャの誇るシューマン書籍群から教えてもらおうと思う。
まずは、西原稔氏が執筆されたばかりの大著、『シューマン 全ピアノ作品の研究』の下巻より、当該箇所を読み耽る。1838年4月にライプツィヒ、1839年3月以前にウィーンで成立。クララとの結婚に反対し続ける父ヴィークをついに提訴したのが同年7月であり、その翌月には友人に「《フモレスケ》はあまり楽しい曲ではない。おそらく私の作品の中ではもっともメランコリックなもの」と言及している。そもそもこのタイトルはなにを意味しているのか。これも友人に宛てた手紙の中で、フランス人にはこの用語が理解しがたいものであり、「夢想的な熱狂とフモール」という、ドイツの国民性に根ざした2つの特性を適切に訳す言葉を持っていないのは不幸なことだ、と。なるほど。「その全体の構成の捉え方がもっとも難しい作品のひとつであり、全体を明確な部分に区分することすらあまり意味を持たない」が、それでも全体は6つ(ないしは5つ)の部分に分けることが可能であろう。
つぎは、藤本一子氏の〔作曲家◎人と作品〕『シューマン』より。クララへの手紙に依れば、「フモールについての概念は情緒とウィットが幸せに溶融したもの」。崇高なものに低俗なものを対置させることで得られる高次の超脱性に微笑む世界観だ、と。ふむふむ。作品全体を貫くのは、第二部に現れる「D-C-B-A-G」と下降する旋律で、これは《ノヴェレッテン》にも《ウィーンの謝肉祭の騒ぎ》でも使われる。複数の作品に同じ旋律を用いることで、周辺の作品群を総合的なイメージのもとに連携させる方法も注目に値する、と。
最後は、〔オルフェ・ライブラリー〕の『シューベルトとシューマン――青春の軌跡』より。井上和雄氏の筆致は軽妙でありながら、対象への深い愛情があちこちに顔を出す。英語の「ユーモア」という言葉よりもさらに幅広い表現であり、機知、耽溺、情緒など、喜びも悲しみも含んだ感情の絡み合った気分であり、内面生活における気分の変動と葛藤を表現したのだ、と表現するブリオンの著作を引用しつつも、完全にその内容に同意はしない。シューマンの鍵盤を駆け抜けるものが、そのような気分の「悲愴な分裂を表現している」とするブリオンの言説に違和感を抱く氏は、この曲がシューマンの分裂性そのものを示唆しているものではなく、シューマンはこの変容を楽しんでいるのであり、たとえ分裂し、多様であろうと、それを音楽で表現するときははるかにクリティカルな目を働かせる、と説く。分裂したまま並べるのではなく、それを美的原理に従って統合しているのだ、と。
井上氏の説くところはとてもよくわかる。およそ現代にまで生き残っている音楽のすべては、その内側に自立的な様式美を保っているものであるから。ベルリオーズの《幻想交響曲》を引くまでもなく、作曲家はみずからのうちに、荒れ狂う激情に苦しむ自分と、それを外から冷ややかに見つめる自分を飼い慣らしているものだから。シューマン自身もそのような自らの二面性を、フロレスタンとオイゼビウス、というかたちで擬人化し、言葉に託し、そしてそれを音楽の世界でも描こうとした。
だが、それでも、シューマンの音楽には、そのようなクリティカルな視点、冷ややかに見つめる視点をかいくぐり、指の間からこぼれ落ちるなにものかがある。以前に比べれば、筆者もシューマンが音楽の形を借りて表現しようとするものを、かなり「理解」できるようにはなってきた。だが、それを全身全霊の「共感」をもって聴く段階には、おそらく、まだ至っていない。今回紹介した本は、三者三様に、筆者の指からこぼれ落ちたなにものかを、言葉として明瞭に説明してくれている、という意味でも、シューマンを「理解」するための手がかりを与えてくれた。その「こぼれ落ちるなにものか」を丹念に拾い、咀嚼するだけではなく、身体に染み入らせ、作曲家の「気分の変動と葛藤」をわがものとして実感できたとき、筆者も晴れて「シューマニアーナ」を名乗れるようになるのだろうか。

シューマン 全ピアノ作品の研究 上
『レッスンの友』での5年間にわたる連載の単行本化。充実した内容のため、全2巻とした。上巻は、第1部「シューマンとその時代」と、第2部のピアノ作品の解説(ピアノ・ソナタ第1番〈作品11〉までを収録)。シューマンの関連書は多いが、ピアノ作品の解説は少なく、全作品を解説する待望の一冊。シューマンは、ドイツ・ロマン派の文学、とりわけジャン・パウルやホフマン、アイヒェンドルフといった作家の小説に深く傾倒し、絶えず夢幻が広がっていく彼らの文学世界を音楽においても表現しようとした。シューマンの作品の難しさは、音符だけで作品を十分に解釈できない要素に起因している。たとえば文学的な要素だけではなく、さまざまな引用や彼の創造の中で飛来した種々の楽想が作品の中に取り込まれている。作品相互の関連や、クララや周囲の人物達とのエピソードなども興味深い。
〔作曲家◎人と作品〕シューマン
好評をもって迎えられている評伝シリーズの最新刊である。ドイツ・ロマン派を代表するこの大作曲家はまた同時に、当時を代表する論客としても名をはせていたことでも有名である。そうした文筆の素養に大きく関わるその生い立ちから、ピアニストを目指していた青年時代、生涯をともにした愛妻クラーラとの出会い、結婚までの困難な道のり、ブラームスを見出し、ドイツ音楽の将来に大きな期待を抱きながらも、しだいに精神を病み、ついにはライン川へ身を投ずるまでの50年に満たない生涯を、そのそれぞれの時期に生み出された傑作の数々を振り返りながら、克明に追っていく。先述の通り、文筆活動においても当時の音楽批評の潮流を左右する重要人物であったことに鑑み、作品篇の末尾には特にその著作についての記述を加えた。