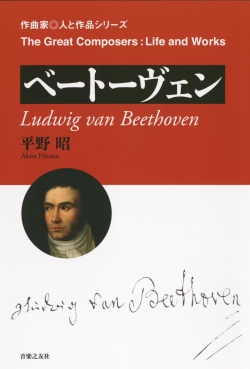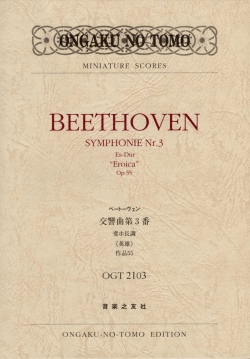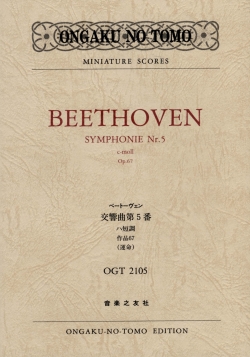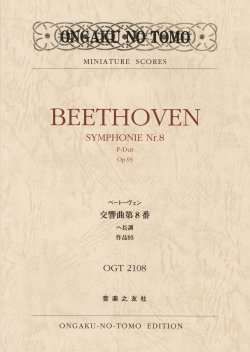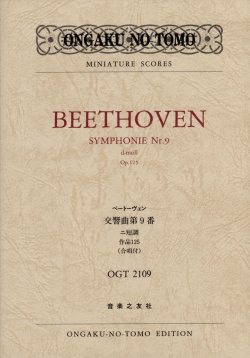第19回 時代を押し開いたベートーヴェンの伝記・作品分析
確かベートーヴェンについては、すでにかなりガッツリ書いたはずでは…、と、過去のアーカイブを遡ると、やっぱり第9回に書いている! この時はひたすらアナリーゼに特化していたので、書き終わった後はグッタリ疲れた。難しいことを難しいまま書くのは実はそれほど難しくはなく、難しい話を多くの人に咀嚼してもらえる形に加工する作業こそが、本当に難しいのだとはよく云われるところ。まあ、この「専門書にチャレンジ!」という連載が、そうした「難しい話をわかりやすく」という課題につねに挑戦し続けるようなものではあるのだが、さすがにあの時ばかりは途方に暮れ、難渋した。
今回のお題を頂いたときも、またベートーヴェンか、あのときの悪夢再来か、とかなり身構えたのだが、幸いにしてその予測は(一部だけではあるが)外れたようである。それはひとえに、ひさびさに登場した『作曲家・人と作品』シリーズの最新刊、平野昭氏による『ベートーヴェン』を真っ先に読んだお蔭であろう。
氏によるベートーヴェンの伝記には、すでに若かりし頃からお世話になっていた。新潮文庫から出ている『カラー版作曲家の生涯』をすべて揃えていたので、まずはその本でベートーヴェンという作曲家の生涯のあらましを知った。あるいは、講談社から発行された「ベートーヴェン全集」なども、その詳細な活動を知るにあたって実に数多くの示唆を与えてくれた(どちらもご自身が「あとがき」で触れていらっしゃるが)。
偉大なる作曲家の生涯を描く氏の筆致は実に明快であり、説かんとする主題に向かって一直線に突き進んでいくかのような潔さすら感じられる。もはや類書によって語り尽くされた感のある「不滅の恋人」論争、さらには甥カールを巡る親権裁判と伯父が甥に与えた精神的苦痛といった微妙な主題にも、氏はこれまでの研究の成果を惜しみなく用いた上で、論文などでは飛躍することの難しい、納得のいく推論を積み重ねていく。当然のことながら、ここ数年間に登場した学説についても氏が目配りを怠ることはなく、留保をつけた上でそのような説があることをさりげなく紹介したりもしてくれる(例:1787年、若き日のベートーヴェンが初めてボンからウィーンに向かう際、実はレーゲンスブルクに立ち寄っていたのではないか、とする説)。
この『作曲家・人と作品』シリーズのもっとも大きな特徴は、「生涯篇」と「作品篇」がそれぞれ独立しており、それぞれに独自の見解が展開されていくところだろう。あたりまえのことながら、作曲家ごとに異なる著者が手がけているわけで、それぞれのアプローチや筆致の違いが際立つのも興味深い。ここでは、平野氏の淡々とした、だが力強い筆致は、後半の「作品編」に至って、さらなる切れ味をもって対象へと迫る。先達の成し遂げた成果を無批判に踏襲することをいさぎよしとせず、常に新しい創意工夫を盛り込もうとするベートーヴェンの姿は、大規模な交響曲やオペラから、小規模な器楽のソナタに至るまで、いずこにも共通するものであり、氏はその精神こそがベートーヴェンをここまでの偉大な存在たらしめている源泉と考えているのだろう。すでに知られたことはより確かに、いまだ知られていないことはよりはっきりと。ベートーヴェンというひとりの作曲家が、いまにもこの本から飛び出して眼前で語りかけてきそうな、そんな実在感を持って迫ってくる伝記は、そうそうお目にかかれるものではない。
今回紹介する中でもっとも骨のあるのは、第9回でも登場したハインリヒ・シェンカーによる《ピアノ・ソナタ第30番》作品109の分析であろう。その分析方法は、この種の音楽分析に慣れていない読者の皆様にとってはほとんど拷問のごとき難しさであろうと思われるので(!)、その基本的なお作法については、懇切丁寧に、ユーモアも交えつつわかりやすく説かれている沼野雄司先生の連載をご一読頂ければ幸いである。
音楽を「分析」するという営為を、同業者からの反論を覚悟の上で簡単に言い切るとすれば、その楽曲を構成する諸要素をこれ以上分解できないような単位にまでバラバラにして、それがどのような規則性をもって組み立てられているか、をミクロの視点(旋律・モティーフ・リズムなど)と、マクロの視点(楽曲の形式、管弦楽法など)からあきらかにし、作曲者がどのような意図・思想に従って曲を組み立てたかを、白日の下にあきらかにしようとすること、になるだろう(ちっとも簡単に言い切っていないけれど)。
シェンカーの理論が異質なのは、これも反論を覚悟の上で言い切るならば、音楽作品というものは、そんな作曲家の意図・思想といったものを超えた、作者自身すらもはっきりとは意識せずに従っている単純な構造へと還元できるものであり、楽曲とはそれを広げていったものである、という考え方から論を繰り広げている点であろう。ドイツ語で「ウアリーニエ Urlinie」、根源的構造という訳語が当てられたこの概念こそ、シェンカーが生み出したまったく独自の分析手法の根幹を成す考え方である。
…とはいうものの、それをわかったところで、その内容は決してやさしくはない。さらに筆者にとっては、この本を通読するのはなかなかの苦行でもある。なにしろ、シェンカーは先行するこの作品の分析を十把一絡げにやっつけ、口を極めて罵るのである。もちろんこの批難が、翻ってシェンカーその人の考え方をわかりやすく知らしめるためのよき手がかりとなってくれるのではあるが、人の悪口を読むのは、正直に言って少々しんどい(と書くことも悪口になってしまうかもしれないが)。オレだけが正しい、と主張する声の大きさは、もちろん当時のウィーンの文化が依って立つレトリックに依拠したものではあり、歴史的なドキュメントとして読むべきものなのだろう。このレトリックの凄まじさは、道なき道を切り開こうとする、武装して戦うシェンカーというひとの苦闘の跡をそのまま物語っているようにも見えてきてしまう。
筆者にとっては、日本人に向けて書かれた同時代人の分析が、心情的にもピッタリと寄り添ってくれる。土田英三郎、沼口隆両氏がベートーヴェンのミニチュア・スコア巻頭に寄せた分析は、楽曲の成立の背景を事細かに解説してくれるだけでなく、決して単純明快とは言えない各楽章の形式を図示してくれるという意味でも貴重であろう。とりわけ、《第3番「英雄」》の図を見れば(同書ix頁)、ソナタ形式の提示部・再現部に比して、展開部がおよそ1.5倍の長さを有していること、さらにはコーダ(終結部)がほとんど再現部と同じほどの規模を有していることが、一目で見て取れるようになっている。いかにこの作品が型破りなものであったかが、一目でわかるだろう。あるいは、《第8番》第1楽章の冒頭と結尾がまったく同じモティーフで挟まれているところに、作曲家の「フモール」を見て取る(同書xi頁)あたりも、つい聞き逃しがちな点であるだけに、ベートーヴェンの聴き方を教えてもらった、蒙を啓かれた思いである。
曲そのものの構造を詳しく知るという意味でも、最新の研究の成果が盛り込まれたこの種の楽曲解説を読むことができるという意義は大きい。演奏会の曲目解説、あるいは作曲家の伝記ですら、与えられた文字数の関係上、ここまで踏み込んだ解説を読むことはできないのだから、そのためだけにこのスコアを繙く価値は大いにあろう。
この連載で山ほどの関連本を読んだお蔭で、筆者もいっぱしのベートーヴェン通になることができたような気がする。ベートーヴェンの偉大さは、もちろん第一義的には優れた曲の数々を遺してくれたことにある。だがそれだけで語れるような底の浅いものでは決してない。自らの名前を冠した曲を後世に遺すという一個の「芸術家」としての自意識は、モーツァルト以前の「職人」作曲家がついに持ち得ぬものでもあった。ベートーヴェンの真の偉大さは、「個」としての芸術家たるひとりの作曲家が、自らを主張し始め、19世紀・ロマン派の幕を開けた、という観点から眺めると、また新たな風景が見えてくるように思われる。晩年作品がロマン派の萌芽とはよく云われるところだが、中期の作品からも、次の時代を押し開こうとするさまざまな工夫を、もっともっと発見できるように思うのだ。
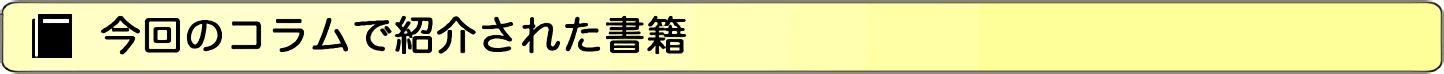
作曲家◎人と作品 ベートーヴェン
本シリーズは、第1期としてショパン、シューベルト、モーツァルトなど12巻が2005年までに刊行され、本書はその後スタートした第2期の6巻目である。長く日本のベートーヴェン研究の第一人者であり続けてきた著者は今回、生涯篇ではベートーヴェンと交流のあった多くの人々との関連に新たな光をあて、新しい「書簡全集」や「筆談帳」から得られるベートーヴェンの人間像に独自性を打ち出している。作品編でも、長年の研究成果が結実された著者独自の視点、解釈が読みどころとなっている。
ベートーヴェンが生きたのは、社会的にさまざまなターニングポイントとなった時代。加えて、難聴や叶うことのなかった恋の数々……。苦難と共に生きた(と思われる)ベートーヴェンにとって、音楽はどのようなものだったのか。従来の伝記からは伺い知れないものも少なくない。
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第30番op.109 批判校訂版
本書は、シェンカーによるベートーヴェンの後期のピアノ・ソナタ第30番 op.109の批判校訂版、作品理解のための詳細な手引き等からなる。同校訂版は、当時それまでに刊行されていた校訂版と異なり、作曲者と直接かかわりのある資料を参照しつつ、随所で的確な判断を下している。しかも、作曲者の指示と校訂者の解釈が楽譜上で明確に区別されている点で、ビューローやリーマンの実用版とは大きく袂を分かつ。手引きは、作品の構造に関する注釈や具体的な演奏指南、他の版への批判を含む。判断の根拠や思考の過程を示しながら展開される作品分析は、目前でシェンカーの講義を受けているような印象を読む者に与える。研究者はもちろん、演奏家にとって裨益するところ大と言えよう。