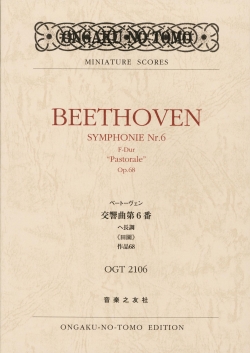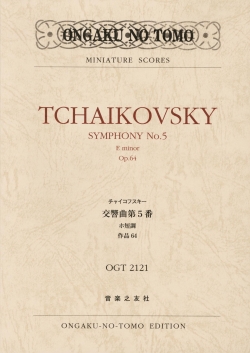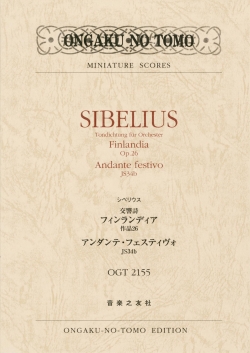第12回 「作品の魅力をいかに伝えるか」――それぞれの工夫が冴えるスコア解説
本欄をお読み頂いている読者の皆様で、いわゆるオーケストラ用の「総譜」、それもポケット・スコア、ミニチュア・スコアと呼ばれるものに、日常的に接している方はどのくらいいらっしゃるのだろうか。筆者の貧困な想像力を働かせてみても、プロ・アマのオーケストラ関係者、あるいは研究者や一般のクラシック・ファンくらいしか思いつかないのだが。基本的にこの手の楽譜は、そもそもある程度楽譜を読める人でなければ手に取ろうと思わないであろう。いずれにせよ、専門性の高いものであることは間違いない。
だが、そんな専門性の高いものを、今回は万人向けにわかりやすく書評せねばならないのである! 西洋音楽史の回でも述べたが、専門性の高いものを、そのまま専門性高いままに解説するのはそれほど難しいことではない。井上ひさしではないが、「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく」伝えるのは、筆者のような浅学菲才の徒には荷が重い。
・・・などと愚痴を言ってもしょうがないので、今回も至らぬなりに頑張るか。ある作品のスコアを買ってみようという動機が生まれるというのは、やはりその曲、あるいは作曲家に対して相当の思い入れがあることの証左でもある。音楽ファンであれば、愛する曲を知るためには、実際の楽譜にあたり、作曲家が楽譜に込めた息吹を知りたい、と思うのは自然の流れであるはず。であれば、尋常ならざる量のオタマジャクシを前に、それがどのような基準に従って配列されているのか、ということを知るための、いわば「旅行ガイド」にあたるものは当然必要であろう。
そこで、いわゆる「曲目解説」というものの出番となる。読者の皆様が普段この種の解説に出会うのは、圧倒的に演奏会場だろう。実はこの演奏会場で配られる(あるいは購入する)解説には、基本的に様々な制約がつきまとう。まずは文字数の問題。オーケストラの定期演奏会の場合、一部の例外を除き、原稿用紙にして10枚、4,000字がほぼ最大のラインである。普通は6~7枚、2,400字の中に、約3曲分の解説を押し込まねばならない。そして譜例の問題。大抵の場合、「演奏会にいらっしゃるお客様全てが楽譜を読めるとは限らない」という前提の下、そして楽譜の浄書に時間とコストがかかる、という実際上の問題もあり、演奏会場で配られる解説に楽譜は含まれないことがほとんどである。
かくして、演奏会の曲目解説を担当する執筆者達は、言葉の力だけで音楽について説明せねばならないという苦行を強いられることになる。作曲の経緯、初演情報など、文字だけで伝えられる情報はまだよい。執筆者の誰もが大なり小なり困るのは、そこで演奏される音楽の実際を、極度に限られた文字数で、楽譜の助けを借りることなく、難しい専門用語も使うことなく描写せねばならないこと。筆者もさまざまな演奏会用の解説を手がけてきたが、この難問をうまく解けた、という手応えを如実に感じられたことは、ただの一度もない。と、この場を借りて白状し、お詫びしたい。音楽を言葉で語ることの可能性・不可能性という議論については、脱線甚だしくなりそうなので、いまはここまで。
・・・賢明な読者諸賢は、筆者がこの後、「だからこそポケット・スコアのような媒体で、文字数の縛りも、譜例の縛りもなく、音楽について執筆することができるのは素晴らしい」という論旨を展開するのだろう、と考えられるかもしれないが、実はそうではない(!)。この命題も決して真実ではないと思う。縛りがない状態、すなわち「何をどれだけ書いてもいいですよ」という状態で原稿を依頼された場合(実はこのエッセイもそうだったりします)、書き手は与えられた自由の過剰さに惑い、惑ったあげくに、結局自らで縛りを設定したうえで、読者を飽きさせない解説を書かねばならないのである。「文字数縛り」「譜例使えない縛り」よりも、自分で縛りを考えねばならない分、ハードルは高いのである。嗚呼。
ここ数年、音楽之友社が、独自に楽譜を組むところからはじめている一連のミニチュア・スコア。そのスコアの解説を手がけている諸氏は、「いかにしてこの作品の魅力を伝えるか」「いかにして音楽に隠された秘密を白日の下に晒すか」を、それぞれの工夫と共に、自らに「縛り」を課しながら伝えようと努力されている。まず注目すべきは、ラフマニノフ《ピアノ協奏曲第2番》で、作曲家として、演奏家としての知見を充分に披露している野平一郎氏のそれであろう。野平氏は解説の大部分を曲の詳細な分析に費やし、その主題同士の関連性を、豊富な譜例と共に論じ尽くしている。コンポーザーにしてパフォーマー、両者を兼ね備えた視点からラフマニノフの作品を徹底的に「解剖」してみせる氏の筆致は、縦横に冴え渡る。その明晰な文体の故に、読み手はどの部分を指した説明かを見失うことがないため、多少難しい専門用語が使われていたとしても、むしろその用語が音楽のどの部分を、どういう現象を指すのかを、音楽そのものから学ぶことさえできるのだ。第3楽章のロンド形式がちょっと変形され・・・、などという話から、本来のロンド形式はどういうものかを学ぶことができる解説など、滅多にお目にかかれるものではない。
ここで取り上げているスコアの解説を執筆しているのは、いずれも日本の第一線で活躍される音楽学者の方ばかり。その筆致と解説はそれぞれの個性を反映するものだが、曲の本質をとらえ、ガッチリ離さない点では共通しており、現代の新しい作品研究がどこまで進んでいるのかを、専門的な論文を繙(ひもと)くことなく知ることができる絶好の読み物でもある。メンデルスゾーン研究の第一人者である星野宏美氏は、《交響曲第3番》解説中に譜例こそ使わないものの、豊富な小節番号の提示と、楽曲形式を表で示すことによって、必要な情報を過不足なく提示している。また、巻末にメンデルスゾーンのスコットランドへの旅の詳細を別途綴ることによって、この作品が遠く悲劇のスコットランド女王メアリー・スチュアート(シラーの戯曲、そしてドニゼッティのオペラでもおなじみ)に由来するものであることもわかる。他に例を見ないこうした独自の工夫によって、曲に対する理解はいや増すことだろう。
ベートーヴェンの交響曲を担当するのは《第6番》が土田英三郎氏、《第7番》が沼口隆氏。以前もベートーヴェンの稿で、このひとの音楽には人を徹底的に「分析したくなる」欲求へと駆り立てる何かがある、という旨を書いたが、まさにその意味で、ここでは二人の専門家が本格的な分析を試みている。これほどまでに尽きせぬ泉のような魅力が、いまだベートーヴェンの音楽には宿っているからこそ、研究者も聴き手もその魅力を探ろうと、今なお躍起になるのかもしれない。《第7番》には、ワーグナーが語ったという有名な、そして謎めいた惹句である「舞踏の浄化Apotheose des Tanzes」への言及がきちんとあるのも嬉しいところ。
分析に全力投球したくなるベートーヴェンとは対照的に、チャイコフスキーの《交響曲第5番》を取り上げる森垣桂一氏、シベリウスの交響詩《フィンランディア》《アンダンテ・フェスティヴォ》を取り上げる神部智氏の筆致は、曲の成立背景にも目配りが行き届き、その過程からも曲の魅力を語り尽くそう、という思いが行間から溢れている。とりわけ、祖国への愛を吐露したといわれる《フィンランディア》のどの部分に、どのような「思い」が込められているのか、その改訂の過程から説き起こす筆者の説明からは、曲そのものの魅力がおのずと伝わってくるようだ。
もしあなたが、スコアの中に溢れかえるオタマジャクシに過度の不安を持っていたとしても、是非一度このスコア群を手にとって、その充実した解説に目を通すところからはじめてみてはいかがだろう。隗より始めよ、千里の道も一歩から、である。ただ、もちろんのことながら、解説だけで充足することなく、CDを聴きながら楽譜を眺める行為も、是非忘れないで頂きたいと思う。幾多の言葉を尽くしても、なお説明しきれぬ圧倒的な力が、楽譜の中には、そして音楽そのものには宿っており、それこそが、我々が音楽を聴く究極の、根源的な理由でもあるのだから。こんなに言葉を連ねても、言いたいことはたったそれだけなどというこのエッセイなど、音楽の前にはなすすべもないのだから(!)。