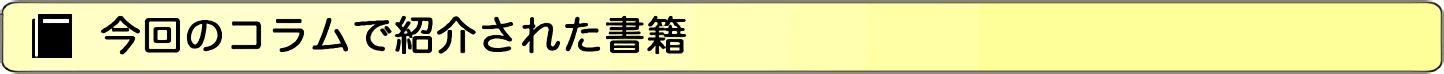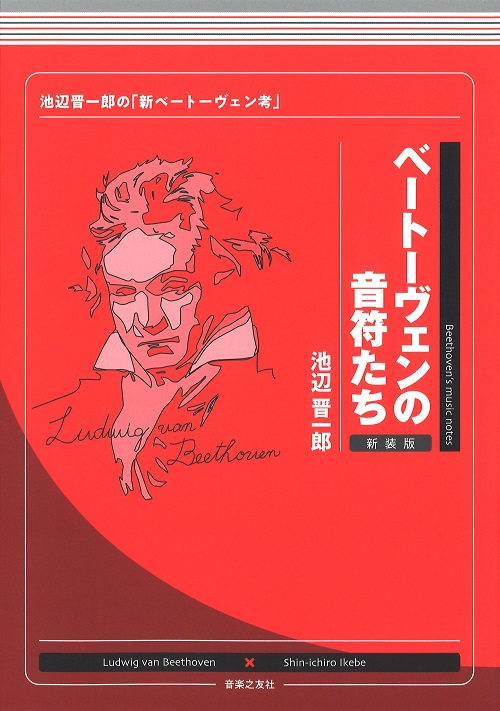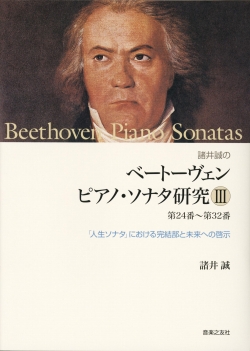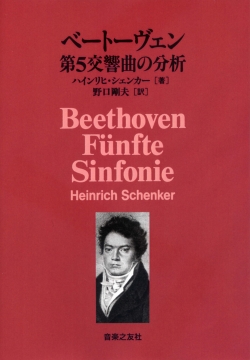第9回 作曲家の「文法」を知る=アナリーゼ!
よくもまあ、これだけベートーヴェン楽曲のアナリーゼ、分析を主題とする本が、ずらっと勢揃いしたものである。さすがは伝統のオンガクノトモシャ。「今回はベートーヴェン本の書評、お願いします」という担当Uさんのメールを目にした瞬間、一瞬意識が遠のいたことは秘密である。
「アナリーゼ? 分析? 小難しいのは勘弁してください。音楽は世界の共通語! 聴いて楽しければそれでいい! 難しい理屈は願い下げ!」そう仰って、ブラウザの「戻る」ボタンをクリックしようとしている読者のみなさん、もう少しお待ちを。そもそも作曲家が思いの丈を込め、全身全霊をもって書き遺した楽譜には、ただ耳に心地よい音楽を再現するための記号が書かれているだけではないのである。楽譜を「感じ」、「演奏する」だけではなく、「読み」、それを「解釈・分析」することにはどんな意味があるのか。原田宏美さんは、『ベートーヴェン ソナタ・エリーゼ・アナリーゼ! 名曲と仲良くなれる楽曲分析入門』(現在絶版)で、その魅力をこんな言葉で表現されている。
「作曲家が楽譜に書きとめた音符や記号は、私たちにメッセージを送っています。ほとんど暗号のように。そして、そうしたメッセージを読み取れたとき、そのときにこそ、作曲家と対話ができたと感じられるのです。そういった体験は、まるで宝の地図で宝のありかの謎が解けたように、私たちを最高に幸せな気持ちにさせてくれるにちがいありません。」
そう、アナリーゼというのは、なにもプロの演奏家や、音楽学者だけの専有物ではない。あたかも外国語を少しずつ学ぶように、和音の構造、旋律の動き方の特性、そしてソナタ形式に代表される、一つの曲を構成するためのお約束ごと(いわゆる楽式論)を少しずつ学んでいくと、作曲家が作品を作るに当たって何を考えていたのか、そしてそれをどのような「文法」で表現しようとしていたのかが、だんだん見えてくるようになる。ちょうど外国語を学ぶことと、実態はあまり変わらないのである。いわゆる「楽曲分析」というのは何なのか、何をすることなのか、これをやることによって何がわかるのか、誰もが知っている曲を取り上げ、わかりやすく解説してくれているこの本は、音楽の「文法」に興味のある方ならば、きっと楽しく読み通すことができるはず。
そういえば、アナリーゼというと、どうしてこんなにベートーヴェンばかりがずらっと並んでしまうのか、という話をまだしていなかったので、それについて触れなくては、と思っていた。いたのだが、その理由は私などが触れなくても、作曲家・池辺晋一郎氏が、『音楽の友』に執筆なさっている名コラムをまとめた単行本『ベートーヴェンの音符たち』で、すでに解説してくださっていたのだった。それも、筆者のように回りくどい言い方でなく、ごく簡潔に。だが力強く。
「あのゥ・・・・・・のっけから愚痴になるけれど、この「音符たち」シリーズ、このベートーヴェンが、これまでで一番やりにくいですね。バッハに始まり、モーツァルト、ブラームス、シューベルトとやってきた。論じられているという点では、どなたも同様。ただ、その「音符たち」がもっとも分析されたがっている顔をしているのがベートーヴェンであるらしい。何しろ、動機(モチーフ)の操作、展開の超達人なのだ。名曲であればあるほど、言葉は悪いが、さんざんいじくり回されてきた。で、名曲は、ここで外せない。従って、あらたまって音符を見つめる僕としては、ベートーヴェンはやりにくいなぁ、ということになるのである。」
いやいや、池辺先生、その鮮やかなアナリーゼの手さばきを見る限り、ご謙遜にしか聞こえませんよ。作曲家の視点からモチーフを切り分け、和声の構造を抽出し、それが作曲技法としてどのように「斬新」であったか、どのような作曲家の個性が刻印されているのかが実によくわかる。しかも、それを説く文章が平易きわまりない。本を読む全ての人にわからせよう、という執念すら感じられる。ここまでに挙げた二冊は、「作曲家と対話できるとこんなに楽しいよ!」というおもしろさを、読者と共有したいというサーヴィス精神に満ちあふれている。
次の二冊は、音楽の「文法」を一通り学び終えた人用の中級編。ご自分で楽譜を見てピアノを弾きこなすことができる方、あるいは筋金入りのベートーヴェン・ピアノ・ソナタ・ファンの方向け、といった感じだろうか。ウィーンのピアニストにして研究家、教育家としての活動も精力的にこなすパウル・バドゥーラ=スコダは、ベートーヴェンの生誕200年を記念して制作されたテレビ番組でソナタ全32作の演奏と解説を行い、それをもとに1970年、『ベートーヴェン ピアノ・ソナタ 演奏法と解釈』をまとめた。昨年で6刷を重ねた、という事実が、40年以上愛読されてきたこの本の価値の高さを雄弁に物語っている。本格的な楽曲分析ばかりに走ることはなく、かといってピアニストのためだけに書かれた実用的な演奏指南書でもなく、その中間を行くようなイメージ。スコダの抑えた筆致からあふれ出るのは、作品の本質、作品への愛情であろう。
もう一冊は限りなく上級に近い中級と考えた方がよいかもしれない。これまでの本は、旧来の分析手法、「文法」を用いて、万人向けに開かれたアナリーゼを模索していたが、ここからの本は、その分析手法、音楽の「文法」を、自らの手で作ることによって、ベートーヴェンの作品に新たな光を与えようとする。旧来の方法に甘んじることなく、グレゴリオ聖歌の楽節の分け方をウィーン古典派の分析に応用すればよいのでは、と考え、それを実践に移した諸井誠氏の偉業「ベートーヴェン ソナタ研究(全3巻)」は、昨年に完結したばかり。分析部分は、読み手にかなりの「文法」知識がないと読みこなすのは難しいかもしれないが、「コーヒーブレイク」や、各種コラムによって、ベートーヴェンの生きた時代へも暖かなまなざしが注がれており、読み手への配慮が至る所に感じられる。
そして、疑いなく上級編、いや超上級編の二冊として、20世紀初頭に活躍した音楽著述家、ハインリヒ・シェンカーによるベートーヴェンの交響曲分析を扱った理論書がそびえ立つ。『ベートーヴェンの第9交響曲 分析・演奏・文献』(1912)、雑誌『音の意志Tonwille』に掲載された『ベートーヴェン 第5交響曲の分析』(1925)をひもといてまず感じるのは、それまでの因習的な分析方法に対する、過剰とすら思える攻撃性であろう。シェンカーは返す刀で、作品の核となる旋律線「ウアリーニエ(根源的旋律線)」を抽出するという方法を創案し、旋律を把握するための新しい概念を生み出した。作品の根源を、音楽とは関係のない言葉で説明しようとする「印象批評」を痛烈に批判しながら、必要とあれば音楽そのものを説明するための語彙すらも生み出すその独創性は「シェンカー理論」と名付けられ、特に戦後、60年代のアメリカで大きな注目を浴びるに至る。いわば、シェンカーは、それまでの「文法」に飽きたらず、そしてその「文法」をいじる評論家たちに飽きたらず、自分で音楽分析のためのあらたな「文法」を開発しようとした、といえば(かなり語弊はあるかもしれないが)、その実態はおわかりいただけるだろうか。晦渋・難解きわまるドイツ語を、その意図するところを尊重しながら、できる限りわかりやすい日本語へと置き換える努力を惜しまなかった訳者の皆様の労には、心より御礼を申し上げたい。
ベートーヴェンのアナリーゼ本を、次から次へと、立て続けに、とっかえひっかえ読むことなど、今後の自分の人生にはもうないことだろう(と信じたい)。交響曲とピアノ・ソナタ、同じ作品を様々な人が、様々なアプローチで分析を試みるさまを間近にすると、まるでベートーヴェンという偉大な恋人に対し、皆が競ってラブレターを書いているかのような錯覚に陥る。自分の魅力をあちこちから注視され、言葉という言葉で説明し尽くされるベートーヴェンは、どう感じるのだろう。まんざら悪い気はしないのか、それとも「いろいろ説明してくれるのはありがたいけど、やっぱりまずは俺の音楽を聴いてくれ」と言われるのがオチなのか・・・。