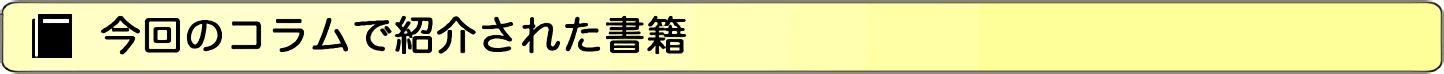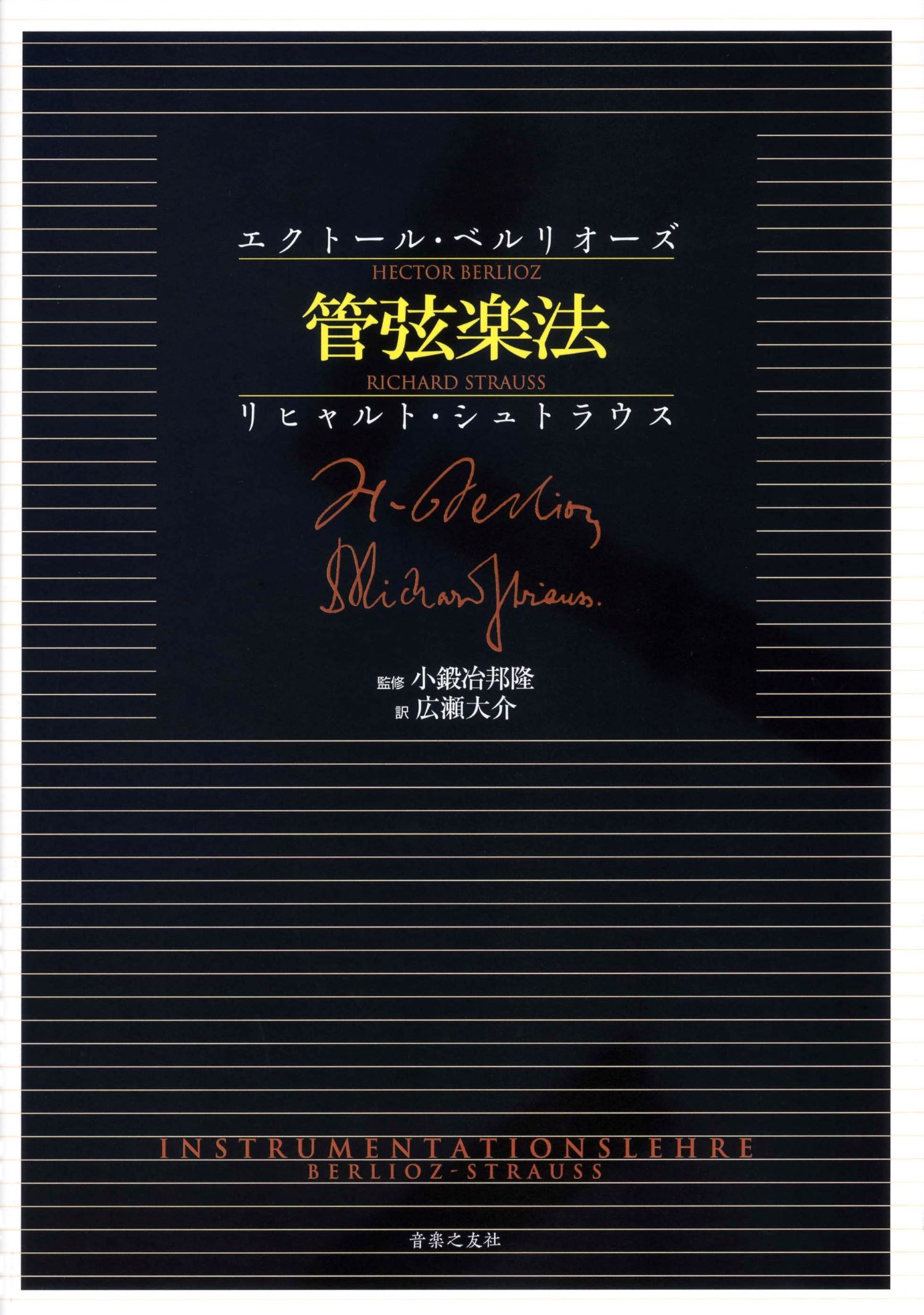第4回 管弦楽「法」とは何なのだろう?
いつも、「管弦楽法」という言葉を使うたび、「法」の一字にひっかかりを覚えてきた。和声法や対位法に「法」の字が使われているのは全く以て納得である。18世紀以降の西洋音楽の根幹を成す機能和声には、その音の選び方に厳格なルールが存在し、それが「法」の名の下に体系化されているのだから。
だが、管弦楽「法」において、体系化されている、されようとしているものの実態は、一体何なのか。そもそもそれは体系化され得るものなのか。いわゆる「管弦楽法 Instrumentation, Orchestration」と呼ばれる理論書が登場するのは19世紀以降のことである。これは、オーケストラ音楽の複雑化、肥大化が進むにつれて、用いられる楽器の数が増大したため、オーケストラで用いられる楽器の奏法、音域、音色の特性などをまとめる必要がでてきたことによる。
したがって、19世紀中頃にエクトール・ベルリオーズが編んだ著作は、その実態を汲んで、本来ならば「楽器奏法集成」とでも訳さねばならないところだろう(自分で訳しておきながら、まったく申し訳ないことである)。ベルリオーズは主に楽器の奏法について執筆し、それがどのように実際のオーケストラ作品で用いられているかを例示することに意を砕いたが、半世紀後に加筆を施したシュトラウスは、新しい楽器の奏法もさることながら、ワーグナー作品における用例をこれでもかとつぎ込んだ。現代的な目から見れば、いわば19世紀半ばの楽器運用の実際を伝えるケーススタディ集というのが、最も適当なところであろう。19世紀から20世紀にかけてのオーケストラ音楽が、どのような発展を見せたかを知る上で、二人の超一流作曲家によるドキュメントは実に示唆に富んでいる。
第3回でも触れた作曲家ウォルター・ピストンによって『管弦楽法』が執筆されたのは1955年。作曲家・戸田邦雄による邦訳が登場したのが67年のことである。さすがに戦後ともなると、管弦楽を扱う上でのより包括的な視点が生まれてくる。全体は三部に分けられ、第一部はそれまでの楽器奏法に充てられているが、第二部は管弦楽作品の実際を「ユニゾン」「旋律と伴奏」「声部書法」など7種類に分けて分析し、第三部には実習問題を配して、読者が実際に管弦楽の書法を段階的に習得できるような配慮が施された。オーケストラ書法を学びたいという学生のために書かれた教科書としての側面が強いのが特徴だろう。自身の《和声法》《対位法》と同様、20世紀までのオーケストラ音楽のケーススタディ集成であるという点においては、ベルリオーズ、シュトラウスのそれと大きく変わるところはない。
その点、伊福部昭ほど、「法」という言葉にこだわったひとはいないだろう。彼にとってのライフワークでもあった著作『管絃楽法』のあまりに幅広い内容には、ただひたすら驚きを覚えるより他はない。ベルリオーズやピストンが論じた観点が含まれるのはもとより、音響学、音と聴覚の関係、聴き手の心理学的考究に至るまで、理系の学問を修め、林務官として働いた前職を持つ筆者ならではの精緻な筆致が隅々まで行き渡っている。
だが、ここまで管弦楽「法」を突き詰めたにもかかわらず、いや、突き詰めたからこそ、伊福部はその限界をも明確に規定する。冒頭、この言葉を規定する伊福部は、次のような留保をつけている。
「管絃楽法とは、ある楽案をいかにして管絃楽化するかと言うその手段を考究する学科である。即ち、管絃楽と言う音楽の大きな表現媒体を、最も合理的に、最も効果的に支配するための手法上の約束を知ることであり、言わば一種の効果のための研究なのである。従って、半ば物理的な、半ば音響心理学的な問題が主流となるのであって、ある想念が音楽としての形態をとるに至る過程、即ち、内部的音楽創作に付いては関与するところがないのである。」
この「一種の効果」を、およそ考え得る限りのさまざまなアプローチから追求したからこそ、伊福部の『管絃楽法』は、世界に類を見ない、唯一無二の理論書として、その圧倒的な存在感を放ち続けているのだろう。いや、この「一種の効果」だけに絞ったからこそ、これだけさまざまな観点から論じることが可能になった、と言うべきか。
この三冊を並べれば、オーケストラ音楽を巡る「理論」は、わずか1世紀程度でここまで発展したのか、と目を瞠らずにはいられない。だが、管弦楽のバラエティに富む諸相を学問的に語ろうとすればするほど、やはり和声「法」や対位「法」のように、一定の規則の中で収まりきるようなものではないのでは、という感は大きくなるばかりである。伊福部が「内部的音楽創作」と呼ぶ作曲家の霊感を、オーケストラという道具で適切に表現するため、先賢の工夫を能う限り吸収し続けるための学問として「管弦楽法」が規定されるのであれば、それはやはりどこまで行っても、体系化を拒否するような、一流作曲家の先例を収集するケーススタディの集積たる本質は変わることはないのではないか。そんな思いが、筆者の念頭からは去ることがない。
いったい、管弦楽「法」とは何なのだろう?