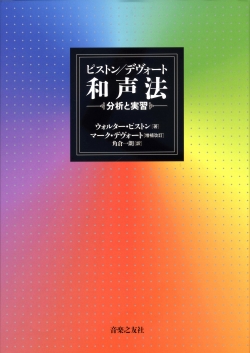第3回 西洋音楽の成り立ちの本質に触れる――わかりやすい日本語による素晴らしい訳業
和声法・対位法の教科書として、アメリカの作曲家ウォルター・ピストン(1894-1976)の原著が日本の音楽大学で採用されていた事例は、決して多くはないだろう。だが、筆者が通っていた一般の大学では、このピストンによる和声法を教材として用いていたことを懐かしく思い出す(今思えば、恩師は慧眼の持ち主だった!)。その教科書を、いまこうして日本語の形で手に取ることに、深い感慨を催さずにはいられない。
この二冊は、和声法・対位法を勉強しようとする人のための教科書である。それをマスターするためには、もちろんきちんと実習課題をこなさねばならない。だが、西洋音楽の根幹を成す、縦糸と横糸たる二つの規則の本質に触れてみたい、という人は、まずは実習課題には目をつぶり、敢えて読み物として通読することをお勧めしたい。ただ「読む」だけでも、西洋音楽の本質とは一体どういうものなのか、その核心の一端を垣間見ることができる作りになっている。
ピストンがこだわるのは、「なぜ」特定の音の組み合わせが禁止されているのか、あるいはこうした規則が「どのように」用いられてきたのか、という実例を、古くはバッハにまで遡り、豊富な譜例で示すことにある。無味乾燥な和声の規則を、古今の名曲とともにイメージし、記憶に定着させることができる教科書など、他には存在しない。作曲家ピストンが、自身の創作活動に於いて得た様々な知識を、あたかも一枚の地図のように、一望の下に提示している、という感すら受ける。
『和声法』におけるピストンの真骨頂のひとつを、第14章「転調」に見てみよう。普通の和声の教科書では、転調における和声の規則だけが素っ気なく語られるに過ぎない。だが、ピストンは、曲の中で「なぜ」転調が実施されねばならないのかに触れるところから論を説き起こす。そして転調が「どのように」行われるのか、その段階を三つのステップに分け、そのステップを、モーツァルトの名曲《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》K.525第1楽章を例に解説してみせる。ソナタ形式における第1主題から第2主題への移行に伴う転調の実際が、明瞭な言葉で説得力豊かに論じ尽くされている。その鮮やかさたるや、類書の遠く及ぶところではない。
『対位法』は、600ページ近い『和声法』に比べれば、二分の一以下の厚さしかないが、その内容・情報量は、和声法に勝るとも劣らない。そして、いきなり2声対位法から論を始めるのではなく、声部の基礎となる旋律とはいかなるものか、どのように形作られるべきなのかから説き起こすところから、この本ははじまる。ピストンの論旨を読み進めれば、大げさでなく、彼が西洋音楽の成り立ちそのものの本質に触れていることがわかる。5声対位法の例として挙げられたバッハの《ブランデンブルク協奏曲》第4番KWV1049第3楽章、あるいはモーツァルトの《交響曲第41番》K.551第4楽章の譜例を見れば、人口に膾炙した作品が、いかに緻密な構造のもとに形作られているかが実感できる。そして、こうした天才の筆先で達成された音楽的霊感と数学的理論の融合を目の当たりにすれば、偉大な作曲家たちに対し、深く頭を垂れずにはいられない。
ピストンはアメリカでの教育を念頭に本書を執筆したため、日本で慣習的に用いられる和声・対位法の専門用語とは必ずしも一致しない説明もある。西洋音楽史の碩学・角倉一朗氏は、そうした細かな点まで目配りを怠らず、わかりやすい日本語によって素晴らしい訳業を成し遂げられた。氏への深い感謝と共に、この春から筆者もピストン『和声法』を手に、学生と相対する予定である。