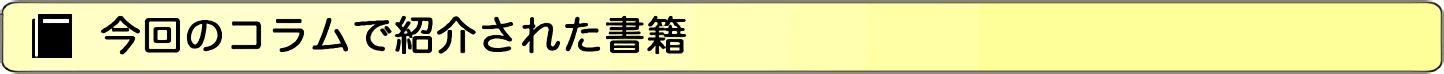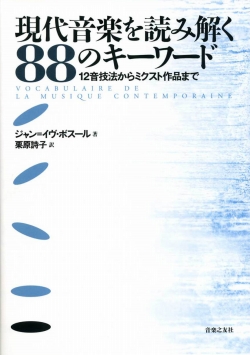第2回 作曲家の思考を追体験する試み ―語義の多彩な変遷と,作曲過程の解明
普段から何気なく使ってしまう音楽用語。だが、こうした用語とその定義を、当の概念を生み出した作曲家が認めているとは限らない。ワーグナーは自身の作品が単純に「楽劇」という言葉で片付けられることを嫌い、「3幕の所為」だの「舞台神聖祝祭劇」だの、いろいろと不思議な名前をつけた。
20世紀に至っても、このあたりの事情はあまり変わらないようである。いや、むしろ様々な音楽語法が爆発的に拡がったためか、その語法の考案者たる作曲家、あるいは他の音楽家や学者があまりにも厳密に再定義を行おうとして、さらなる混沌へと陥っているようにすら見受けられる。
ボスールの『現代音楽を読み解く88のキーワード』は、こうした語義の多彩な変遷を、実際の作曲家の発言を引用し、それを並べることによって、自ずと読者に知らしめようと試みる。「無調」の項を見れば、「無調=調性がない音楽」という短絡的な我々の思い込みを、シェーンベルクがあの手この手で戒めようとしているのが見て取れるはずだ。
20世紀の新しい音楽の潮流を、(ピアノの鍵盤の数に倣ったのか)88のキーワードに添って概観しようというこの本。アンソロジー的に、興味のある項目を拾い読みするだけでも、単なる辞書の定義にはとどまらない、「そのキーワードによって、作曲家はどのような思想を表現しようとしたのか」という思考の跡が追体験できるようになっている。これこそが、本書の最大の長所だろう。筆者自身のコメントもさることながら、折々に登場するピエール・ブーレーズが、その精緻な論理によって、何となくイメージが先行するだけのキーワードに、鋭い洞察を与えている点も注目されよう(とくに「即興」の項など、怒れるブーレーズの面目躍如!)。
『作曲の技法』という書名を見て、「これを読めば誰でも作曲ができる!」という類の入門書を想像してはならない。何しろその著者は、およそ考え得る限りのハイブロウな日本語で、自身の思考を精緻に、そして自在に綴ることのできる小鍛治邦隆なのだから。当代きっての作曲家が、作曲家の視点で、バッハから新ウィーン楽派までの作曲家の作曲過程を順に説明するその筆致は、ボスールとは別のレトリックで、作曲家の頭の中を鮮やかに解剖してみせる。
小鍛治は、第1章「対位法と作曲のオートマティズム」で、バッハとヴェーベルンの例を取り上げ、両者の音楽に共通する「自律的、あるいは自己組織的な作曲法」に注目する。バッハの《インヴェンション》や《フーガの技法》、あるいはヴェーベルンの《弦楽四重奏曲》を例に、曲の冒頭に掲げられた基本形が模倣、反行、拡大を繰り返しながら自己生成していくような両者の作曲法が、巧みに解き明かされる。最終的に二人の音楽の共通性を「音楽的テクスト生産におけるサイバネティックス(人工知能学)としての作曲技術」である、と総括してみせるその強靱な文体は、(確かに字面は難しいが)決して理解不能なものなどではなく、むしろ首尾一貫した、豊かな説得力を有している。「日本語は論理的な叙述に向いていない」という神話は、単に「日本人には論理的な思考ができないひとが多い」ということでしかないのが、この本を読めば痛いほどよくわかる。