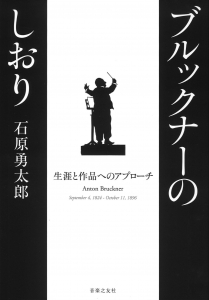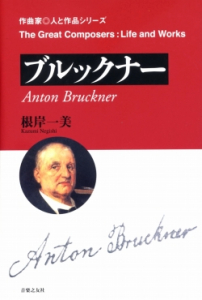広瀬 大介(ひろせ・だいすけ)
音楽学者、音楽評論家。1973年生まれ。青山学院大学教授。日本リヒャルト・シュトラウス協会常務理事・事務局長。
近刊に『知っておきたい! 近代ヨーロッパ史とクラシック音楽』(音楽之友社)、その他の著書に『もっときわめる! 1曲1冊シリーズ3 ワーグナー:《トリスタンとイゾルデ》』『楽譜でわかる クラシック音楽の歴史 古典派・ロマン派・20世紀の音楽』
(以上音楽之友社)、『オペラ対訳×分析ハンドブック シュトラウス/楽劇 サロメ』『同 シュトラウス/楽劇 エレクトラ』『同 シュトラウス/楽劇 ばらの騎士』『リヒャルト・シュトラウス自画像としてのオペラ』(以上アルテスパブリッシング)、『帝国のオペラ』(河出書房新社)など。『レコード芸術』など各種音楽媒体での評論活動のほか、NHKラジオへの出演、演奏会曲目解説・CDライナーノーツの執筆、オペラ公演・映像の字幕・対訳などを多数手がける。
広瀬先生 最新刊!
『世界史×音楽史 知っておきたい! 近代ヨーロッパ史とクラシック音楽』
第60回 記念年明けにじっくり読みたいブルックナー本2冊
2024年はアントン・ブルックナー(1824-1896)の生誕200周年に明け暮れた印象が強い。昨年だけで、ブルックナーの演奏会には何度行っただろう。《交響曲第8番》の初稿など珍しいバージョンが聴けた一方、演奏される曲目にある程度の偏りもみられたようで、普段聴くことの難しい作品にあまり触れることができなかったようにもおもわれた。個人的には《第5番》の演奏機会が少なかったのが残念だったが、それでも、数多く演奏に触れることができたのはありがたかった。
アニヴァーサリーということで、ブルックナー関係の日本語著書も数多くリリースされる中、その掉尾を飾るように登場した石原勇太郎氏の『ブルックナーのしおり 生涯と作品へのアプローチ』 は、さまざまな意味において、日本における今後のブルックナー需要に大きな変革をもたらすことになるだろう。
著者が「はじめに」において「自分なら第7章を読んでから他の章に進む」(11ページ)と書いておられるので、評者もそれに従って第7章から読み進めた。「神話の形成と分解――多様なるブルックナー像の構築」、と題されたこの第7章は、おもにふたつの問題提起から成っている。
ひとつはブルックナー死後の作曲家像形成における、第三帝国の関与にかかわる問題。「大ドイツ的理念」、国民社会主義的な理想を示すために、校訂に際してロベルト・ハースが歪んだ姿勢を示したことをあらためて論じた上で、音楽と政治、思想と楽譜校訂に関して、現代に生きる我々にとっても、それが単なる歴史上の出来事に留まらないことを教えてくれる。なにより、ブルックナー受容の(おそらく著者は「歪んでいる」と考えているであろう)現代の在り方の源泉を知ることで、純粋に、正面からブルックナーに向かい合うことを、聴き手のひとりひとりに求めているのだろうから。
もうひとつはブルックナー作品とジェンダーの問題。日本では「ブルックナー・オタク(ブルオタ)」という言葉が独り歩きしているほど、ファン層が男性に偏っている現象としてひろく共有されている感覚だろうが、これはヨーロッパにおいてもある程度当てはまるようだ。「小さな、しかし多様な外的要因が積み重なることで、(少なくとも日本では)ブルックナーの作品には強力な男性性がこびりついてしまったのではないか」(310ページ)との著者の指摘には、本来は万人にひらかれた作曲家・作品であるはずだ、そうあらねばならない、という著者のしずかな、だが力強い主張が感じられよう。
第7章に目を通したうえで、あらためて第1章から第6章の記述に戻れば、人生の各ステージにおけるブルックナーの活動とそのひととなり、主要楽曲の(おもに形式と調性に重きを置いた)過不足ない分析が淡々と続いてゆく。簡にして要を得た記述。なるほど、これはたしかに、ブルックナーの性格や作品を知る上での「しおり」と称するにふさわしい。まずはこの本をきっかけとして、読み手が自分自身でブルックナーの音楽に正面から向かい合い、そのうえであらためて自分なりのブルックナー像を形作ることを、著者は読み手のひとりひとりに促しているのだろう。
著者のこだわりは随所にみられるが、ここでは、《第0番》をその作曲過程から、あらためて《無効交響曲》と呼ぶことを提唱していることをご紹介しておこう。これは、『作曲家◎人と作品 ブルックナー』
など、数多くの著作でブルックナーを紹介し続けた根岸一美氏もまた長年にわたって提唱している説であることはひろく知られているところ。もちろん著者もそのことに言及している(104ページ)。ひろく読まれてきた根岸氏のこの著作も合わせてひもとけば、ブルックナーについての研究が新しい世代へと受け継がれ、さらなる発展を遂げようとしていることを感じられるはずである。
これからも、石原氏が数多くの研究において、より多くのファンに対してブルックナーとその音楽を開かれた存在としていくことは疑いないだろう。評者もまたその謦咳に接しつつ、ブルックナーとの新しい出会いの可能性に、大きく胸を躍らせている。
*****
最後になりましたが、ちょうど60回目となった本稿をもちまして、この連載も終わらせることとなりました。長年にわたってお読み頂き、励ましの言葉をかけてくださった皆さまには、あらためて心より御礼申し上げます。私自身も、10年以上にわたって継続的に専門書に目を通し続けることで、図らずも自身の学びを多方面に深めることができました。今後は私よりもより若い方に、あらたな立場からの評を書いて頂けることになりそうです。引き続き、新しい連載もどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
※この記事は2025年1月に掲載致しました。