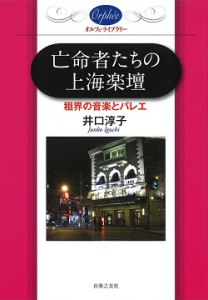広瀬 大介(ひろせ・だいすけ)
1973年生。青山学院大学教授。日本リヒャルト・シュトラウス協会常務理事・事務局長。
著書に『楽譜でわかる クラシック音楽の歴史』『もっときわめる!1曲1冊シリーズ ③ ワーグナー:《トリスタンとイゾルデ》』(以上、音楽之友社)、『リヒャルト・シュトラウス 自画像としてのオペラ――《無口な女》の成立史と音楽』(アルテスパブリッシング)、『帝国のオペラ――《ニーベルングの指環》から《ばらの騎士》まで』(河出書房新社)、訳書にベルリオーズ、シュトラウス『管弦楽法』(音楽之友社)など。
さらに各種音楽媒体などへの寄稿のほか、曲目解説・ライナーノーツの執筆、オペラ公演・映像の字幕対訳を多数手がけている。
Twitter ID: @dhirose
第55回 バロック・オペラ座・上海租界――3書で拡がるバレエの愉しみ
評者がバレエについてなにかを書くことはほとんどない。おそらくこれが初めてのはずである。オペラにはいそいそと通うのに、バレエそのものの公演に赴くのは年に数回、といったところ。敬遠しているつもりはまったくなく、肉体を限界まで酷使して究極の美を追求するその姿勢には、アスリートの研ぎ澄まされたスポーツ競技に似た趣きもあり、常に心を打たれる。そのいっぽうでその美しさを愛でるために必要な、踊りのためのテクニックなどの知識が自分には欠けており、舞台を観ても、きっと自分にはその本質が半分も理解できていないのだろうな……、とかなしくなってしまうこともある。もちろん、開き直って、無心で楽しめればよいのだが、舞台の演出や音楽が気になってしまうと肝心の踊りに目が行き届かなくなる(これは完全なる職業病)。おそらく自分は、バレエに関する諸々の知識がかなり偏っているのだろう。
というわけで、今回はそんな自分にとって(そして多くのクラシック・ファンにとってもおそらくは同様に)、あらゆる意味でその偏りを少しでも是正し、バレエの世界へと誘ってくれる近著3点をご紹介する。
バロック期の作品、とくに組曲を演奏する際に頻出する舞踏由来の作品名(舞曲)は、たとえ器楽曲としての体裁を整えていたとしても、そのリズムや楽曲の性格において本来の舞踏の様式に則って作られたものであることには変わりなく、もともとの舞踏がいかなるものであったのかを知っておくにしくはない。その意味で、自身がダンサーでもある浜中康子氏による著作『舞曲は踊る バッハを弾くためのバロック・ダンス入門』は、本来の「ダンス」を知るための、最良のガイドたりうるだろう。
もっとも、本のタイトルに「バッハを弾くための」と含まれてはいるが、かならずしもバッハに限定せずとも、あらゆるバロック期の作品(いわゆる組曲)、あるいは20世紀におけるラヴェルやプーランクなどの作品などを解釈するにあたっても、当然参考になる。本書では、ブレ、リゴドン、メヌエット、サラバンドなど、名前は聞いたことがあっても実際の音楽と結びつけるのが難しい印象があるバロック・ダンスが16種類取り上げられ、それらの実例とともに紹介されている。そしてなにより本書が特徴的なのは、それらが実際のステップなどを示す舞踏譜とともにしめされているという点であろう。自分も含め、踊らない大部分のひとにとって、舞踏譜は複雑な線の集合体にしか見えないのだが、そのうちのわかりやすい部分を図示して、そのリズムの特徴がどこにあるかを懇切丁寧に説明してくれている。QRコードでその舞踏の映像が観られるように工夫されており、行き届いた配慮とともに、舞曲そのものを、まるで自分が踊っているかのように愉しむことができるだろう。
永井玉藻氏による『バレエ伴奏者の歴史 19世紀パリ・オペラ座と現代、舞台裏で働く人々』では、バレエの上演を支えるひとたちに視線が注がれている。バレエ稽古のための教師・伴奏者を意味する「レペティトゥール」が、時代の変遷とともにどのようなひとを指し示すようになったのか、丹念に追いかける筆致は大変に興味深い。バレエの音楽的表現に弦楽器独奏が頻繁に使われ、レペティトゥールとなるバレエ教師も弦楽器奏者であることが普通だった、という記述は、その後になっても、バレエ音楽に弦楽器独奏が用いられることの多い訳を、端的に説明してくれている(例えば《ジゼル》のヴィオラ・ソロなど)。
本書のユニークなところは、こうした研究を踏まえたうえで、それらが現代のバレエ上演にどのような伝統として残っているのか、実際の舞台関係者へのインタビューを通じてあきらかにしようとしている点にある。パリ・オペラ座バレエ団でリハーサル・ピアニストを務めるミシェル・ディートラン、同団エトワールのマチアス・エイマン、さらには新国立劇場バレエ団プリンシパル・ダンサーの米沢唯など、多くのひとたちへのインタビューを通じ、これらの歴史的内容を現代に生きる伝統とつなげてみせることで、単なる歴史書・研究書に終わらぬ魅力を備えている。
さらには、1930年代以降、上海に作られた、西欧列強の半植民地、いわゆる租界における、各地からの亡命者たちによって形作られた文化的中心地においても、バレエの文化が花開いたことは、あまり知られていないのではないか。井口淳子氏の『亡命者たちの上海楽壇 租界の音楽とバレエ』では、2万人とも言われる、ロシア革命を逃れてやって来たロシア人たちのうちで、ディアギレフのバレエ・リュス(ロシア・バレエ団)を引き継ごうという志のもとに生まれた上海バレエ・リュスの活動とその実態についても、かなり詳しく触れられている。1935年に旗揚げされ、日本が敗戦を迎える1年前にはストラヴィンスキー《ペトルーシュカ》を上演し、西欧と遜色ない程度にまで成長を遂げたその軌跡は、井口氏の冷静でありつつも情熱を帯びた筆致によって、余すことなく描かれている。
本書はそれ以外にも、上海における楽壇の諸相、あるいはヴィルトゥオーゾ演奏家や日本の音楽マネージャー、原善一郎の活躍など、さまざまな側面から、上海の租界における音楽活動の全体像をあきらかにしようとしており、当時の上海にいるかのような臨場感を味わえることだろう。
バレエの音楽、あるいはその歴史については、ひとつひとつの事実を知っていたとしても、それは点としてその存在を知るに過ぎない。だが、このようにあらゆる視点からバレエの諸相を眺めることで、いままで知っていた音楽上の知識とそれらがつながって線となり、面となって拡がっていくような愉しさを覚えることができた。さきほど説明した弦楽器のソロの来歴などは、まさにそのような例のひとつに数えられよう。こうした堅実な研究・著作のひとつひとつによって、今後鑑賞することになる実際のバレエ上演に寄せる眼差しもまた、より味わい深いものとなっていくはず、と期待が膨らむのである。
※この記事は2023年10月に掲載致しました。