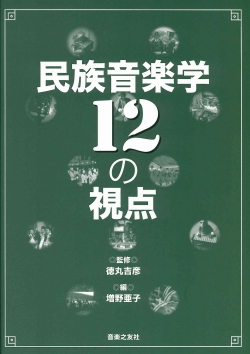第33回 民族音楽学の現在、そしてアフリカ音楽を「理解する」とは
民族音楽学、という言葉の成り立ちを考えるとき、19世紀後半から戦前あたりまでは、この新しい学問のジャンルは「比較音楽学」と呼ばれていた。もちろんその概念を作った西洋人が、自分たちとそれ以外の音楽を「比較」するという意味で、これを命名したのである。そして民俗音楽よりもみずからを上位に定義づけた「西洋音楽」という二者の対立する概念を覆し、地球上に存在するすべての音楽を平等なものとみなすところから「民族音楽学」がはじまったことは、よく知られたところであろう。というより、これからご紹介する『民族音楽学12の視点』をひもとけば、その最終章に、徳丸吉彦氏がこの問題をわかりやすく、そして熱く説かれておられるのを目にすることができるので、筆者がそこに屋上屋を重ねるつもりはない。ここでは、この2冊を読了した後で、筆者が感じた個人的な問題意識を記してみようと思う。それしかできない、と言うべきかもしれないが。
『民族音楽学12の視点』は、いま現在、民族音楽学をリードする12人のトップランナーたちが、それぞれの専門分野だけにとらわれることなく、より大きな、ふたつ以上の音楽文化を比較する「視点」から、我々を多様な音楽の世界へと導いてくれる。冒頭に見開き2ページで、著者自身がその音楽世界にどのように引き込まれていったのかが個人的視点で語られ、そのうえで概説としての学問的見地が紹介され、さらにその内容を詳しく知りたいひとのために、コラムという形でより細かな、専門的な解説が試みられる。さまざまな観点を通読して痛感するのは、紙に書き記すという形で音楽を後世に「伝承」していく西洋音楽の形態が、世界規模で音楽文化を眺め渡したときに、いかに例外的な事象であるか、ということ。そして、あらゆる音楽を包摂する学問としての「民族音楽学」が確立する過程で、西洋の学者たちが、いままで書かれることのなかった音楽をいかにして書き記すことに精魂を傾けたか、である。
この苦闘は、『アフリカ音楽の正体』をひもとくと、さらに具体的にそのイメージが掴めることだろう。『視点』ではグローバル化する音楽とその著作権問題を論じていた塚田健一氏は、『正体』においては、みずからのフィールドたるアフリカ音楽が西洋に「発見」された経緯を論じるところから説き起こす。20世紀初頭にベルリンで比較音楽学を提唱・主導したエーリヒ・フォン・ホルンボステルにしてから、カメルーンの民族集団パングウェの合唱付き木琴合奏のリズムを採譜することができなかったという。1934年になって、アーサー・ジョーンズがホルンボステルの説に反駁する形で、新しい「ポリリズム」論を提唱するに至るきっかけが、「音楽の採譜にあたっては、採譜者がそのリズムを正確に演奏できる」ことだというのだから、問題の根は深い。いささか乱暴な言い方をお許し頂くならば、そんなことにも気がつかずに採譜しようとしていたのか、と思わずにはいられない。当時の西洋文化至上主義の根はそれだけ深かった、ということなのだろう。18世紀末のモーツァルトがすでに《ドン・ジョヴァンニ》(第1幕・宴会の場で、複数の楽団が異なる音楽を同時に演奏する)においてポリリズムによる劇的効果を試みていたというのに、異なるリズムが同時に進行し、その重なりから聞こえてくる音を解釈する能力を、20世紀前半のヨーロッパ人は忘れてしまっていたのだろうか。
だが次の瞬間、この非難はそのまま自分に返ってくるブーメランであることにも、否が応でも気がつかされる。この本を読み、インターネット上で再生できる音源を聴き、それに対応する楽譜を目にしてはみたが、果たして自分はどこまでその音楽を「理解」することができたというのだろうか。幼少期にピアノやヴァイオリンを習うことで、いわゆる「西洋音楽」にもっとも慣れ親しむ形で成長し、そのまま西洋音楽を研究することを生業としてしまった筆者にとっては、結局のところ、ここで紹介されている音楽を視覚上で確認し、「理解」するための一歩を踏み出すためには、どうしても西洋音楽の記譜法に頼らざるを得ないのだから。他文化を理解するための共通語のようなものとして、いわばお互いが意思疎通を図るための、ちょうど英語のようなツールとして、楽譜という存在を位置づけるべきなのだろうか。
このほかにも、ルヴァレ音楽には和声言語に長三和音と短三和音の区別が存在しないこと、太鼓で叩くリズムと抑揚で言葉を伝達する「トーキング・ドラム」という考え方そのものに対して塚田氏が呈する疑義など、そのそれぞれが斬新であった。そしてそれにいちいち驚いている自分という存在は、あまりにも西洋音楽の考え方を血肉としすぎてしまっているのだろう。もちろん、純粋に民族音楽学、アフリカ音楽に関心を持っている読者にとって、これほど読み応えのある本はなかなか見つからないであろう。が、長きにわたってこのエッセイを書き続けている筆者にとって、これほど考えさせられ、切ない気分にさせられたことはない本でもあった。
※この記事は2016年10月に掲載致しました。

民族音楽学12の視点
「民族音楽学」は世界の多様な音楽文化を扱いながら、人間と音楽について考える学問。本書はこの民族音楽学の入門書。専門的な音楽の経験がなくても、音楽への知的な好奇心がある人に向けて編まれた。「民族」という語がついてはいるものの、民族音楽学は遠い異国の音楽だけを扱うものではなく、あらゆる音楽を扱う。本書は地域別・ジャンル別ではなく、むしろ複数の音楽文化を横断的に捉えられるような以下の視点を提示する。第一部「響きと身体」では身体、舞踊、書記性(楽譜)、言葉。第二部「伝承と政策」では、個人にとっての伝承、国家の政策、ユネスコ等の国際機関の関与。第三部「社会の中の音楽」ではマイノリティ、越境、アイデンティティ構築、知的所有権。最後に、「民族音楽学」という学問の現在までを示す。「リズム」「舞踊研究」「音組織」「採譜と分析」「資料としての楽器」「フィールドワーク」「映像」の7つのコラムも読みごたえがある。
アフリカ音楽の正体
坂本龍一氏推薦!「20世紀以降のジャズやロックを含む全てのポピュラー音楽は、アフリカ音楽の影響を受けている、あるいはそれ以上に基底にはアフリカ音楽があると言っても過言ではない。(中略)あの広大でたくさんの部族が暮らしているアフリカに、ある共通するリズムパターンがある不思議。西洋とは異なるハーモニー感覚がなぜ生じるのか、人類がもつ言葉と音楽の関係の根源に対する考えを促すような音楽と言葉との関係など、アフリカ音楽には尽きない魅力が満載である。ぜひこの本を手にとってその魅力に触れてほしい。」「理論編」では、アフリカ伝統音楽の構造を、リズム、ハーモニー、旋律、太鼓、子供の遊びなどを取り上げて解き明かす。「実践編」のアフリカの太鼓合奏実技は、音楽の授業教材としても最適。アフリカ音楽に興味を持つすべての人に贈る入門書。『音楽教育―中学・高校版』(1996~97)連載を大幅に加筆修正。