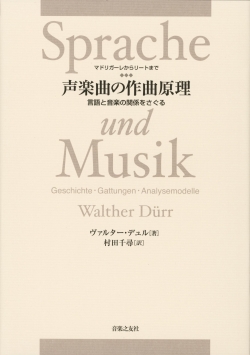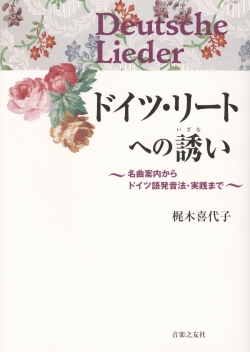第6回 言葉そのものが持つ響きが音楽へ与える影響とは
最近、ヨーロッパのクラシック音楽の素晴らしさを説くあまり、「音楽は世界の共通語」という類の標語を、大まじめに説く人は少なくなったように見受けられるが、現状はどうなっているのだろう。個人的には大変望ましいことだと思っている。少なくともこの言葉は、間に言葉を介さない純粋な交響曲や器楽曲に対して用いられることが多い。だが、そのような曲といえども、少しでも曲の背景を知ろうと試み、そのうえで西欧の音楽を眺めれば眺めるほど(やっかいなことに、それが名作であればあるほど)、いかにその音楽が、それを生み出した文化的土壌に根ざしたものであるかを、いやというほど思い知らされることになるのである。まして、それが現地の言葉を伴う歌曲、劇作品などになれば、言葉という高く、厚い壁が、我々日本人の理解を妨げる。そのような壁を前にして、評者自身、無力感を覚えたことは一再ではない。
その意味で、シューベルト研究の泰斗であるヴァルター・デュル博士が、専門のシューベルトのみならず、ヨーロッパの声楽曲における言葉と音楽の関係を本質的なところから説き明かした著作『声楽曲の作曲原理』が日本語で読めるようになったことの意義は限りなく深い。
これまで声楽曲を分析する、という行為は、いわゆる器楽曲の楽曲分析の手法を援用すると同時に、歌詞が指し示す内容を、どのように音楽が表現しているか、という個々の「音楽的」技法を考察することが多かった。デュルがこの著書で提示しているのは(蛮勇をふるい、誤解を恐れず、一言でいい切るならば)、言葉それ自体が持つ要素を、その「音楽層」と「意味層」に分割し、それがヨーロッパの各時代の音楽に於いてどのように扱われたかを、大きな流れの中で概観する試みである。
言葉における「音楽層」とは、人間が発話する言葉の「音」そのものの次元である。イタリア語やドイツ語が持つ響きの次元にとどまらず、言葉のアクセント、ひいては西洋詩学における抑揚がどのように音楽に影響を与えるか、といった分析であり、「意味層」とは、単語、あるいは単語の連なりとしての文章や作品全体がもつ「意味」が音楽の表現に与える影響である。フィグーレンレーレ(音型論)、あるいはライトモティーフや調性などによって、言葉の「意味」を音楽がどのように表現しているのか、そしてそれが歴史とともにどのように変遷したか、というこれまでの分析方法は、いわば、この「意味層」に大きく偏っていたものと言ってもよいだろう。言葉の持つ「音楽層」を、作曲家がどれまで意識してきたかについて、日本の研究者の関心が比較的薄かったことは否定のできない事実だろう(そして、このような本が書かれたということ自体、他の国での現状も日本とそれほど違わないのだろう)。本書が大きな意義を有するのは、まさにこの部分についての自覚を読者に促すためにほかならないのである。
とはいえ、日本でこの部分の研究が進まないのはやむを得ない事情もあった。西欧諸国の言葉に精通するだけでなく、各国で発達した詩学、言語学、音声学など、様々な分野に目配りして、ようやく研究のスタートラインに立てるのだから。母国語でない言葉を研究する、というそのことだけで、既に大きなハンディを抱えているのだから。
この本で挙げられているマレンツィオ、あるいはパレストリーナ、モンテヴェルディといったルネサンス、バロックの巨匠の作品においては、少なくとも言葉のアクセントに反する高低を用いた付曲(デュルはこれを「バーバリズム」と呼ぶ)は、注意深く避けられている。時代が下り、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルトに至るまで、この種の「バーバリズム」がおずおずとしか成されない点を見れば、言葉が音楽のありように大きな影響を保っていたことが容易に感得されよう。そして、デュルはこれらの巨匠が声楽作品に成した本質的な貢献の変遷を追い、言葉に作曲を施すという作業は、同時に歴史的な価値観の変遷を反映したものであったことも、明確に説いてみせるのである。その斬新な観点は、類書の追随を許さない。前回の小泉文夫でもお薦めした手法ではあるが、この本も各章の最後にはかならず「まとめ」が付されているので、まずは先に目を通し、その章でどのようなことが議論されるのかを、あらかじめ頭に入れておくと良いと思う。
このデュルの著書は、はっきり言って、これまで取り上げてきたどの本よりも骨があり、その言わんとするところを理解するには相当の困難を伴う。内容そのものが難しいというよりも、読者に要求される前提知識が実に広範に及び、その議論の全容を把握し、全体像を思い描くことができず、途方に暮れてしまう、といった類の絶望感を感じてしまうのだ。浅学菲才の評者には荷が重く、まさに、日暮れて道なお遠し、である。デュルの薫陶を受けた梶木喜代子による『ドイツ・リートへの誘い』は、デュルと同じ問題意識を共有してはいるが、その懇切丁寧な筆致によって、より親しみやすい本となっている。同書は、基本的には声楽家に向けて執筆された本であり、日本人が愛し、親しんできた有名なドイツ歌曲を選び、発音指導、楽曲解説、演奏のポイント、作曲家の人となりを知るコラムなどから構成されている。言葉そのものが持つ響きが音楽に与えた影響を論じる、という観点こそ、著者がデュルから教示を受けた部分だと思われる。デュルの大作に挑む前の、よき「準備体操」となるだろう。

マドリガーレからリートまで 『声楽曲の作曲原理』 言語と音楽の関係をさぐる
『言語と音楽:歴史・ジャンル・分析モデル』という原題をもつ本書は、14世紀から20世紀にいたる声楽史の研究書であり、かつ「声楽」について体系的に論じたジャンル論である。それぞれの時代の音楽家たちが声楽というジャンルをどのようにとらえていたか、また、言語と音楽の関係についてどのように考え、作曲をしていたかが、時代を追って明らかにされている。そして、ルカ・マレンツィオのマドリガーレをはじめ、パレストリーナのミサ曲、モンテヴェルディのオペラ、シュッツの宗教曲、バッハのカンタータ、モーツァルト、ベートーヴェンのオペラ、シューベルトのリート、そしてシュネーベルのモテットなどの実例とその分析は、本書を分析法の模範的なテクストとしている。