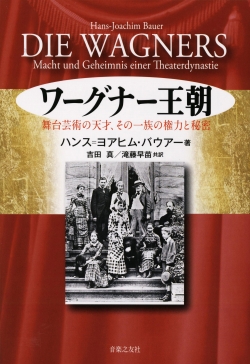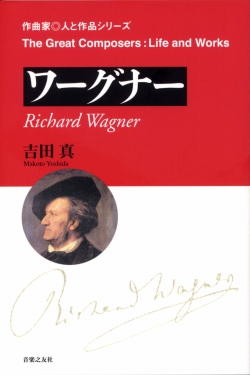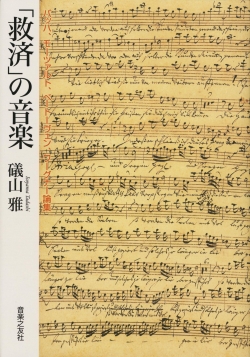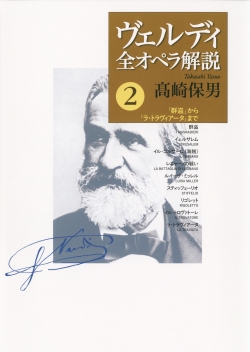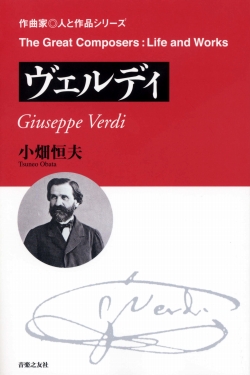第21回 生誕200年!オペラの巨匠ワーグナー&ヴェルディ
リヒャルト・ワーグナー、そしてジュゼッペ・ヴェルディ、ドイツとイタリアを代表するオペラの巨匠が揃って生誕200年を迎えている。個人的にもたいへん深く、深く関わってきたオペラの作曲家ということもあり、今年は各所で個人的な想い出を垂れ流している。「極私的ワーグナーへの愛情吐露」についてはこちらに執筆したのでここでは繰り返さないが、いずれにしても彼らがいなければ、いまここでこのような文章を書く仕事に就いていなかったことは確かであり、いまの自分を作ってくれた大恩人でもある。
音楽だけ聴けば正反対のようにも思える個性を持つふたりではあるが、他者に自分の芸術的信念を強制し、不屈の精神でそれを貫き通した、という意味では、両者はまったく変わるところはない。それまでは、ただひたすらに仕え、生活のために膝を屈し続けた存在であった王侯貴族にさえへつらわず、むしろその芸術の前に彼らをひれ伏させた。壮年期から社会的地位を築き上げ、毀誉褒貶に晒され、ついには晩年に揺るぎない名声を確立する。
純然たる成功者としての生涯を送ったふたりはまた、たゆまなき努力の人でもあった。作曲家の日常は、日々ピアノに向かって音を紡ぎ、それを五線譜の上に写し取る。一旦作曲が終わっても、次はそれをオーケストラの譜面に移し替えるという、気の遠くなるような「単純作業」が待ち受ける。強靱な個性はまた、その作業を淡々とこなすことのできる強靱な精神力・勤勉さと表裏一体の関係でもあるだろう。
このようなふたりの足跡を知るためには、やはりトモシャが誇る『作曲家◎人と作品』シリーズに教えを乞うのがもっとも手っ取り早い。例によってその生涯と作品を分けて叙述するそのスタイルによって、伝記的事実と主要作品の内容が系統立てて理解できるよう工夫されており、作曲家の事績を知るために真っ先にひもとくべき本であることに、いまもって変わりはない。吉田真氏の筆致がストイックなのに対し、小畑恒夫氏の筆致が情熱に溢れているのは、やはりドイツとイタリア、それぞれの特性を引きうつしているのかもしれない(!)。
ワーグナーの芸術が時を超え、異なる文化を超えて広まっていく過程では、その遺族たち、とりわけ妻のコジマ・ワーグナーと息子ジークフリート、そして孫のヴィーラント、ヴォルフガングが多大なる役割を果たした。作曲家の子孫が、ここまで偉大なる祖先の業績を護っていくということそのものに類例がない。それはまさに代々受け継がれる「王朝」の名にふさわしかろう。『ワーグナー王朝』の初代国王リヒャルト・ワーグナー。本書のはじめ三分の一では、この王朝の建国物語、つまり王朝が崇め奉るハコ(バイロイト祝祭劇場)とイレモノ(《ニーベルングの指環》《パルジファル》など楽劇の数々)が完成するまでの通史を説き、作曲家ワーグナーの人生を振り返っている。だが、本書でひもとくべきは、むしろこの後に続く三分の二であろう。ワーグナーの妻コジマ、息子ジークフリートと妻ヴィニフィレート、そして孫ヴィーラントとヴォルフガング、この歴代の「国王」たちが、自身の全存在をかけて、偉大な初代国王が遺したハコとイレモノのみならず、初代国王その人を、そしてその血筋を引く自らをも神格化しようと試み、それに曲がりなりにも成功した記録である。戦後におけるヴィーラントによる「新バイロイト様式」演出、あるいはヴォルフガングによる新しい演出家・指揮者の招聘など、高く評価されるべき事績には事欠かないが、王朝につきまとうスキャンダルをも赤裸々に描くという点で、類書とは異なる光芒を放っている。
筆者がヴェルディの作品に対し、ワーグナーに耽溺した10代後半の頃に同じような興奮を覚えなかった理由を、敢えて他責的(=ひとのせい)に考えるならば、それは歴史面・音楽面双方からの詳しい考察を施した研究書・解説書の類が本当に乏しかったことにも、その一因があるとも思う。その意味でも、長年オペラに携わり続けてこられた高崎保男氏が、満を持して執筆を続けておられる『ヴェルディ全オペラ解説』(1・2巻)は、そんな長年の渇きを払拭してくれる大著となるはず(現在は全3巻予定のうち第2巻、《ラ・トラヴィアータ》までが発売されている)。奇をてらうような、扇情的な文章のそぶりは微塵も感じられない。舞台で接することが難しい《リゴレット》以前の作品についても、作品の意義に始まり、成立と初演、原作について、台本、登場人物、あらすじ、音楽解説、これ以上ないほどの正統的な手段を踏んで、懇切丁寧な解説が付される。対象に接し、それを扱う時の眼差しの優しさ、そして真摯さには強く胸を打たれる。とりわけ第3作目にして出世作となった《ナブッコ》を、「仮にもし、彼が《ナブッコ》以後全くオペラを書かなかったと仮定しても(中略)、ヴェルディの名は《ナブッコ》ただひとつだけでさえ、19世紀イタリア・オペラの歴史に特筆大書されたに相違ない」と激賞する。近年の資料研究の成果がこうしたかたちで手軽にアクセスできるようになったことを、素直に喜ばずにはいられない。
ヴェルディに比べれば、ワーグナーについて書かれている本は増殖の一途を辿っているようにすら見える。初心者向けから研究者向けまで、その数は留まるところを知らず、去年から今年にかけてはさらに増え続けている。一生をかけても読み切れないことだけは確実である(!)。礒山雅氏の『「救済」の音楽』では、ワーグナー作品の根幹を成す思想のひとつである「救済」という概念について、その概念を真正面から取り扱う《パルジファル》とともに考察し続けた氏の論考をまとめて読むことができる。学術的な論文集ではあるが、聖なる世界=全音階、魔の世界=半音階というワーグナーの描きわけに始まる広大な音楽の全貌が、さまざまなアプローチによって示され、読者に作品理解への手がかりを与えてくれる。この世界になじみのない聴き手にとっては新鮮な指摘となるはずであり、《パルジファル》に精通した聴き手にとっても、この作品が様々な解釈の可能性を残す懐の深い音楽で彩られていることに、あらためて驚嘆の念を覚えるであろう。とりわけ氏は、本作がキリスト教世界のことを描く内容であるにもかかわらず(アムフォルタスがキリストに重ね合わされているにもかかわらず)、その「キリスト」ということばが作中に登場しないという点にワーグナーの問題意識を求めている。この作品がキリスト教社会の成立以前(原始キリスト教)の世界を描くものであり、ワーグナー自身が当時のキリスト教社会に幻滅・絶望していたことを考え合わせれば、氏の主張の背後には、実に示唆に富む世界が広がっていると感じられるはず。そしてこうした問題意識が、ベートーヴェン、モーツァルトを遡り、氏の専門であるバッハにまでたち戻る複眼的な視点を与えてくれる。

「救済」の音楽 バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、ワーグナー論集
『魂のエヴァンゲリスト』(辻荘一賞)、『マタイ受難曲』(京都音楽賞)などのバッハ研究や、『モーツァルト/二つの顔』、訳書のN.ザスラウ著『モーツァルトのシンフォニー』などにまとめられたモーツァルト研究をはじめ、充実の書で読者の篤い信頼を獲得している氏による音楽論集。今回の書は、全体を大きく3つに分け、もっとも得意とするバッハ論に比重を置きながらも、モーツァルト論とベートーヴェン論が2本ずつ収められた「古典派の音楽」、第3章には「ロマン派の音楽」として、氏がクラシック音楽に親しむ切っ掛けとなったもう一人の敬愛する作曲家、ワーグナーについての長年の研究成果が今回初めてまとめられている。なかでも氏の最も関心の深いテーマ「キリスト教と音楽」を扱った《パルジファル》について多くのページが割かれている。
ヴェルディ全オペラ解説・2 「群盗」から「ラ・トラヴィアータ」まで
日本を代表するオペラ研究家・評論家、高崎保男によるヴェルディ全オペラ解説の第2巻。処女作「オベルト」から「マクベス」までの10作品を収めた第1巻につづく、「群盗」から「ラ・トラヴィアータ」までのヴェルディ中期9作品を収めている。当巻では中期のみならずヴェルディの全作品のなかでも特に人気と作品の充実度の高い三部作「リゴレット」「イル・トロヴァトーレ」「ラ・トラヴィアータ」を含み、作品の位置づけと意義、成立と初演の事情や時代背景、台本、あらすじ、登場人物、音楽解説など、詳細な解説および作品論をおさめている。第1巻と同様、氏が長年にわたって書き続けてきたレコード解説等をベースに最新の研究成果を盛り込んだものや、あらたに書き下ろしたものでまとめたもの。